2014年02月18日
大和の国・纏向を歩く③(纏向古墳群からJR巻向駅)
「山の辺の道」と分かれて間もなく、左手に大神神社の大鳥居や大和三山が見える。
工事中の道を右往左往しながら、田圃の中にポツンとある社?を発見。
20数年ぶりの再開。 周辺の景色は随分と変わったような・・・。
東に三輪山の全貌が見える。
狐塚古墳(方墳?。一辺40m以上?)
畦道をJR線に向かって進む。
小さな果樹園の中、畑の作業小屋のような建物の西側に封土がなく剥き出しになっている石室が現われる。
あいにく今回も玄室は水浸しで入れない。 羨道まで下りた後、石室の周囲を見学。

弁天社古墳(墳形不明)
茅原の集落内、家々に囲まれて富士神社・厳島神社(弁天社)がある。その境内の左(南)側に石造り基壇の上に立つ社の裏に封土のない石室が露出しており、北側の天井石が外されたところから羨道部の家形石棺の蓋石を確認できる。
玄室の幅約1.7m、長さ約2.3m。
石室前の案内表示に、
「弁天社古墳は封土が既に失われ、現在は玄室が露出している。 発掘調査が行われていないため詳細なことは不明だが、石室は南に羨道をもつ両袖式の横穴式石室である。 玄室内には既に破壊された石棺の破片があり、羨道部には立派な家形石棺が安置されている。 石棺は凝灰岩を刳り抜いて造られたもので裏側には盗掘の際の穴があけられている。 この古墳は、古墳時代後期の古墳が多い三輪山麓の中でも石棺の残る珍しい例の一つである。」とある。


ここで気になったのは、境内に入って右側のお堂。左に馬頭観音?、右は・・・錫杖のクロスは何?。
この2体の石仏に挟まれてお祀りされている「石」、これは何??

茅原大墓古墳(全長約86m。後円部径約72m。この数値は最新のもので、以下の案内表示の数値とは乖離している。)
茅原集落の北端に所在する古墳時代中期初頭(4C末)頃の帆立貝式古墳。 平成22年の発掘調査後に整備されている。
これまでの調査で葺石、埴輪列、埴輪棺などが検出されている。 このなかで埴輪には、円筒埴輪、蓋形埴輪や壺形埴輪のほか形象埴輪(入れ墨表現のある盾持人埴輪、鶏(水鳥?)形埴輪)がある。
墳丘裾の案内に、
「この古墳は、三輪山の西麓に築かれた、帆立貝式の前方後円墳である。墳丘部全長約66m、後円部径約56m、前方部幅約29mで、箸中古墳群の中では、「箸墓古墳」に次ぐ規模をもっている。墳丘には葺石とともに円筒埴輪が樹立していたらしく、破片が散乱している。 また、周囲に周濠の痕跡をとどめている。この古墳の築造年代は5世紀と考えられる。帆立貝式の古墳は全国でも数が少なく、古墳時代中期の墓制を考える上で貴重な古墳である。」と説明されている。(※ 古墳の規模等の数値の齟齬は、案内板の作成以後において新たなデータが公表されたことによる。)
※ 古墳時代における茅原大墓古墳の位置
3Cの古墳出現期から大型古墳が築造されてきた奈良盆地東南部だが、4C後半以降になると大型古墳の築造の中心は奈良盆地北部や河内地域に移ってしまう。これは、政権内における勢力変動を反映したものと考えられている。茅原大墓古墳は、こうした奈良盆地東南部の勢力が衰退していく時期、その最後に築造された古墳であり、それ以前の大型古墳より小さい86mという墳丘規模に時代背景が示されている。
帆立貝式の古墳形態は、4C末頃から多く見られるようになる。これは、この時期に前方後円墳の築造が『規制』されるようになった結果、創出されたものと考えられる。
※ 盾持人埴輪
他の形象埴輪と異なり、古墳の外縁部に置かれる例が多く、外部の邪悪なものから古墳を守る辟邪の意味を持たせている?
これまでに50ヶ所以上の古墳・遺跡から出土。とくに、関東地方が多い。大半は5C後半~6C。これまで、4C末~5C前半の拝塚古墳(福岡市)や5C前半の墓山古墳(羽曳野市・藤井寺市)の盾持埴輪が最古の例とされていたが、これらに先行する時期のものとみられ、人物を造形した埴輪としても最も古いものと位置づけられる。 茅原大墓古墳での人物埴輪の出現は、古墳時代中期中頃以降に埴輪祭祀が盛行する契機となった。
茅原大墓古墳の周辺にいくつかの小古墳が確認できる。墳丘に立つと溜池のある地形などから周濠の痕跡を確認できる。
また、この古墳から北西方向に多くの古墳が集在していることも確認できる。例えば、ごく近くにも、西から北へ毘沙門塚古墳(前方後円墳。全長45m)・ツヅロ塚古墳(円墳。径約30m)・ツクロ塚古墳(円墳。径約10m)など・・・。 田圃の中を北に向かう。
この辺り、地図を見ると100mほどの間隔をもって東西方向に道が何本も走っていることを確認できる、条里遺構。
ホケノ山古墳を目指して北進する。箸中集落内にある北石神塚古墳(円墳?)は、草地になっており全くそれと分からない姿。
集落の北、纏向川を渡ったところの右手に三輪山慶雲寺(浄土宗)がある。境内に弥勒菩薩を刻んだ石棺仏。
阿蘇の凝灰岩製ということなのだが・・・わずかに赤紫色がかっている?ということは、石切場でみた色よりかなり薄いが「ピンク石(馬門石)」??・・・ということは、6C前半~中頃の古墳が近くにある??

本堂の脇の狭い所を通って裏に回ると円墳との間に石室が開口している、慶運寺裏古墳(円墳?。径13m)
境内にある案内には、
「後世の開発によって墳丘が改変され墳形は不明であるが、南面する円墳と考えられる。石室は乱石積によって構築された両袖式の横穴式石室で、長さ約3m、幅1.8m、高さ約2m、羨道の一部は削り取られている。 本堂の西側には、建治型と呼ばれる弥勒菩薩を刻んだ刳抜式石棺の身があるが、慶雲寺周辺にはかつて6基前後の後期古墳が存在していたようで、いずれの古墳に属していたか、はっきりしない。」とある。

慶運寺を出て纏向川沿いに西行する。最初の角を右折すると眼前にホケノ山古墳。
ホケノ山古墳
墳丘裾の案内表示、
「この古墳はホケノ山古墳と呼ばれる3世紀後半に造られた日本でも最も古い部類に属する前方後円墳の一つです。 古墳は東方より派生した緩やかな丘陵上に位置し、古墳時代前期の大規模集落である纏向遺跡の南東端に位置します。 また、古墳からは以前に画文帯神獣鏡と内行花文鏡が出土したとの伝承がありますが、その実態は良く分かっていません。 平成7年以降、古墳の史跡整備に先立って2次に亙る発掘調査が行われ、様々な事柄が解っています。 合計12本設定された調査区の中では周濠や葺石・周辺埋葬に伴う木棺の跡・沢山の土器片などが出土しました。 周濠は第一次調査の第一トレンチでは幅17.5mで、最も狭い所では第二次調査の第二トレンチの幅10.5mと西側に行くほど幅が狭くなっています。 葺石は墳丘側の総ての調査区において確認されています。 葺石の構造は地山を削り出しによって整形した後、二層の裏込め土を盛った上に、付近から採取できる河原石を小型・中型・大型の順で葺いています。 ただし、前方部側面は墳丘の傾斜が30度前後と、後円部の40~50度という急傾斜に対して極端に緩やかにつくられていました。 また、周濠や墳丘は前方部前面が旧纏向川によって削平されており、本来の規模や形状などははっきりしませんが、全長は85m前後と考えています。今回復元している前方部については調査において確認された地山の削り出しに、本来あったはずの裏込め土や葺石を括れ部のデーターを基にして復元したものです。」
墳丘裾に組合せ式木棺が復元されており「前方部東斜面検出の埋葬施設」として以下のような説明がある。
「ここに復元しているのは第二次調査において確認された埋葬施設です。墓壙の規模は全長4.2m、幅1.2m、残存する深さは30~50cmになります。 墓壙内には南端に大型複合口縁壺が、中央には底部を穿孔した広口壺が共存し、これに挟まれるように全長2.15m、幅45cm、現存する深さ15cmの組合せ式木棺の痕跡が確認されました。 また、木棺内部の南側からは40×45cmの範囲に薄く撒かれた水銀朱も検出されています。 これらの状況からこの墓壙は埋葬に木棺を用い、複合口縁を有する大型壺・底部に穿孔のある広口壺を供献した埋葬施設であることが確認されました。 この埋葬施設は葺石をはずして、裏込め土から地山まで掘り込んで作られており、墳丘が完成した後に設置されたものと考えております。 また、構築の年代については供献土器以外には全く副葬品が見られなかったため、供献土器の年代に頼らざるを得ません。 これらの土器は、概ね3世紀後半の中に治まるものであり、他の墳丘や周濠に伴って出土した土器の年代と大きく矛盾することはないと考えています。」
さらに、「周濠状遺構」についての説明もなされている。
ホケノ山古墳の東に先刻の慶雲寺があり、北に北口塚古墳(円墳?。径約25m)・茶ノ木塚古墳(円墳?。径約28m)が並んでおり、すぐ西には、堂ノ後古墳(前方後円墳。全長60m以上)。ホケノ山から纏向川まで戻って堂ノ前古墳の横をとおり国津神社の裏にある堂ノ後古墳の墳丘に至る。案内には、
「纏向地域から茅原の地域にかけての丘陵部には、有名な珠城山古墳群や箸墓古墳、茅原大墓古墳などがあるが、この地域にはほかに20数基の中・小規模の古墳が散在している。数基の方墳のほかは古墳時代後期の円墳と見られ、中には前方後円形を呈するものもいくつかあるようだ。堂ノ後古墳もこれらの古墳群の中の一つで、調査が行われていないため詳細は不明だが、径35m程度の円墳のようだ。」(※ 現在は前記のように当該古墳の形体・大きさ等の評価が案内表示とは異なっている。)
手前:ホケノ山の墳丘上、中:堂ノ後古墳、奥:箸墓古墳
再び纏向川に戻り国津神社(箸中字湯屋垣内)に入る。
祭神は、素戔嗚尊の五男神である正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊、天穂日命、天津彦根命、活津彦根命、熊野樟櫲樟日命。 合祭神として、素戔嗚尊。(『日本書紀』神代・上 素戔鳴尊、乞取天照大神髻鬘及腕所纒八坂瓊之五百箇御統、濯於天眞名井、然咀嚼、而吹棄氣噴之狹霧所生神、號曰正哉吾勝勝速日天忍穗耳尊。次天穗日命是出雲臣・土師連等祖也、次天津彥根命是凡川內直・山代直等祖也、次活津彥根命、次熊野櫲樟日命、凡五男矣。)
天津神を祀っているのに、何故、『国津』神社? 出雲系の神々がどこかに隠れている??
境内の案内には、
「当國津神社は、古来より「地主の森」といい、天照大神の御子神5柱を祭神としています。 この男神5柱は、『記紀』神話によると、素戔嗚尊が天照大神と天の安河を中にはさんで誓約をしたとき、天照大神の玉を物実として成り出でた神であります。 ちなみに纏向河下流の芝の国津神社(九日神社)には、素戔嗚尊の剣を物実として生まれた奥津島比売、市杵島比売、多岐津比売の3女神を祭祀しています。この箸中と芝で、神の三輪山を水源とする纏向川をはさみ、2神の誓約によって成り出でた神をそれぞれ祭神としていることに、古代神話伝承の原景をみる思いがします。 なお古来より毎年8月28日には、大字箸中と芝が相集い、三輪山の麓に鎮座する檜原神社(祭神:天照大神)の大祭を執行しています。 また『日本書紀』崇神天皇6年の条に「天照大神・倭大国魂2神を天皇の大殿の内に並祭る。 然して其の神の勢を畏りて」ともに住みたまふに安からず。 故、天照大神を以ては、豊鍬入姫命に託けまつりて、倭の笠縫邑に祭る」とあり、ここ箸中の東、三輪山麓の地は天照大神の伊勢鎮座以前の宮居のあった笠縫邑の伝承地となっています。 天照大神の祭祀に奉じた豊鍬入姫命は崇神天皇の皇女で、その墓所が国津神社裏のホケノ山古墳であるという伝承が地元に伝わっています。」とある。
この神社が『太陽の道』(北緯34度32分線)の上にあることは既述。
箸中の国津神社を出て、JR線を越えて西進し箸墓古墳・上ツ道・芝の集落などをとおり、西池の南東堤上にあるもう一つの芝の国津神社に向かう。 古い家並みの間の狭い路地のような道。
国津神社(九日社)
西池の南東堤上にある。
拝殿横にある立板によると、祭神は多紀理比賣命、狭依理比賣命、多岐津比賣命の宗像三女神となっている。
これら3柱の女神は、天照大神が素戔嗚尊の十拳剣(『日本書紀』では十握剣)を取って3つに折って天の眞名井で振りすすいで噛んで吹き出した霧から生まれたという。(『日本書紀』神代・上 天照大神、乃索取素戔鳴尊十握劒、打折爲三段、濯於天眞名井、然咀嚼[然咀嚼、此云佐我彌爾加武]而吹棄氣噴之狹霧[吹棄氣噴之狹霧、此云浮枳于都屢伊浮岐能佐擬理所]生神、號曰田心姫。次湍津姫、次市杵嶋姫、凡三女矣。・・・古事記もほぼ同じ内容であるが、3女神の名は多紀理毘賣命(奧津嶋比賣命)・市寸嶋(上)比賣命(狹依毘賣命)・次多岐都比賣命。)
社殿は東面し、板塀の中に流造、千鳥破風付、銅板葺の本殿があり、前に切妻造、瓦葺の拝殿がある。
境内の石燈籠や手水鉢には、「九日社」と刻まれている。
拝殿の前、狭い境内を北へ進むと正面に、陰陽石が祀られている。
例祭は十月九日・・・で、九日社? ではなく、秋の収穫祭において、神のコトヨサシによって労き励んで作った結果、この通り収穫できましたと神の御前に新穀を捧げてお祭りする「(御)供日」「(お)くにち・くんち」に因んだ?
神社の前の道、真東に三輪山を望める。
本日の散策はここまで。帰路は箸墓古墳の後円部裾をとおりJR巻向駅へ。
この日の歩行時間:5時間弱。 総歩数:25,907歩。
なお、参考記事の多くは桜井市立埋蔵文化財センターの現地説明会資料等に依る。
【追記】 ホケノ山周辺の古墳について
従来、纒向遺跡の東端のホケノ山古墳周辺の小古墳の多くは6世紀の円墳と見られていたが近年の測量調査や研究成果で纒向型の前方後円墳の可能性が高い事が判明。
この周辺にある6基の古墳(南飛塚古墳、ツゾロ塚古墳、堂ノ後古墳、北口塚古墳、平塚古墳、小川塚東古墳)も前方後円墳の可能性あり。
工事中の道を右往左往しながら、田圃の中にポツンとある社?を発見。
20数年ぶりの再開。 周辺の景色は随分と変わったような・・・。
東に三輪山の全貌が見える。
狐塚古墳(方墳?。一辺40m以上?)
畦道をJR線に向かって進む。
小さな果樹園の中、畑の作業小屋のような建物の西側に封土がなく剥き出しになっている石室が現われる。
あいにく今回も玄室は水浸しで入れない。 羨道まで下りた後、石室の周囲を見学。
弁天社古墳(墳形不明)
茅原の集落内、家々に囲まれて富士神社・厳島神社(弁天社)がある。その境内の左(南)側に石造り基壇の上に立つ社の裏に封土のない石室が露出しており、北側の天井石が外されたところから羨道部の家形石棺の蓋石を確認できる。
玄室の幅約1.7m、長さ約2.3m。
石室前の案内表示に、
「弁天社古墳は封土が既に失われ、現在は玄室が露出している。 発掘調査が行われていないため詳細なことは不明だが、石室は南に羨道をもつ両袖式の横穴式石室である。 玄室内には既に破壊された石棺の破片があり、羨道部には立派な家形石棺が安置されている。 石棺は凝灰岩を刳り抜いて造られたもので裏側には盗掘の際の穴があけられている。 この古墳は、古墳時代後期の古墳が多い三輪山麓の中でも石棺の残る珍しい例の一つである。」とある。
ここで気になったのは、境内に入って右側のお堂。左に馬頭観音?、右は・・・錫杖のクロスは何?。
この2体の石仏に挟まれてお祀りされている「石」、これは何??
茅原大墓古墳(全長約86m。後円部径約72m。この数値は最新のもので、以下の案内表示の数値とは乖離している。)
茅原集落の北端に所在する古墳時代中期初頭(4C末)頃の帆立貝式古墳。 平成22年の発掘調査後に整備されている。
これまでの調査で葺石、埴輪列、埴輪棺などが検出されている。 このなかで埴輪には、円筒埴輪、蓋形埴輪や壺形埴輪のほか形象埴輪(入れ墨表現のある盾持人埴輪、鶏(水鳥?)形埴輪)がある。
墳丘裾の案内に、
「この古墳は、三輪山の西麓に築かれた、帆立貝式の前方後円墳である。墳丘部全長約66m、後円部径約56m、前方部幅約29mで、箸中古墳群の中では、「箸墓古墳」に次ぐ規模をもっている。墳丘には葺石とともに円筒埴輪が樹立していたらしく、破片が散乱している。 また、周囲に周濠の痕跡をとどめている。この古墳の築造年代は5世紀と考えられる。帆立貝式の古墳は全国でも数が少なく、古墳時代中期の墓制を考える上で貴重な古墳である。」と説明されている。(※ 古墳の規模等の数値の齟齬は、案内板の作成以後において新たなデータが公表されたことによる。)
※ 古墳時代における茅原大墓古墳の位置
3Cの古墳出現期から大型古墳が築造されてきた奈良盆地東南部だが、4C後半以降になると大型古墳の築造の中心は奈良盆地北部や河内地域に移ってしまう。これは、政権内における勢力変動を反映したものと考えられている。茅原大墓古墳は、こうした奈良盆地東南部の勢力が衰退していく時期、その最後に築造された古墳であり、それ以前の大型古墳より小さい86mという墳丘規模に時代背景が示されている。
帆立貝式の古墳形態は、4C末頃から多く見られるようになる。これは、この時期に前方後円墳の築造が『規制』されるようになった結果、創出されたものと考えられる。
※ 盾持人埴輪
他の形象埴輪と異なり、古墳の外縁部に置かれる例が多く、外部の邪悪なものから古墳を守る辟邪の意味を持たせている?
これまでに50ヶ所以上の古墳・遺跡から出土。とくに、関東地方が多い。大半は5C後半~6C。これまで、4C末~5C前半の拝塚古墳(福岡市)や5C前半の墓山古墳(羽曳野市・藤井寺市)の盾持埴輪が最古の例とされていたが、これらに先行する時期のものとみられ、人物を造形した埴輪としても最も古いものと位置づけられる。 茅原大墓古墳での人物埴輪の出現は、古墳時代中期中頃以降に埴輪祭祀が盛行する契機となった。
茅原大墓古墳の周辺にいくつかの小古墳が確認できる。墳丘に立つと溜池のある地形などから周濠の痕跡を確認できる。
また、この古墳から北西方向に多くの古墳が集在していることも確認できる。例えば、ごく近くにも、西から北へ毘沙門塚古墳(前方後円墳。全長45m)・ツヅロ塚古墳(円墳。径約30m)・ツクロ塚古墳(円墳。径約10m)など・・・。 田圃の中を北に向かう。
この辺り、地図を見ると100mほどの間隔をもって東西方向に道が何本も走っていることを確認できる、条里遺構。
ホケノ山古墳を目指して北進する。箸中集落内にある北石神塚古墳(円墳?)は、草地になっており全くそれと分からない姿。
集落の北、纏向川を渡ったところの右手に三輪山慶雲寺(浄土宗)がある。境内に弥勒菩薩を刻んだ石棺仏。
阿蘇の凝灰岩製ということなのだが・・・わずかに赤紫色がかっている?ということは、石切場でみた色よりかなり薄いが「ピンク石(馬門石)」??・・・ということは、6C前半~中頃の古墳が近くにある??
本堂の脇の狭い所を通って裏に回ると円墳との間に石室が開口している、慶運寺裏古墳(円墳?。径13m)
境内にある案内には、
「後世の開発によって墳丘が改変され墳形は不明であるが、南面する円墳と考えられる。石室は乱石積によって構築された両袖式の横穴式石室で、長さ約3m、幅1.8m、高さ約2m、羨道の一部は削り取られている。 本堂の西側には、建治型と呼ばれる弥勒菩薩を刻んだ刳抜式石棺の身があるが、慶雲寺周辺にはかつて6基前後の後期古墳が存在していたようで、いずれの古墳に属していたか、はっきりしない。」とある。
慶運寺を出て纏向川沿いに西行する。最初の角を右折すると眼前にホケノ山古墳。
ホケノ山古墳
墳丘裾の案内表示、
「この古墳はホケノ山古墳と呼ばれる3世紀後半に造られた日本でも最も古い部類に属する前方後円墳の一つです。 古墳は東方より派生した緩やかな丘陵上に位置し、古墳時代前期の大規模集落である纏向遺跡の南東端に位置します。 また、古墳からは以前に画文帯神獣鏡と内行花文鏡が出土したとの伝承がありますが、その実態は良く分かっていません。 平成7年以降、古墳の史跡整備に先立って2次に亙る発掘調査が行われ、様々な事柄が解っています。 合計12本設定された調査区の中では周濠や葺石・周辺埋葬に伴う木棺の跡・沢山の土器片などが出土しました。 周濠は第一次調査の第一トレンチでは幅17.5mで、最も狭い所では第二次調査の第二トレンチの幅10.5mと西側に行くほど幅が狭くなっています。 葺石は墳丘側の総ての調査区において確認されています。 葺石の構造は地山を削り出しによって整形した後、二層の裏込め土を盛った上に、付近から採取できる河原石を小型・中型・大型の順で葺いています。 ただし、前方部側面は墳丘の傾斜が30度前後と、後円部の40~50度という急傾斜に対して極端に緩やかにつくられていました。 また、周濠や墳丘は前方部前面が旧纏向川によって削平されており、本来の規模や形状などははっきりしませんが、全長は85m前後と考えています。今回復元している前方部については調査において確認された地山の削り出しに、本来あったはずの裏込め土や葺石を括れ部のデーターを基にして復元したものです。」
墳丘裾に組合せ式木棺が復元されており「前方部東斜面検出の埋葬施設」として以下のような説明がある。
「ここに復元しているのは第二次調査において確認された埋葬施設です。墓壙の規模は全長4.2m、幅1.2m、残存する深さは30~50cmになります。 墓壙内には南端に大型複合口縁壺が、中央には底部を穿孔した広口壺が共存し、これに挟まれるように全長2.15m、幅45cm、現存する深さ15cmの組合せ式木棺の痕跡が確認されました。 また、木棺内部の南側からは40×45cmの範囲に薄く撒かれた水銀朱も検出されています。 これらの状況からこの墓壙は埋葬に木棺を用い、複合口縁を有する大型壺・底部に穿孔のある広口壺を供献した埋葬施設であることが確認されました。 この埋葬施設は葺石をはずして、裏込め土から地山まで掘り込んで作られており、墳丘が完成した後に設置されたものと考えております。 また、構築の年代については供献土器以外には全く副葬品が見られなかったため、供献土器の年代に頼らざるを得ません。 これらの土器は、概ね3世紀後半の中に治まるものであり、他の墳丘や周濠に伴って出土した土器の年代と大きく矛盾することはないと考えています。」
さらに、「周濠状遺構」についての説明もなされている。
ホケノ山古墳の東に先刻の慶雲寺があり、北に北口塚古墳(円墳?。径約25m)・茶ノ木塚古墳(円墳?。径約28m)が並んでおり、すぐ西には、堂ノ後古墳(前方後円墳。全長60m以上)。ホケノ山から纏向川まで戻って堂ノ前古墳の横をとおり国津神社の裏にある堂ノ後古墳の墳丘に至る。案内には、
「纏向地域から茅原の地域にかけての丘陵部には、有名な珠城山古墳群や箸墓古墳、茅原大墓古墳などがあるが、この地域にはほかに20数基の中・小規模の古墳が散在している。数基の方墳のほかは古墳時代後期の円墳と見られ、中には前方後円形を呈するものもいくつかあるようだ。堂ノ後古墳もこれらの古墳群の中の一つで、調査が行われていないため詳細は不明だが、径35m程度の円墳のようだ。」(※ 現在は前記のように当該古墳の形体・大きさ等の評価が案内表示とは異なっている。)
手前:ホケノ山の墳丘上、中:堂ノ後古墳、奥:箸墓古墳
再び纏向川に戻り国津神社(箸中字湯屋垣内)に入る。
祭神は、素戔嗚尊の五男神である正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊、天穂日命、天津彦根命、活津彦根命、熊野樟櫲樟日命。 合祭神として、素戔嗚尊。(『日本書紀』神代・上 素戔鳴尊、乞取天照大神髻鬘及腕所纒八坂瓊之五百箇御統、濯於天眞名井、然咀嚼、而吹棄氣噴之狹霧所生神、號曰正哉吾勝勝速日天忍穗耳尊。次天穗日命是出雲臣・土師連等祖也、次天津彥根命是凡川內直・山代直等祖也、次活津彥根命、次熊野櫲樟日命、凡五男矣。)
天津神を祀っているのに、何故、『国津』神社? 出雲系の神々がどこかに隠れている??
境内の案内には、
「当國津神社は、古来より「地主の森」といい、天照大神の御子神5柱を祭神としています。 この男神5柱は、『記紀』神話によると、素戔嗚尊が天照大神と天の安河を中にはさんで誓約をしたとき、天照大神の玉を物実として成り出でた神であります。 ちなみに纏向河下流の芝の国津神社(九日神社)には、素戔嗚尊の剣を物実として生まれた奥津島比売、市杵島比売、多岐津比売の3女神を祭祀しています。この箸中と芝で、神の三輪山を水源とする纏向川をはさみ、2神の誓約によって成り出でた神をそれぞれ祭神としていることに、古代神話伝承の原景をみる思いがします。 なお古来より毎年8月28日には、大字箸中と芝が相集い、三輪山の麓に鎮座する檜原神社(祭神:天照大神)の大祭を執行しています。 また『日本書紀』崇神天皇6年の条に「天照大神・倭大国魂2神を天皇の大殿の内に並祭る。 然して其の神の勢を畏りて」ともに住みたまふに安からず。 故、天照大神を以ては、豊鍬入姫命に託けまつりて、倭の笠縫邑に祭る」とあり、ここ箸中の東、三輪山麓の地は天照大神の伊勢鎮座以前の宮居のあった笠縫邑の伝承地となっています。 天照大神の祭祀に奉じた豊鍬入姫命は崇神天皇の皇女で、その墓所が国津神社裏のホケノ山古墳であるという伝承が地元に伝わっています。」とある。
この神社が『太陽の道』(北緯34度32分線)の上にあることは既述。
箸中の国津神社を出て、JR線を越えて西進し箸墓古墳・上ツ道・芝の集落などをとおり、西池の南東堤上にあるもう一つの芝の国津神社に向かう。 古い家並みの間の狭い路地のような道。
国津神社(九日社)
西池の南東堤上にある。
拝殿横にある立板によると、祭神は多紀理比賣命、狭依理比賣命、多岐津比賣命の宗像三女神となっている。
これら3柱の女神は、天照大神が素戔嗚尊の十拳剣(『日本書紀』では十握剣)を取って3つに折って天の眞名井で振りすすいで噛んで吹き出した霧から生まれたという。(『日本書紀』神代・上 天照大神、乃索取素戔鳴尊十握劒、打折爲三段、濯於天眞名井、然咀嚼[然咀嚼、此云佐我彌爾加武]而吹棄氣噴之狹霧[吹棄氣噴之狹霧、此云浮枳于都屢伊浮岐能佐擬理所]生神、號曰田心姫。次湍津姫、次市杵嶋姫、凡三女矣。・・・古事記もほぼ同じ内容であるが、3女神の名は多紀理毘賣命(奧津嶋比賣命)・市寸嶋(上)比賣命(狹依毘賣命)・次多岐都比賣命。)
社殿は東面し、板塀の中に流造、千鳥破風付、銅板葺の本殿があり、前に切妻造、瓦葺の拝殿がある。
境内の石燈籠や手水鉢には、「九日社」と刻まれている。
拝殿の前、狭い境内を北へ進むと正面に、陰陽石が祀られている。
例祭は十月九日・・・で、九日社? ではなく、秋の収穫祭において、神のコトヨサシによって労き励んで作った結果、この通り収穫できましたと神の御前に新穀を捧げてお祭りする「(御)供日」「(お)くにち・くんち」に因んだ?
神社の前の道、真東に三輪山を望める。
本日の散策はここまで。帰路は箸墓古墳の後円部裾をとおりJR巻向駅へ。
この日の歩行時間:5時間弱。 総歩数:25,907歩。
なお、参考記事の多くは桜井市立埋蔵文化財センターの現地説明会資料等に依る。
【追記】 ホケノ山周辺の古墳について
従来、纒向遺跡の東端のホケノ山古墳周辺の小古墳の多くは6世紀の円墳と見られていたが近年の測量調査や研究成果で纒向型の前方後円墳の可能性が高い事が判明。
この周辺にある6基の古墳(南飛塚古墳、ツゾロ塚古墳、堂ノ後古墳、北口塚古墳、平塚古墳、小川塚東古墳)も前方後円墳の可能性あり。
下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
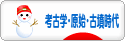
にほんブログ村
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
にほんブログ村
大和の国を歩く ~ 本薬師寺
飛鳥へ ~ 都塚古墳を訪ねる
奈良・春日山原始林を歩く
大和の国を訪ねる(2)・・・多神社・多遺跡、新沢千塚古墳群、室大墓へ
大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その3)
大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その2)
飛鳥へ ~ 都塚古墳を訪ねる
奈良・春日山原始林を歩く
大和の国を訪ねる(2)・・・多神社・多遺跡、新沢千塚古墳群、室大墓へ
大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その3)
大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その2)










