2014年02月17日
大和の国・纏向を歩く②(相撲神社・兵主神社から桧原神社を経て纏向古墳群)
「山の辺の道」沿いにある森岡観光果樹園から少し入った兵主神社の参道脇に景行天皇の纏向日代宮跡伝承地の碑がある。穴師山から西に伸びた二つの尾根(珠城山古墳群のある尾根とクノボ古墳・立子古墳・立子塚古墳・立石古墳・渋谷向山古墳などのある尾根)に囲まれた谷の入口付近の布留式期の中枢地域が展望できる。
相撲神社
穴師坐兵主神社の鳥居の南。
野見宿禰と當麻蹶速が展覧相撲を行なった処とか(「書紀」第11代・垂仁天皇7年)
境内には、小さな祠、勝利の聖である野見宿禰を描いた真新しい石碑、力士像、そして4本の細い桜の木に囲まれた空間=土俵?など。
案内板にご当地カタヤケシの由緒が案内板に記載されている。
「今を去る上古約2千年前、垂仁天皇7年7月乙亥(7日)大兵主神社神域内小字カタヤケシにおきまして野見宿彌、當麻蹶速による日本最初の勅命展覧相撲が催されました。これが世界に誇るわが国国技相撲の遮光であります。・・・。」
さらに、別の案内が「国技発祥の地 天覧角力開祖 相撲神社」として、
「国に国家、国花があるが如く日本の国技は相撲である。相撲はもとは神の信仰から出て、国土安穏、五穀豊穣を祈る平和と繁栄の祭典であり、第11代垂仁帝の7年、野見宿彌と当麻蹶速が初めて天皇の前で相撲をとり相撲節(7月7日)となり、それがもとで後世、宮中の行事となった。 昭和37年10月6日、大兵主神社に日本相撲協会時津風理事長(元横綱双葉山)を祭主に2横綱(大鵬、柏戸)5大関(琴ヶ浜、北葉山、栃ノ海、佐田ノ山、栃光)をはじめ、幕内全力士が参列。相撲発祥の地で顕彰大祭がおこなわれ、この境内のカタヤケシゆかりの土俵に於いて手数入りが奉納された。」とある。
※ 『カタヤケシ』って?
カタヤ(=方屋)は、① 相撲・競べ馬などで左右・東西に分かれた力士・騎手などの控え所 ②相撲の土俵場。 ケシ(=気色)は、物事のようす、自然界のありさま。という意なので、『相撲の土俵がある地』っていうことかな??
なお、野見宿禰の墓は、十二神社(桜井市出雲)の境内にある。その辺りが垂仁天皇から下賜された鍛地?
※ 力比べ(角力の元祖:「書紀」垂仁天皇7年秋7月7日)
おそばの者が申し上げるには、「当麻邑に勇敢な人がいます。當麻蹶速といい、力が強くて角を折ったり、曲がった鈎をのばしたりします。人々に『四方に求めても自分の力に並ぶ者はいない。 何とかして強力の者に会い、生死を問わず力比べをしたい』と言っています。」
天皇はこれをお聞きになり群卿たちに「當麻蹶速は天下の力持ちだという。これに敵う者がいるだろうか。」と言われた。
ひとりの臣が「出雲国に野見宿禰という勇士がいると聞いています。この者を蹶速に取り組ませてみたらいかがでしよう。」と進言した。その日に倭直の祖・長尾市を遣わして野見宿禰を呼ばれた。出雲からやってきた野見宿禰と當麻蹶速に角力させた。互いに足を挙げて蹴りあい、野見宿禰は當麻蹶速のあばら骨を踏み砕き、そしてその腰の骨を踏みくじいて殺した。天皇は、當麻蹶速の土地を没収して、すべて野見宿禰に与えられた。これがその邑に腰折田(山裾の折れ曲った田)のあるわけである。野見宿禰はそのまま留まって天皇にお仕えした。
※ 野見宿禰と埴輪(野見宿禰は土師連らの先祖:日本書紀巻第六 活目入彥五十狹茅天皇 垂仁天皇)
七年秋七月己巳朔乙亥、左右奏言、當麻邑有勇悍士。曰當摩蹶速。其爲人也、强力以能毀角申鉤。恆語衆中曰、於四方求之、豈有比我力者乎。何遇强力者、而不期死生、頓得爭力焉。天皇聞之、詔群卿曰、朕聞、當摩蹶速者、天下之力士也。若有比此人耶。一臣進言、臣聞、出雲國有勇士。曰野見宿禰。試召是人、欲當于蹶速。卽日、遣倭直祖長尾市、喚野見宿禰。於是、野見宿禰自出雲至。則當摩蹶速與野見宿禰令捔力。二人相對立。各舉足相蹶。則蹶折當摩蹶速之脇骨。亦蹈折其腰而殺之。故奪當摩蹶速之地、悉賜野見宿禰。是以其邑有腰折田之緣也。野見宿禰乃留仕焉。
28年冬10月5日 天皇の母の弟・倭彦命亡くなる。
11月2日 倭彦命を身狭の桃花鳥坂に葬る。 この時、近習の者を集めて全員を生きたまま陵の周りに埋めた。日を経ても死なず昼夜泣き呻いた。ついには死んで腐って犬や鳥が集まり食べた。
天皇は、この泣き呻く声を聞かれ心を痛められ、それ以後の殉死を止めるように言われた。
32年秋7月6日、皇后・日葉酢媛命が亡くなられた。天皇は群卿に詔して「殉死は良くないことは前に分かった。今度の葬りはどうしようか。」と言われた。 野見宿禰が進んで「君主の陵墓に生きている人を埋め立てるのは良くないことです。 これから後、この土物をもって生きた人に替え陵墓に立てることを後世の決まりとしましよう。」と言って、出雲国から呼んだ土部100人を使って埴土で人や馬などいろいろな物の形を作って天皇に献上した。天皇は大いに喜ばれ、その土物をはじめて日葉酢媛命の墓に立てた。よって、この土物を名づけて埴輪あるいは立物といった。
天皇は、野見宿禰の功を誉められて鍛地(かたしところ。陶器を成熟させる土地)を授け、土師の職に任じられた。それで本姓を改めて土師臣という。これが土師連らが天皇の喪葬を司るいわれである。
廿八年冬十月丙寅朔庚午、天皇母弟倭彥命薨。十一月丙申朔丁酉、葬倭彥命于身狹桃花鳥坂。於是、集近習者、悉生而埋立於陵域。數日不死、晝夜泣吟。遂死而爛臰之。犬烏聚噉焉。天皇聞此泣吟之聲、心有悲傷。詔群卿曰、夫以生所愛、令殉亡者、是甚傷矣。其雖古風之、非良何從。自今以後、議之止殉。
卅二年秋七月甲戌朔己卯、皇后日葉酢媛命一云、日葉酢根命也。薨。臨葬有日焉。天皇詔群卿曰、從死之道、前知不可。今此行之葬、奈之爲何。於是、野見宿禰進曰、夫君王陵墓、埋立生人、是不良也。豈得傳後葉乎。願今將議便事而奏之。則遣使者、喚上出雲國之土部壹佰人、自領土部等、取埴以造作人・馬及種種物形、獻于天皇曰、自今以後、以是土物更易生人、樹於陵墓、爲後葉之法則。天皇、於是、大喜之、詔野見宿禰曰、汝之便議、寔洽朕心。則其土物、始立于日葉酢媛命之墓。仍號是土物謂埴輪。亦名立物也。仍下令曰、自今以後、陵墓必樹是土物、無傷人焉。天皇厚賞野見宿禰之功、亦賜鍛地。卽任土部職。因改本姓、謂土部臣。是土部連等、主天皇喪葬之緣也。所謂野見宿禰、是土部連等之始祖也。
相撲神社前の鳥居下を通り参道を進むと右の山腹にいくつかの境内社を見つつ進むと三連屋根の前に建つ拝殿がある。その横に小さな祠が集在している。稲田姫社・須勢理姫社、水社・橘社・稲荷社・須佐之男社、八王子社・祖霊社。祓戸社。
穴師坐兵主神社参道の登り石段の脇にある案内「大兵主神社 大和国 穴師坐兵主神社」には、
「御祭神 若御魂神社(右) 兵主神社(中) 大兵主神社(左)
御創建 崇神天皇60年
御由緒 当社は3神殿にして、古典の伝えるところによると、今より、2千年前の御創建にかかり、延喜の制で名神大社に列せられ、祈年、月次、相嘗、新嘗のもろもろの官幣に預り、元禄5年には正一位の宣旨を賜った最高の社格をもつ大和一の古社である。
御神徳 衣食住を守護し、風水を司る。」
とある。
この説明に加えて拝殿には、
「中央の神は、第十代崇神天皇の60年、命を受けて皇女倭姫命が創建され、天皇の御膳の守護神として祀られ、御食津神と申し上げ、生産と平和の神、又、知恵の神として崇敬を受けられました。
右の神は、天孫降臨の際の三種の神器を御守護された稲田姫命をお祀りし、芸能の神として崇敬を受けられておられます。
左の神は、第十二代垂仁天皇の御代に当地で初めて天覧相撲が催され、ご神体の矛にちなみ武勇の神とし相撲の祖神としてスポーツ界の信仰をお受けになっておられます。」
といったメモ書きが掲示されている。
当地は元々、大兵主神社(下社)の故地であって、東の斎月岳(弓月岳)山上にあった上社の兵主神社が応仁の乱(1467~77年)により焼失したため下社に合祀したものとのこと。 若御魂神社も纏向山の都谷にあったものを応仁の乱などの争乱で荒廃したので、上社と同じ頃に下社に遷したとのこと。
上社のあったところはゲシノオオダイラ(夏至の大平)と呼ばれ、山頂・上社・下社・箸墓中軸が一直線に並んでおり、箸墓から見て斎月岳山頂に太陽が昇る時期を夏至として稲の生育を祈念する農工祭祀をおこなったのではないかと推測される・・・。機会を得て、一度、登ってみたいものだ。
万葉集にも「痛足河 々浪立奴 巻目之 由槻我高仁 雲居立有良志(穴師川川波立ちぬ巻向の弓月が岳に雲居立てるらし)」、「足引之 山河之瀬之 響苗尓 弓月高 雲立渡(あしひきの山川の瀬の鳴るなへに弓月が岳に雲立ちわたる)」などと詠われている。
なお、ご神体は、上社が日矛、下社が鈴之矛、ということで気になるのは「天日矛」との関連・・・さて~?
森岡観光果樹園から「山の辺の道」を通る。この辺りは20数年ぶり、道も整備され随分イメージが変わった。 それでも舗装されておらず拡幅もされていない道もあり懐かしく、何故かホッとする。
展望も良く、金剛・葛城の山嶺をはじめ、二上山、生駒山のTV塔なども見える。
大和の青垣
「夜麻登波 久尓能麻本呂婆 多多那豆久 阿袁加岐 夜麻碁母禮流 夜麻登志宇流波斯 (大和は国のまほろば たたなづく青垣 山ごもれる大和し 美し)」と倭建命が謳った国思歌(古事記歌謡31)の景色。奈良盆地が、生駒山地や矢田丘陵、纏向・三輪の山々などで幾重にも緑の垣根に囲まれたようになっている風景が望める。
三気大神神社
ネットでは、固く閉ざされた不気味な神社、新興宗教、近寄り難いので足早に通り過ぎた・・・などと酷評した記事がたくさんあったのだが、参道の表示がある門扉は開いていた。 特段の断り書きもないので信者でなくても入って良いのだろうか?
「大空からりと晴れわたる 雲霧遮るものもなく ゆるゆると これこその 平坦な道を 人の一生を 平穏無事を 甘露の天の道に 自ら学び取り 足りないところ 粗末なところ 物事の善悪を 見分ける眼識を持って事を致せ。」との掲示あり。
桧原神社
日本書紀崇神天皇6年条(巻第五 御間城入彥五十瓊殖天皇 崇神天皇)に、
六年、百姓流離。或有背叛。其勢難以德治之。是以、晨興夕惕、請罪神祇。先是、天照大神・倭大國魂二神、並祭於天皇大殿之內。然畏其神勢、共住不安。故以天照大神、託豐鍬入姬命、祭於倭笠縫邑。仍立磯堅城神籬。神籬、此云比莽呂岐。亦以日本大國魂神、託渟名城入姬命令祭。
とある。即ち、
百姓が流離するもの、反逆するものがあり、その勢いは徳をもって治めようとしても難しかった。 それで朝夕天神地祇に祈った。 これから先、天照大御神と大和大国魂神の二神を御殿内にお祀りした。 ところが、あまりの強力な霊威のある二神を同社に祀ることはかえって人に禍をもたらしたので、崇神天皇はこの二神を他所に祀ることを決心した。天照大御神は豊鍬入姫命に託され、倭笠縫邑に遷し祀られた。 そして堅固な神籬を造った。 日本大國魂神は渟名城入姬命に託し祀られた(現在の大和神社?)。
とのこと。
境内の案内表示には「元伊勢 桧原神社と豊鍬入姫宮の御由緒」として、
「大神神社の摂社「桧原神社」は、天照大御神を、末社の「豊鍬入姫宮」(向かって左の建物)は崇神天皇の皇女、豊鍬入姫命をお祀りしています。 第10代崇神天皇の御代まで、皇祖である天照大御神は宮中にて「同床共殿」でお祀りされていました。同天皇の6年初めて皇女、豊鍬入姫命(初代の斎王)に託され宮中を離れ、この「倭笠縫邑」に「磯城神籬」を立ててお祀りされました。 その神蹟は実にこの桧原の地であり、大御神の伊勢御遷幸の後もその御蹟を尊祟し、桧原神社として大御神を引続きお祀りしてきました。 そのことより、この地を今に「元伊勢」と呼んでいます。 桧原神社はまた日原社とも称し、古来社頭の規模などは本社である大神神社に同じく、三ツ鳥居を有していることが室町時代以来の古図に明らかであります。 萬葉集には「三輪の桧原」とうたわれ山の辺の道の歌枕となり、西につづく桧原台地は大和国中を一望できる景勝の地であり、麓の茅原・芝には「笠縫」の古称が残っています。 また「茅原」は、日本書紀崇神天皇7年条の「神浅茅原」の地とされています。 更に西方の箸中には、豊鍬入姫命の御陵と伝えるホケノ山古墳(内行花文鏡出土・社蔵)があります。」と記されている。
また、三ツ鳥居の前にある案内に「大神神社摂社 桧原神社」として、
「御祭神 天照大神 若御魂神 伊弉諾命 伊弉冊命
御由緒 第10代崇神天皇の御代、それまで皇居で祀られていた「天照大御神」を皇女豊鍬入姫命に託したここ桧原の地(倭笠縫邑)に遷しお祀りしたのが始まりです その後、大神様は第11代垂仁天皇25年に永久の宮居を求め各地を巡行され、最後に伊勢の五十鈴川の上流に御鎮まり、これが伊勢の神宮(内宮)の創祀と云われる」とある。
この三ツ鳥居の前には豊鍬入姫を祀った「大神神社末社 豊鍬入姫宮」の小さな祠があり御由緒として、
「御祭神は、第10代崇神天皇の皇女であります 皇女は「天照大御神」をこの「倭笠縫邑」にお遷しし、初代の御杖代(斎王)として奉仕されたその威徳を尊び奉り、昭和61年11月5日に創祀されたものであります 斎王とは天皇にかわって大神様にお仕えになる方で、その伝統は脈々と受け継がれ、現代に於いても皇室関係の方がご奉仕されています」とある。
東に三輪山をご神体して建つ桧原神社に社殿はなく、北・西・南の3ヶ所の境内への入口すべては(鳥居)ではなく〆柱である。
三ツ鳥居の奥、三輪山山上にかけて8群の神籬・磐座があるとのこと、地形図でみると尾根筋になっており、江戸時代の古絵図には登山路や建物が描かれているのだが・・・果たして?
※ 萬葉集「三輪の桧原」
1092 動神之 音耳聞 巻向之 桧原山乎 今日見鶴鴨
(鳴る神の音のみ聞きし巻向の桧原の山を今日見つるかも)
1093 三毛侶之 其山奈美尓 兒等手乎 巻向山者 継之宜霜
(三諸のその山なみに子らが手を巻向山は継ぎしよろしも)
1118 古尓 有險人母 如吾等架 弥和乃桧原尓 挿頭折兼
(いにしへにありけむ人も我がごとか三輪の桧原にかざし折りけむ)
1119 徃川之 過去人之 手不折者 裏觸立 三和之桧原者
(行く川の過ぎにし人の手折らねばうらぶれ立てり三輪の桧原は)
※ 日本書紀崇神天皇7年条(日本書紀巻第五 御間城入彥五十瓊殖天皇 崇神天皇)
七年春二月丁丑朔辛卯、詔曰、昔我皇祖、大啓鴻基。其後、聖業逾高、王風轉盛。不意、今當朕世、數有災害。恐朝無善政、取咎於神祇耶。蓋命神龜、以極致災之所由也。於是、天皇乃幸于神淺茅原、而會八十萬神、以卜問之。是時、神明憑倭迹々日百襲姬命曰、天皇、何憂國之不治也。若能敬祭我者、必當自平矣。天皇問曰、教如此者誰神也。答曰、我是倭國域內所居神、名爲大物主神。時得神語、隨教祭祀。然猶於事無驗。天皇乃沐浴齋戒、潔淨殿內、而祈之曰、朕禮神尚未盡耶。何不享之甚也。冀亦夢裏教之、以畢神恩。是夜夢、有一貴人。對立殿戸、自稱大物主神曰、天皇、勿復爲愁。國之不治、是吾意也。若以吾兒大田々根子、令祭吾者、則立平矣。亦有海外之國、自當歸伏。
秋八月癸卯朔己酉、倭迹速神淺茅原目妙姬・穗積臣遠祖大水口宿禰・伊勢麻績君、三人共同夢、而奏言、昨夜夢之、有一貴人、誨曰、以大田々根子命、爲祭大物主大神之主、亦以市磯長尾市、爲祭倭大國魂神主、必天下太平矣。天皇得夢辭、益歡於心。布告天下、求大田々根子、卽於茅渟縣陶邑得大田々根子而貢之。天皇、卽親臨于神淺茅原、會諸王卿及八十諸部、而問大田々根子曰、汝其誰子。對曰、父曰大物主大神。母曰活玉依媛。陶津耳之女。亦云、奇日方天日方武茅渟祇之女也。天皇曰、朕當榮樂。乃卜使物部連祖伊香色雄、爲神班物者、吉之。又卜便祭他神、不吉。
玄賓庵
桓武・嵯峨天皇に厚い信任を得ながら、俗事を嫌い三輪山の麓に隠棲したという玄賓僧都の庵。世阿弥の作と伝える謡曲「三輪」の舞台として知られる。かつては山岳仏教の寺として三輪山の檜原谷にあったが、明治初期の神仏分離により現在地に移されたとのこと。
建物自体はそう古いものではないが、ここに漂う静寂の景色に安堵を覚える。
※ 謡曲「三輪」
三輪山麓に住む僧の玄賓(ゲンピン)が、いつも参詣に来る女を待つ。 その日、女は玄賓に衣を乞い、玄賓は衣を与え女の素性を尋ねる。 女は杉が目印だと住みかを教えて消える。 里の男がご神木に衣が掛かるのを見付けて玄賓に知らせ、玄賓が確かめると衣の裾に金色の文字で歌が書かれている。 その歌を詠むと杉木の中から返歌が聞え、女姿の三輪明神が姿を現す。 神も衆生を救うため欲深い人の心を持つことがあるので、その罪を助けて欲しいという。そして明神は三輪の神婚譚を語り、天照大神の岩戸隠れのときの神楽を舞う(伊勢と三輪の神が一体分神だと物語る)が、やがて夜が明けるとともに消えてゆく。
この後、「山の辺の道」と分かれ、西に向かって一気に下って行く。
・・・ この続きは「大和の国・纏向を歩く③」
下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
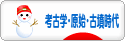
にほんブログ村
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
にほんブログ村
大和の国を歩く ~ 本薬師寺
飛鳥へ ~ 都塚古墳を訪ねる
奈良・春日山原始林を歩く
大和の国を訪ねる(2)・・・多神社・多遺跡、新沢千塚古墳群、室大墓へ
大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その3)
大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その2)
飛鳥へ ~ 都塚古墳を訪ねる
奈良・春日山原始林を歩く
大和の国を訪ねる(2)・・・多神社・多遺跡、新沢千塚古墳群、室大墓へ
大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その3)
大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その2)










