2014年08月17日
飛鳥へ ~ 都塚古墳を訪ねる
飛鳥と纏向、毎年、
互いに競うように『新発見!』という文字が躍る
大和盆地の東南エリアの考古の世界・・・
今回は、その最端部にある古墳の説明会に行ってきた。
スタートは、
この地方固有の大和棟を模した駅舎を持つことなどから
「近畿の駅百選」に選ばれた近鉄・橿原神宮駅の東口。


明日香周遊バス「かめバス(赤かめ)」に乗って石舞台BSへ。
(※ 写真は飛鳥資料館前BSのかめバス)

 ここから冬野川とその支流・都塚川に
ここから冬野川とその支流・都塚川に
ほぼ並行して緩やかな坂道を進むこと1時間ほど
(この日は見学の順番待ちのため・・・何もなければ10分ほど?)


以下、見学順路にしたがって主な調査区ごとに見ると

1区・・・墳丘裾北端の確認。幅1~1.5m、深さ≒0.4mの周濠。周濠護岸およびテラス面に拳~人頭大の石材。

3区・・・墳丘裾南西端の確認。1段目のテラス幅員≒6m。

 4区・・・墳丘2段目の西法面、高さ≒3m。
4区・・・墳丘2段目の西法面、高さ≒3m。
石室・・・南西に開口した両袖式横穴石室。全長=12.2m、玄室長=5.3m・幅=2.8m・高=3.55m、羨道長=6.9m・幅=1.9~2.0m・高≒2m。石材は、「飛鳥石(石英閃緑岩)」。玄室内に暗渠排水溝あり。

石棺・・・二上山凝灰岩製の刳抜式家形石棺。石棺の総高=1.74m。棺身長=2.23m・幅=1.46m・高=1.08m(内法長=1.74m・幅=0.82m・深=0.65m)


8区・・・墳丘裾南東端の確認。
7区・・・上部墳丘上の段状になった石積み4段を確認。

以下、都塚古墳の概要
6C後半。東西≒41m・南北≒42m・高≧4.5m(尾根先に築かれているため、西側からの見かけ上の高さは7m以上)。
古墳周辺は、6~7Cにおける蘇我氏の本拠地。


当初、都塚古墳を見学後、
ミニチュア竃などを出土した細川谷古墳群(蘇我氏の奥津城?)の探訪を予定していたが・・・
変更して、奈文研・飛鳥資料館へ。

前庭に置かれた
亀石・猿石、石人像、須弥山石など
飛鳥の石造物(レプリカ)は、いつ観ても楽しい~。













この日の歩行数 7,319歩
下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
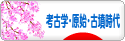
にほんブログ村
滋賀県内の遺跡・史跡などの探訪録は、
コチラ ⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2
互いに競うように『新発見!』という文字が躍る
大和盆地の東南エリアの考古の世界・・・
今回は、その最端部にある古墳の説明会に行ってきた。
スタートは、
この地方固有の大和棟を模した駅舎を持つことなどから
「近畿の駅百選」に選ばれた近鉄・橿原神宮駅の東口。


明日香周遊バス「かめバス(赤かめ)」に乗って石舞台BSへ。
(※ 写真は飛鳥資料館前BSのかめバス)

 ここから冬野川とその支流・都塚川に
ここから冬野川とその支流・都塚川にほぼ並行して緩やかな坂道を進むこと1時間ほど
(この日は見学の順番待ちのため・・・何もなければ10分ほど?)


以下、見学順路にしたがって主な調査区ごとに見ると

1区・・・墳丘裾北端の確認。幅1~1.5m、深さ≒0.4mの周濠。周濠護岸およびテラス面に拳~人頭大の石材。

3区・・・墳丘裾南西端の確認。1段目のテラス幅員≒6m。

 4区・・・墳丘2段目の西法面、高さ≒3m。
4区・・・墳丘2段目の西法面、高さ≒3m。石室・・・南西に開口した両袖式横穴石室。全長=12.2m、玄室長=5.3m・幅=2.8m・高=3.55m、羨道長=6.9m・幅=1.9~2.0m・高≒2m。石材は、「飛鳥石(石英閃緑岩)」。玄室内に暗渠排水溝あり。

石棺・・・二上山凝灰岩製の刳抜式家形石棺。石棺の総高=1.74m。棺身長=2.23m・幅=1.46m・高=1.08m(内法長=1.74m・幅=0.82m・深=0.65m)


8区・・・墳丘裾南東端の確認。
7区・・・上部墳丘上の段状になった石積み4段を確認。

以下、都塚古墳の概要
6C後半。東西≒41m・南北≒42m・高≧4.5m(尾根先に築かれているため、西側からの見かけ上の高さは7m以上)。
古墳周辺は、6~7Cにおける蘇我氏の本拠地。


当初、都塚古墳を見学後、
ミニチュア竃などを出土した細川谷古墳群(蘇我氏の奥津城?)の探訪を予定していたが・・・
変更して、奈文研・飛鳥資料館へ。

前庭に置かれた
亀石・猿石、石人像、須弥山石など
飛鳥の石造物(レプリカ)は、いつ観ても楽しい~。













この日の歩行数 7,319歩
下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
にほんブログ村
滋賀県内の遺跡・史跡などの探訪録は、
コチラ ⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2
2014年08月01日
奈良・春日山原始林を歩く
少し前のことだけれど、明後日は梅雨明け~という日、
イベントに参加して、原始林の中を歩いてきた。

原始林?、原生林??
ネットで検索すると、
「原生林(げんせいりん)はある程度昔から現在まで、伐採や災害などによって破壊(森林破壊)されたことがなく、またほとんど人手が加えられたことのない自然のままの森林をさす。それらが一切無いものを原始林というが、それに準ずるものである。」とのことだが、
「春日山原始林 - 古都奈良に存在する原生林(1998年世界遺産文化遺産)。」の記載もあり、意味不明~(笑)
これまで、登山などで『原生林』を多く訪ねてきたことはある。
それらの多くは、古代から人の手が入っていないような登山路すら満足にないブナ林や照葉樹林など・・・。
春日大社の山として禁伐令が841年に出されてから積極的に保護された結果、極相に達した原生林が6千年前から変わらず広がっているとのこと。
さて、雲行の怪しいなか、近鉄・奈良駅から路線バスに乗って、奈良公園へ。

道に迷いつつ春日大社近くの駐車場から遊歩道に入り、水谷川に沿って歩く。

川岸には趣のある茶店。


木々の間、緩やかな登りの続く道はやがて鎌研交番所に・・・。
駐車場の脇を西に進むと鶯塚古墳。

鹿の群れの横を通って若草山の山頂(342m)に到達。
あいにくの天気で遠望は利かなかったが、それでも山麓の東大寺をはじめ奈良市内は良く観えた。

若草山・・・山全体が芝生でおおわれている。
この芝生、日本固有のシバで、近畿では若草山付近が唯一の自生地とのこと。
ノシバの種は堅い殻に覆われており、鹿がシバの葉と共に種を食べても、鹿の歯と胃液による消化などから堅い殻が種を守る。
ただ守るだけでなく、鹿の胃に入ると、胃液と体温(40度程度)で殻は速やかに溶けて発芽できる状態になり、未消化の種は糞とともに山に散布されることにより、ノシバは発芽する。
このサイクルを繰り返し、古来よりこの地で生息してきたそうだ。
鶯塚古墳・・・5C、全長103m・前方部幅約50m・後円部径61m、二段築成の前方後円墳。
前方部に露出している葺石の確認ができる。
日本考古学の大先達・濱田耕作はここでも埴輪を採集したとか・・・。
後円部の墳丘上に享保13年(1733)に建てられたという「鶯陵」の顕彰碑がある。


清少納言が「枕草子」の第17段に、
陵(みささぎ)は うぐひすの陵(みささぎ)。柏原の陵。あめの陵。
と書いている「うぐひすのみささぎ」がここだとも・・・。
16代仁徳天皇の皇后、磐之媛命の墓は、現在、奈良市の北郊にある佐紀盾列古墳群のヒシアゲ古墳(平城坂上陵)が比定されている。
現在の位置に比定されたのは明治になってからで、それまでは「平城天皇陵」とされていたそうである。

ところで、この磐之媛命、葛城襲津彦の娘だが、なぜ仁徳天皇と離ればなれに葬られているのかというと・・・、「書紀」(巻第十一 大鷦鷯天皇 仁德天皇)によれば、皇后である磐之媛命が紀の国へ出かけている留守に、天皇は八田皇女を難波宮に呼び寄せて寵愛したので、怒った皇后はそれ以後、筒城宮(現・京都府綴喜郡)に入って天皇の求めにも応じず、その後その地で亡くなる。
「書紀」には、
卅五年夏六月、皇后磐之媛命、薨於筒城宮。
卅七年冬十一月甲戌朔乙酉、葬皇后於乃羅山。
即ち、
仁徳天皇35年夏6月、皇后磐之媛命は筒城宮でなくなられた。
37年冬11月12日、皇后をナラ山に葬った。
と、ごく簡単に記載している。
なお、磐之媛は、履中・反噬正・允恭の各天皇の母。
駐車場まで戻って春日奥山道路を進むと、直ぐに十八丁休憩所。
この休憩所の傍らにある石仏。
白粉を塗って、唇に紅が・・・悪戯?。
なんとも異様な顔になっていた。

花山・地蔵の背を過ぎ、春日奥山の最大の山桜の下を通り、さらに進むと谷から水音が聞こえてきた。


案内の石碑に導かれ、遊歩道から分れて下降すると落差10mほどの鶯の瀧。
滝の名は、この辺りで美しく囀る金色の小鳥を、神功皇后が「うぐいす」と名付け愛玩したことに、あるいは滝から落ちる水音がうぐいすの鳴声のように聞こえることに由来するともいわれているそうな・・・。

元の遊歩道に戻ると直ぐに大原橋休憩所。
ここに「春日山原始林」の石標が建っている。
その横からも鶯の瀧に至るルートがある。
変化のない樹林帯を進むと、間もなく芳山交番所。
ここでクルマの通る春日奥山道路と別れ、未舗装の「柳生街道(滝坂道)」を下るとやがて江戸時代に奈良奉行によって敷かれたという石畳道に・・・。

ここは、柳生の道場を目指す剣豪たちが往来した道。
そこの三叉路に高さ2mほどの首切地蔵が立っている。
柳生十兵衛の弟子・荒木又右衛門がためし切りしたと伝わるとおり、首のところは、真一文字にセメントで繋がれている様子。

原始林の中、能登川沿いに石畳道を下っていくと間もなく、磨崖仏・朝日観音。
真ん中に弥勒菩薩像、その両側に地蔵菩薩が刻まれている。
東面しており、朝日に映えるのでこの名が付いたとか・・・。

続いて、壁面に夕日観音。

そのすぐ先の道端に、崖から転がり落ちてきたのか、横向きの大日如来像・寝仏。

右手に古墳状の連なるマウンドを見ながら下ると白乳神社、飛鳥中学校、志賀直哉旧居を経て砥石町のBSに辿り着いた。


春日山原始林・・・寒地性植物群と亜熱帯性植物群など多様な植物相が評価された特別天然記念物。
また、春日大社や東大寺などの建造物群と合わせて世界文化遺産にも登録されている。


千年以上、手つかずの樹林の中を歩いていると自然の力・強風のためか、所々で幹の途中から折れた大木や根元から倒れた木々が目に付いた。
その中で育っているのがナギやナンキンハゼ。
これらの木々の出現によって春日山原始林の多様性が劣化し、春日山の照葉樹林も徐々に崩壊しつつあるのだろうか・・・。

この日の総歩行数:26,676歩
下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
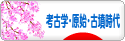
にほんブログ村
滋賀県内の遺跡・史跡などの探訪録は、
コチラ ⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2
イベントに参加して、原始林の中を歩いてきた。

原始林?、原生林??
ネットで検索すると、
「原生林(げんせいりん)はある程度昔から現在まで、伐採や災害などによって破壊(森林破壊)されたことがなく、またほとんど人手が加えられたことのない自然のままの森林をさす。それらが一切無いものを原始林というが、それに準ずるものである。」とのことだが、
「春日山原始林 - 古都奈良に存在する原生林(1998年世界遺産文化遺産)。」の記載もあり、意味不明~(笑)
これまで、登山などで『原生林』を多く訪ねてきたことはある。
それらの多くは、古代から人の手が入っていないような登山路すら満足にないブナ林や照葉樹林など・・・。
春日大社の山として禁伐令が841年に出されてから積極的に保護された結果、極相に達した原生林が6千年前から変わらず広がっているとのこと。
さて、雲行の怪しいなか、近鉄・奈良駅から路線バスに乗って、奈良公園へ。

道に迷いつつ春日大社近くの駐車場から遊歩道に入り、水谷川に沿って歩く。

川岸には趣のある茶店。


木々の間、緩やかな登りの続く道はやがて鎌研交番所に・・・。
駐車場の脇を西に進むと鶯塚古墳。

鹿の群れの横を通って若草山の山頂(342m)に到達。
あいにくの天気で遠望は利かなかったが、それでも山麓の東大寺をはじめ奈良市内は良く観えた。

若草山・・・山全体が芝生でおおわれている。
この芝生、日本固有のシバで、近畿では若草山付近が唯一の自生地とのこと。
ノシバの種は堅い殻に覆われており、鹿がシバの葉と共に種を食べても、鹿の歯と胃液による消化などから堅い殻が種を守る。
ただ守るだけでなく、鹿の胃に入ると、胃液と体温(40度程度)で殻は速やかに溶けて発芽できる状態になり、未消化の種は糞とともに山に散布されることにより、ノシバは発芽する。
このサイクルを繰り返し、古来よりこの地で生息してきたそうだ。
鶯塚古墳・・・5C、全長103m・前方部幅約50m・後円部径61m、二段築成の前方後円墳。
前方部に露出している葺石の確認ができる。
日本考古学の大先達・濱田耕作はここでも埴輪を採集したとか・・・。
後円部の墳丘上に享保13年(1733)に建てられたという「鶯陵」の顕彰碑がある。


清少納言が「枕草子」の第17段に、
陵(みささぎ)は うぐひすの陵(みささぎ)。柏原の陵。あめの陵。
と書いている「うぐひすのみささぎ」がここだとも・・・。
16代仁徳天皇の皇后、磐之媛命の墓は、現在、奈良市の北郊にある佐紀盾列古墳群のヒシアゲ古墳(平城坂上陵)が比定されている。
現在の位置に比定されたのは明治になってからで、それまでは「平城天皇陵」とされていたそうである。

ところで、この磐之媛命、葛城襲津彦の娘だが、なぜ仁徳天皇と離ればなれに葬られているのかというと・・・、「書紀」(巻第十一 大鷦鷯天皇 仁德天皇)によれば、皇后である磐之媛命が紀の国へ出かけている留守に、天皇は八田皇女を難波宮に呼び寄せて寵愛したので、怒った皇后はそれ以後、筒城宮(現・京都府綴喜郡)に入って天皇の求めにも応じず、その後その地で亡くなる。
「書紀」には、
卅五年夏六月、皇后磐之媛命、薨於筒城宮。
卅七年冬十一月甲戌朔乙酉、葬皇后於乃羅山。
即ち、
仁徳天皇35年夏6月、皇后磐之媛命は筒城宮でなくなられた。
37年冬11月12日、皇后をナラ山に葬った。
と、ごく簡単に記載している。
なお、磐之媛は、履中・反噬正・允恭の各天皇の母。
駐車場まで戻って春日奥山道路を進むと、直ぐに十八丁休憩所。
この休憩所の傍らにある石仏。
白粉を塗って、唇に紅が・・・悪戯?。
なんとも異様な顔になっていた。

花山・地蔵の背を過ぎ、春日奥山の最大の山桜の下を通り、さらに進むと谷から水音が聞こえてきた。


案内の石碑に導かれ、遊歩道から分れて下降すると落差10mほどの鶯の瀧。
滝の名は、この辺りで美しく囀る金色の小鳥を、神功皇后が「うぐいす」と名付け愛玩したことに、あるいは滝から落ちる水音がうぐいすの鳴声のように聞こえることに由来するともいわれているそうな・・・。

元の遊歩道に戻ると直ぐに大原橋休憩所。
ここに「春日山原始林」の石標が建っている。
その横からも鶯の瀧に至るルートがある。
変化のない樹林帯を進むと、間もなく芳山交番所。
ここでクルマの通る春日奥山道路と別れ、未舗装の「柳生街道(滝坂道)」を下るとやがて江戸時代に奈良奉行によって敷かれたという石畳道に・・・。

ここは、柳生の道場を目指す剣豪たちが往来した道。
そこの三叉路に高さ2mほどの首切地蔵が立っている。
柳生十兵衛の弟子・荒木又右衛門がためし切りしたと伝わるとおり、首のところは、真一文字にセメントで繋がれている様子。


原始林の中、能登川沿いに石畳道を下っていくと間もなく、磨崖仏・朝日観音。
真ん中に弥勒菩薩像、その両側に地蔵菩薩が刻まれている。
東面しており、朝日に映えるのでこの名が付いたとか・・・。

続いて、壁面に夕日観音。

そのすぐ先の道端に、崖から転がり落ちてきたのか、横向きの大日如来像・寝仏。

右手に古墳状の連なるマウンドを見ながら下ると白乳神社、飛鳥中学校、志賀直哉旧居を経て砥石町のBSに辿り着いた。


春日山原始林・・・寒地性植物群と亜熱帯性植物群など多様な植物相が評価された特別天然記念物。
また、春日大社や東大寺などの建造物群と合わせて世界文化遺産にも登録されている。


千年以上、手つかずの樹林の中を歩いていると自然の力・強風のためか、所々で幹の途中から折れた大木や根元から倒れた木々が目に付いた。
その中で育っているのがナギやナンキンハゼ。
これらの木々の出現によって春日山原始林の多様性が劣化し、春日山の照葉樹林も徐々に崩壊しつつあるのだろうか・・・。

この日の総歩行数:26,676歩
下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
にほんブログ村
滋賀県内の遺跡・史跡などの探訪録は、
コチラ ⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2
2014年07月20日
大和の国を訪ねる(2)・・・多神社・多遺跡、新沢千塚古墳群、室大墓へ
筒井城から多神社(多坐弥志理都比古神社)へ。

ここは、
太安万侶らをはじめとする
古代氏族多氏の本貫地?
この冬、
纏向遺跡など田原本町内を散策した折に、
夕刻タイムアウトになったため訪れることができなかった処。
書紀 巻第三 神日本磐余彥天皇 神武天皇に
辛酉年春正月庚辰朔、天皇卽帝位於橿原宮、是歲爲天皇元年。尊正妃爲皇后、生皇子神八井命・神渟名川耳尊。
とあり、
神武天皇が即位されたこと、皇子の神八井命と神淳名川耳尊(第三子、綏靖天皇)が生まれたことなどが記載されている。
さらに、巻第四 神渟名川耳天皇 綏靖天皇に
・・・神日本磐余彥天皇崩。・・・其庶兄手硏耳命、行年已長、久歷朝機。故、亦委事而親之。然其王、立操厝懷、本乖仁義、遂以諒闇之際、威福自由、苞藏禍心、圖害二弟。・・・。
冬十一月、神渟名川耳尊、與兄神八井耳命、陰知其志而善防之。至於山陵事畢、乃使弓部稚彥造弓、倭鍛部天津眞浦造眞麛鏃、矢部作箭。及弓矢既成、神渟名川耳尊、欲以射殺手硏耳命。會有手硏耳命於片丘大窨中獨臥于大牀、時渟名川耳尊、謂神八井耳命曰「今適其時也。夫言貴密、事宜愼、故我之陰謀、本無預者。今日之事、唯吾與爾自行之耳。吾當先開窨戸、爾其射之。」
因相隨進入、神渟名川耳尊、突開其戸。神八井耳命、則手脚戰慄、不能放矢。時神渟名川耳尊、掣取其兄所持弓矢而射手硏耳命、一發中胸、再發中背、遂殺之。於是、神八井耳命、懣然自服、讓於神渟名川耳尊曰「吾是乃兄、而懦弱不能致果。今汝特挺神武、自誅元惡。宜哉乎、汝之光臨天位、以承皇祖之業。吾當爲汝輔之、奉典神祇者。」是卽多臣之始祖也。
・・・四年夏四月、神八井耳命薨。卽葬于畝傍山北。
とあり、
神武天皇の崩御後、兄(第一子)の手硏耳命が権力を欲しいままにし、二人の弟(神八井耳命と神渟名川耳尊)を殺そうと企てたが、そのことを知った二人は・・・。ふるえおののいて矢を射ることができなかった神八井耳命の弓矢を神渟名川耳尊が取って胸と背中を射抜いて殺した。これを恥じて神八井耳命は皇位を神渟名川耳尊に譲った。・・・ことなどが記載されている。
多神社(多坐弥志理都比古神社)、「みしりつひこ(=神八井耳命)」。
神武天皇の子でありながら弟に皇位を譲ったので、「身を退いた」という意味?
もっとも、末子相続制の習俗を反映かな??っていう見方も・・・。
鳥居をくぐると、整然と並んだ石灯籠。

境内の左に築地塀で囲まれた神職の館。

正面、拝殿の後ろに春日造社殿1間社の本殿が東西に4殿並んでいる。
東の第一殿が神武天皇、第二殿が神八井耳命(神武天皇の長子。多氏の祖)、第三殿が神淳名川耳命(綏靖天皇)、第四殿が姫御神(玉依姫)を祀る。
本殿の後方に古代の祭祀場もしくは古墳と考えられている「神武塚」と呼ばれる小丘があるそうなのだが・・・鬱蒼と茂った林の中、塚の確認はできなかった。


鳥居まで戻ると、
その南東に 真新しい
「古事記」と刻んだ石柱と
小杜神社境内地図。
南に進むと古事記献上の碑。
平成24年(2012)に、『古事記』が編纂1300年を記念して建てられた。

杜の中に鎮座する小杜神社の祭神は、太安万侶。
30数年前に奈良市此瀬町の茶畑で火葬された骨や真珠が納められた木櫃と墓誌が出土したことから、この神社東方にある太安万侶の墓と伝える小円墳は見なかった。

小杜神社の南に、皇子神命神社。
林の中、忘れ去られたような古びた小さな祠が建っていた。

多神社周辺は、弥生時代から中世に至る時期の大規模な複合遺跡。
特に、弥生時代、長軸350m、短軸300mの規模をもつ拠点的な環濠集落であったと推定されている。
多神社の東約200m、集落の西のはずれに姫皇子命神社。
本殿(春日造)が東面(多神社及び他の摂社はすべて南面)しており、三輪山に昇る朝日が直射する位置、三輪山と向かいあうように建てられていた。
このあと、橿原市の新沢千塚古墳群と御所市の室大墓などを廻って帰宅。
前者の新沢千塚古墳群は、4世紀末から7世紀にかけて造営された600余基からなる大古墳群。
シルクロードの最東端にある古墳群からは、これまでペルシャ地方や中国東北部、朝鮮半島などからもたらされたとみられるガラス容器や金銀製の装身具などの副葬品が出土している。 20数年前、初めて訪ねたときは、正倉院御物の類似品が古墳から出土したことに驚いたことを思いだす。
以前あった資料館は、今春、博物館としてリニューアルオープンしていた。

後者の室大墓古墳(室宮山古墳)は、古墳時代中期前半、全長238m・後円部径105m・高さ25m・前方部幅110m・高さ22m、三段築成の巨大な前方後円墳。

孝安天皇室秋津島宮趾碑と八幡神社本殿の間の鳥居をくぐって斜面を登ると後円部の墳頂に出る。
竪穴式石室の天井石の一部がなく、そこから長持形石棺・縄掛突起が見えている。
これと並行して北側にも天井石が露出した竪穴式石室がある。

この日の探訪は、ここまで~。 走行キロ:202km、歩数:12,945歩。
下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
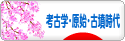
にほんブログ村
滋賀県内の遺跡・史跡などの探訪録は、
コチラ ⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2

ここは、
太安万侶らをはじめとする
古代氏族多氏の本貫地?
この冬、
纏向遺跡など田原本町内を散策した折に、
夕刻タイムアウトになったため訪れることができなかった処。
書紀 巻第三 神日本磐余彥天皇 神武天皇に
辛酉年春正月庚辰朔、天皇卽帝位於橿原宮、是歲爲天皇元年。尊正妃爲皇后、生皇子神八井命・神渟名川耳尊。
とあり、
神武天皇が即位されたこと、皇子の神八井命と神淳名川耳尊(第三子、綏靖天皇)が生まれたことなどが記載されている。
さらに、巻第四 神渟名川耳天皇 綏靖天皇に
・・・神日本磐余彥天皇崩。・・・其庶兄手硏耳命、行年已長、久歷朝機。故、亦委事而親之。然其王、立操厝懷、本乖仁義、遂以諒闇之際、威福自由、苞藏禍心、圖害二弟。・・・。
冬十一月、神渟名川耳尊、與兄神八井耳命、陰知其志而善防之。至於山陵事畢、乃使弓部稚彥造弓、倭鍛部天津眞浦造眞麛鏃、矢部作箭。及弓矢既成、神渟名川耳尊、欲以射殺手硏耳命。會有手硏耳命於片丘大窨中獨臥于大牀、時渟名川耳尊、謂神八井耳命曰「今適其時也。夫言貴密、事宜愼、故我之陰謀、本無預者。今日之事、唯吾與爾自行之耳。吾當先開窨戸、爾其射之。」
因相隨進入、神渟名川耳尊、突開其戸。神八井耳命、則手脚戰慄、不能放矢。時神渟名川耳尊、掣取其兄所持弓矢而射手硏耳命、一發中胸、再發中背、遂殺之。於是、神八井耳命、懣然自服、讓於神渟名川耳尊曰「吾是乃兄、而懦弱不能致果。今汝特挺神武、自誅元惡。宜哉乎、汝之光臨天位、以承皇祖之業。吾當爲汝輔之、奉典神祇者。」是卽多臣之始祖也。
・・・四年夏四月、神八井耳命薨。卽葬于畝傍山北。
とあり、
神武天皇の崩御後、兄(第一子)の手硏耳命が権力を欲しいままにし、二人の弟(神八井耳命と神渟名川耳尊)を殺そうと企てたが、そのことを知った二人は・・・。ふるえおののいて矢を射ることができなかった神八井耳命の弓矢を神渟名川耳尊が取って胸と背中を射抜いて殺した。これを恥じて神八井耳命は皇位を神渟名川耳尊に譲った。・・・ことなどが記載されている。
多神社(多坐弥志理都比古神社)、「みしりつひこ(=神八井耳命)」。
神武天皇の子でありながら弟に皇位を譲ったので、「身を退いた」という意味?
もっとも、末子相続制の習俗を反映かな??っていう見方も・・・。
鳥居をくぐると、整然と並んだ石灯籠。

境内の左に築地塀で囲まれた神職の館。

正面、拝殿の後ろに春日造社殿1間社の本殿が東西に4殿並んでいる。
東の第一殿が神武天皇、第二殿が神八井耳命(神武天皇の長子。多氏の祖)、第三殿が神淳名川耳命(綏靖天皇)、第四殿が姫御神(玉依姫)を祀る。
本殿の後方に古代の祭祀場もしくは古墳と考えられている「神武塚」と呼ばれる小丘があるそうなのだが・・・鬱蒼と茂った林の中、塚の確認はできなかった。


鳥居まで戻ると、
その南東に 真新しい
「古事記」と刻んだ石柱と
小杜神社境内地図。
南に進むと古事記献上の碑。
平成24年(2012)に、『古事記』が編纂1300年を記念して建てられた。

杜の中に鎮座する小杜神社の祭神は、太安万侶。
30数年前に奈良市此瀬町の茶畑で火葬された骨や真珠が納められた木櫃と墓誌が出土したことから、この神社東方にある太安万侶の墓と伝える小円墳は見なかった。

小杜神社の南に、皇子神命神社。
林の中、忘れ去られたような古びた小さな祠が建っていた。

多神社周辺は、弥生時代から中世に至る時期の大規模な複合遺跡。
特に、弥生時代、長軸350m、短軸300mの規模をもつ拠点的な環濠集落であったと推定されている。
多神社の東約200m、集落の西のはずれに姫皇子命神社。
本殿(春日造)が東面(多神社及び他の摂社はすべて南面)しており、三輪山に昇る朝日が直射する位置、三輪山と向かいあうように建てられていた。
このあと、橿原市の新沢千塚古墳群と御所市の室大墓などを廻って帰宅。
前者の新沢千塚古墳群は、4世紀末から7世紀にかけて造営された600余基からなる大古墳群。
シルクロードの最東端にある古墳群からは、これまでペルシャ地方や中国東北部、朝鮮半島などからもたらされたとみられるガラス容器や金銀製の装身具などの副葬品が出土している。 20数年前、初めて訪ねたときは、正倉院御物の類似品が古墳から出土したことに驚いたことを思いだす。
以前あった資料館は、今春、博物館としてリニューアルオープンしていた。

後者の室大墓古墳(室宮山古墳)は、古墳時代中期前半、全長238m・後円部径105m・高さ25m・前方部幅110m・高さ22m、三段築成の巨大な前方後円墳。

孝安天皇室秋津島宮趾碑と八幡神社本殿の間の鳥居をくぐって斜面を登ると後円部の墳頂に出る。
竪穴式石室の天井石の一部がなく、そこから長持形石棺・縄掛突起が見えている。
これと並行して北側にも天井石が露出した竪穴式石室がある。

この日の探訪は、ここまで~。 走行キロ:202km、歩数:12,945歩。
下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
にほんブログ村
滋賀県内の遺跡・史跡などの探訪録は、
コチラ ⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2
2014年06月28日
大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その3)
3度目、再々度の訪問は、前回のリベンジと石床神社の旧・社地探訪。

東光寺からは、前回と違って尾根に上がらず、谷筋を進む・・・
が、最後は、獣道を頼りに、苦労して急斜面を尾根に上がる。
尾根に上がった所は、石の集在している下側。
尾根を切って北の谷に向かって薄らと獣道が続いているようなので、これに従う。
幅10㎝にも満たないような細道を頼りに、谷を巻き、北の尾根下まで到達。
先人のブログの記事から、この尾根筋にあることを確信して登る。
集在している大石を過ぎて登ると、先日、辿り着いた尾根先の石の集在していた場所に出た。
船石は?

・・・石組みの下を通って船上神社跡に着く。
船石は、どこ・・・??

探索を諦めて、三里城跡に向かうことにした。
下山して登るのも嫌だったので、
山頂に上がり、尾根筋を行けば、先日の峠道に辿り着くはずと考え、
壁石下のガレ場を過ぎたところから山頂を目指す。
ん~。
あそこにも石が・・・、

大きい~、鯨?
ちょっとオーバーか・・・。


尾根に上がると・・・鯱のような船石。
尾根の下側ではなく、上側にあった。
あのブログ記事は~???
尾根の凸部に並んだ3本の花崗岩。

40度を超える急斜面、

今にも山を滑り下りようとするかのように頭を下に向けている。
L=6~9m・W=1~1.5、H=1~1.2m・・・かな?


船石の上部に、祭祀跡らしき石組み遺構。
さらに上ると、磐座のような石の集在。
北側は絶壁、そこに張り出した重箱積み様の岩などなど・・・。
予想どおり頂上部に尾根筋の道。
北に進む。

直ぐに、尾根が堀切のように切られ、
その北側のピークは細長い平坦地(郭か狼煙台の跡?)。
そして、また堀切・・・。
まもなく、足の踏み場がないほどの倒竹。

尾根筋の北進を諦め、右下を見ると輝く水面。
ブッシュを掻き分けて下りると水田が見え、やがて農家の裏に出た。
舗装道に出て、北に向かうと直ぐに白石畑集会所。

平群に向かう峠道の分岐まで来たところで、草刈りをしていたオヤジさんと談笑。
松尾寺まで30分ほどかかるとのこと。
諦めて峠道へ。
 峠、やはり笹竹の密生しているところは先刻の尾根道に続いている模様。
峠、やはり笹竹の密生しているところは先刻の尾根道に続いている模様。
三里城跡。
前回、峠道近くの削平地だけの確認で終わっていたので、
ブッシュを掻き分け、
横堀を左に見ながら北端沿いを進む。
2段ほど上がった所で前に進めず退却。
主郭まで到達できなかった。
雛壇状の削平地とその下部の堀跡らしきものの確認はできたが、
ブッシュが酷く縄張全体の確認は不可。

下山後、竜田川駅から石床神社の旧・社地を目指す。
人権交流センターから杜の南を巻くようにして進むと溜池・今池の南端に出る。
そこの道案内に従い越木塚集落の家々の間の細道を上り、
南に下ると集落の外れに石床神社の旧・社地。


鳥居の後ろにH≒6m、W≒10m(9m×18mとも)の岩壁。
中央割れ目の上部から垂れるような細長い岩とそれを下で受ける丸岩からなる磐座(陰石)。
今朝、見てきた矢田丘陵の船石(陽石?)に相応する大きさか・・・。
陰石を御神体として本殿のない古い信仰形態。
集落に戻り、案内表示に従って進み、
越木塚集会所の奥に石床神社。

大正時代に旧・社地から遷座、本殿前の右側に神篭石・・・石棒?が寄り掛かっている。

石床神社の頭上、南側に一段上がったところが消渇神社。

拝殿に並べられた土団子と米団子・・・


神社の石段下、鳥居横の小さな建物の壁に
「祈願のときは土の団子を十二個供えて、満願のときは米の団子を十二個供えて下さい」との説明書が掛けられ、
土団子を作り供えるための材料・道具一式が置かれている。
参道の説明板には、
「室町時代に、旅の僧信海が腰の病を治してもらってから下半身の病気に御利益があるとして村人に信仰されるようになる。
江戸時代には社名から女性の病気や性病に効果があるとして京都祇園からの参拝者もあり、参道に茶店が出るほど賑わったという。・・・。」
と書かれていた。
消渇神社を更に1段上がると崩れつつある築地塀に囲まれて七社神社の小さな祠。

境内を出て北に坂を下ったところに消渇神社の御神水。

「生水では飲まないで下さい」との注意書があるのだが・・・
良く観ると油が浮いて黄変している様子、とても飲む気にはなれない。

越木塚関取道標を過ぎて、十三街道?を四ツ辻古墳群に向かう。
案内表示がなく、ここでは~と思ったところからブッシュの中に駆け上がる。
右奥(西側)に径20mを超えそうなマウンド、南にまわってみたが石室は開口していない。

直ぐ南にも小さなマウンドが・・・
その墳丘の南側に、何とか拳が入るくらいの大きさで開口しているが・・・
石室内は見えず(四ツ辻2号墳? 径=9m)。

諦めて帰りかけると、北東側にマウンド。


石室が開口している・・・が、H≒40cm。
羨道部は低いものの玄室は高さがありそうなので、腹這いになって匍匐前進で突入~。



右片袖式石室なのか??
・・・右側壁が大きく孕んで今にも崩れてきそう~なので、写真だけ撮って早々に退室(四ツ辻1号墳? Φ=13m・H=3mの円墳。玄室L=3m・W=2m・W≒2.1m、羨道L≒2.2m・W=1.2m)。

東側にも小さなマウンドが幾つかありそうだが、汗に土で泥んこになってしまったため、探訪継続の意欲を喪失。
道路に戻る。
赤色のカラーコーンが1ヶ。
そこは最後に見た古墳の墳丘裾。

山土の中に所々1~2cm厚の白色粘土の塊と花崗岩の細片が混じった古墳断面を見ることが出来る。

この後、剣上塚古墳を経由して近鉄・竜田川駅。
元山上口駅で途中下車して、北に5分弱歩く。
車窓から見えた「椣原(しではら)の勧請綱」、L≒27m・Φ≒25cmの綱が竜田川に張られている。
雄綱に雌綱が巻き付いている。
雄綱の中央から松の枝を取付けた2本の龍足(L=9.3m)がたれさがり、男根、フグリも付けられている。
勧請綱・・・悪霊や厄病の侵入を阻止するために村の出入口の道路上に張られることが多いのだが、ここは水の神・龍神信仰と豊作・子孫繁栄が結びついたのか・・・。

3回に及んだ平群谷の探訪はここまで・・・総歩数=69,474歩
※ 平群谷の古墳・・・5C後半の宮山塚古墳⇒6C後半の烏土塚古墳⇒7C初頭のツボリ山古墳⇒7C中頃の西宮古墳など、古墳時代中期後半から終末期の横穴式石室の変遷が見て取れる。
この中には、円墳・方墳・前方後円墳、片袖式・両袖式、小さな平板をドーム状に積み上げたもの、巨石を用いたもの、切石によるもの、竜山石・二上山石・越木岩石など変化に富んでおり、古墳好きにはたまらない谷であった。
下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
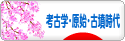
にほんブログ村
滋賀県内の遺跡・史跡などの探訪録は、
コチラ ⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2

東光寺からは、前回と違って尾根に上がらず、谷筋を進む・・・
が、最後は、獣道を頼りに、苦労して急斜面を尾根に上がる。
尾根に上がった所は、石の集在している下側。
尾根を切って北の谷に向かって薄らと獣道が続いているようなので、これに従う。
幅10㎝にも満たないような細道を頼りに、谷を巻き、北の尾根下まで到達。
先人のブログの記事から、この尾根筋にあることを確信して登る。
集在している大石を過ぎて登ると、先日、辿り着いた尾根先の石の集在していた場所に出た。
船石は?

・・・石組みの下を通って船上神社跡に着く。
船石は、どこ・・・??

探索を諦めて、三里城跡に向かうことにした。
下山して登るのも嫌だったので、
山頂に上がり、尾根筋を行けば、先日の峠道に辿り着くはずと考え、
壁石下のガレ場を過ぎたところから山頂を目指す。
ん~。
あそこにも石が・・・、

大きい~、鯨?
ちょっとオーバーか・・・。


尾根に上がると・・・鯱のような船石。
尾根の下側ではなく、上側にあった。
あのブログ記事は~???
尾根の凸部に並んだ3本の花崗岩。

40度を超える急斜面、

今にも山を滑り下りようとするかのように頭を下に向けている。
L=6~9m・W=1~1.5、H=1~1.2m・・・かな?


船石の上部に、祭祀跡らしき石組み遺構。
さらに上ると、磐座のような石の集在。
北側は絶壁、そこに張り出した重箱積み様の岩などなど・・・。
予想どおり頂上部に尾根筋の道。
北に進む。

直ぐに、尾根が堀切のように切られ、
その北側のピークは細長い平坦地(郭か狼煙台の跡?)。
そして、また堀切・・・。
まもなく、足の踏み場がないほどの倒竹。

尾根筋の北進を諦め、右下を見ると輝く水面。
ブッシュを掻き分けて下りると水田が見え、やがて農家の裏に出た。
舗装道に出て、北に向かうと直ぐに白石畑集会所。

平群に向かう峠道の分岐まで来たところで、草刈りをしていたオヤジさんと談笑。
松尾寺まで30分ほどかかるとのこと。
諦めて峠道へ。
 峠、やはり笹竹の密生しているところは先刻の尾根道に続いている模様。
峠、やはり笹竹の密生しているところは先刻の尾根道に続いている模様。三里城跡。
前回、峠道近くの削平地だけの確認で終わっていたので、
ブッシュを掻き分け、
横堀を左に見ながら北端沿いを進む。
2段ほど上がった所で前に進めず退却。
主郭まで到達できなかった。
雛壇状の削平地とその下部の堀跡らしきものの確認はできたが、
ブッシュが酷く縄張全体の確認は不可。

下山後、竜田川駅から石床神社の旧・社地を目指す。
人権交流センターから杜の南を巻くようにして進むと溜池・今池の南端に出る。
そこの道案内に従い越木塚集落の家々の間の細道を上り、
南に下ると集落の外れに石床神社の旧・社地。


鳥居の後ろにH≒6m、W≒10m(9m×18mとも)の岩壁。
中央割れ目の上部から垂れるような細長い岩とそれを下で受ける丸岩からなる磐座(陰石)。
今朝、見てきた矢田丘陵の船石(陽石?)に相応する大きさか・・・。
陰石を御神体として本殿のない古い信仰形態。
集落に戻り、案内表示に従って進み、
越木塚集会所の奥に石床神社。

大正時代に旧・社地から遷座、本殿前の右側に神篭石・・・石棒?が寄り掛かっている。

石床神社の頭上、南側に一段上がったところが消渇神社。

拝殿に並べられた土団子と米団子・・・


神社の石段下、鳥居横の小さな建物の壁に
「祈願のときは土の団子を十二個供えて、満願のときは米の団子を十二個供えて下さい」との説明書が掛けられ、
土団子を作り供えるための材料・道具一式が置かれている。
参道の説明板には、
「室町時代に、旅の僧信海が腰の病を治してもらってから下半身の病気に御利益があるとして村人に信仰されるようになる。
江戸時代には社名から女性の病気や性病に効果があるとして京都祇園からの参拝者もあり、参道に茶店が出るほど賑わったという。・・・。」
と書かれていた。
消渇神社を更に1段上がると崩れつつある築地塀に囲まれて七社神社の小さな祠。

境内を出て北に坂を下ったところに消渇神社の御神水。

「生水では飲まないで下さい」との注意書があるのだが・・・
良く観ると油が浮いて黄変している様子、とても飲む気にはなれない。

越木塚関取道標を過ぎて、十三街道?を四ツ辻古墳群に向かう。
案内表示がなく、ここでは~と思ったところからブッシュの中に駆け上がる。
右奥(西側)に径20mを超えそうなマウンド、南にまわってみたが石室は開口していない。

直ぐ南にも小さなマウンドが・・・
その墳丘の南側に、何とか拳が入るくらいの大きさで開口しているが・・・
石室内は見えず(四ツ辻2号墳? 径=9m)。

諦めて帰りかけると、北東側にマウンド。


石室が開口している・・・が、H≒40cm。
羨道部は低いものの玄室は高さがありそうなので、腹這いになって匍匐前進で突入~。



右片袖式石室なのか??
・・・右側壁が大きく孕んで今にも崩れてきそう~なので、写真だけ撮って早々に退室(四ツ辻1号墳? Φ=13m・H=3mの円墳。玄室L=3m・W=2m・W≒2.1m、羨道L≒2.2m・W=1.2m)。

東側にも小さなマウンドが幾つかありそうだが、汗に土で泥んこになってしまったため、探訪継続の意欲を喪失。
道路に戻る。
赤色のカラーコーンが1ヶ。
そこは最後に見た古墳の墳丘裾。

山土の中に所々1~2cm厚の白色粘土の塊と花崗岩の細片が混じった古墳断面を見ることが出来る。

この後、剣上塚古墳を経由して近鉄・竜田川駅。
元山上口駅で途中下車して、北に5分弱歩く。
車窓から見えた「椣原(しではら)の勧請綱」、L≒27m・Φ≒25cmの綱が竜田川に張られている。
雄綱に雌綱が巻き付いている。
雄綱の中央から松の枝を取付けた2本の龍足(L=9.3m)がたれさがり、男根、フグリも付けられている。
勧請綱・・・悪霊や厄病の侵入を阻止するために村の出入口の道路上に張られることが多いのだが、ここは水の神・龍神信仰と豊作・子孫繁栄が結びついたのか・・・。

3回に及んだ平群谷の探訪はここまで・・・総歩数=69,474歩
※ 平群谷の古墳・・・5C後半の宮山塚古墳⇒6C後半の烏土塚古墳⇒7C初頭のツボリ山古墳⇒7C中頃の西宮古墳など、古墳時代中期後半から終末期の横穴式石室の変遷が見て取れる。
この中には、円墳・方墳・前方後円墳、片袖式・両袖式、小さな平板をドーム状に積み上げたもの、巨石を用いたもの、切石によるもの、竜山石・二上山石・越木岩石など変化に富んでおり、古墳好きにはたまらない谷であった。
下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
にほんブログ村
滋賀県内の遺跡・史跡などの探訪録は、
コチラ ⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2
2014年06月26日
大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その2)

2度目、再度の現地訪問の目的は、船石と三里城など中世城郭遺構の確認なんだが・・・。
まずは、簡単に見つけることができそうな三里城へ、
平群町・・・お薦めの遺跡などの案内はしっかりしているのだけれど、
そうではないところについては、道の案内表示どころか、
遺跡に到達しても表示がまったくないことからその場所に辿り着いたかどうかも判り難い。
・・・ということで、平群駅を出て山麓の三里集落まで来て、さて困った。
山に取付く道は3本。登山路にある叶堂跡が目印なのだが・・・。
南ルートを選択しかけたのだが(こちらが正解)・・・、 北ルートを選択し、矢田丘陵を彷徨うことに~。


由緒ありげな水場(井戸?)と石仏があったので、ここであろうと推察し、竹林をひたすら登る。

やがて、林間の九十九折れ。尾根に出たものの、城郭遺構らしきものは見当たらず。


位置確認のため、尾根の三叉路を西に展望の利くところへ・・・絶壁、磐座のような大石の上に出た。
垂直に割れた岩の上から、平群の谷の眺めは頗る良好。
ここに来る人がいるのか、鳥除けにCDが吊るされている。
三叉路まで戻って、僅かに踏み跡の残った尾根道を東進すると水田に出た。

谷筋に細長く繋がる水田を南に農道を進むと素左男神社。
予想どおり山一つを越え、白石畑の集落まで来てしまっていた。
鳥居に額束はあるものの神額はなく社名は不明。
通りがかった親爺さんに訊ねて分かった。
合わせて、平群に行く道を教示していただく。

集落内をとおり近畿自然歩道と別れ平群へ向かう峠道に入る。


峠付近は、笹竹が密集しトンネル模様。
自動車道ができるまで、おそらく村人は平群へ、
あるいは松尾寺への参詣人も
この道をとおったのか・・・、
そんな歴史を感じることのできる道。
山麓に近づいた頃、切通し?を通過・・・
左側の南の尾根先は削平地??
すぐ下に道を塞ぐかのような大石・・・三里城!


で、切通しまで戻って北側の削平地に入るも藪が酷くて遺構の確認できず・・・。
防御を考えてのことか、大石の下側の道は急登を幾度か曲がって登るような構造になっている。
叶堂跡を過ぎ山麓の集落に着く。
登山路入口に軽トラが駐車して道を塞いでいる。
他所の家の庭先のよう・・・これでは道を見つけることができないハズ。
道案内の標識が欲しい~。


船山神社に立寄り船石に辿り着けるよう祈念した後、東光寺を目指す。
端正な佇まいの東光寺の前を東進し、ため池の傍を抜け尾根に取付く。
この間、クマザサで隠れて道が不詳。
東光寺前にも道の案内表示が欲しいところ・・・。

ところどころ道が切れるものの尾根筋を辿れば、やがて船上神社の旧社地。
東西に2段の削平地。
東の削平地に祠の基壇となる石組み遺構が残存している。

さらに東に尾根を上ると左の谷側に石組み。 目の前は、垂直の岩壁。


事前に確認したブログの地図には
北側の尾根、神社跡から下のほうに見えるとのことだったので、
岩のガレ場をまわって
北の尾根先を進むと数個の大きな石が集在しているところに出た。
これが、船石??
尾根を巻くように更に北側に進んだが、絶壁で足場がない。
仕方なくガレ場まで戻り、垂直の岩壁をサイドの枯れ木の根を足掛かりに登ると・・・その裏側も垂直。

岩壁は幅1~2mほどの大きな立石だった。
船石の影すら見つけられず下山。
このあと、下垣内城跡と西宮城跡のある中央公園に進むが、
公園の造成にあたって、現地に建っても遺構の概観すら分からないほど地形が改変されていた。
遺構は地下に残存しているとのことなのだが・・・
埋め戻しても、遺跡・遺構の概要くらいは、それなりに分かる姿で保存したいもの・・・。
西宮古墳に立ち寄った後、近鉄・竜田川駅。

次の探訪を含め、3回の昼食は「道の駅 くまがしステーション」でお世話になった。
地元野菜を使った身体に優しそうな・・・、ハードな山行には少し軽めの食事。

下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
にほんブログ村



