2014年05月10日
山陰の雄『尼子氏』の山城を訪ねて・・・出雲紀行(その2-②)
翌日、茶臼山城(神名樋野 ※)に登ったほかは、古代史関係の遺跡めぐり。
※ 探訪録は、以下の「あきのブログ http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2」をご覧ください。
翌々日、広瀬町の歴史資料館(この日、K館長さんは、お休みで会えず。)に立寄ったあと尼子氏関係の遺跡を巡った。

まずは、対岸の勝山城(安来市。標高250m。尼子十砦の一つ)へ。
広瀬の街並みの北外れ、飯梨川(冨田川)の支流・洞貫川に走る県道45号、交通安全祈願の母子像のところを山側の石原の集落に入る。川沿いの道を進むと三叉路があり右側(墓地の反対側)に「勝山城」の小さな案内板。未舗装の細い道を上ると農家の作業小屋の前に出る。左側の細い林道を道なりに進むと木橋のところで道がなくなる。そこが登山口。5台ほどP可能。
ただし、作業小屋からの林道はぬかるみが酷いので、雨後の場合、車幅の広い普通車は進入しないほうが賢明。深さ30cm以上の轍が10m以上続いている。(四駆の軽トラなら通行可かも・・・)

ぬかるみの手前にクルマを置いて「登山」開始。 木橋を渡り、右岸、左岸に移動しながら沢沿いの流石・流木の多い径を進む。

途中、右岸に2ヶ所の石垣を観たが、いつ頃のモノなのか? (下山後、資料館で訊ねたが、不詳とのこと)

沢を詰めたところから尾根に向かって壁を登る。 標高500mほどの尾根に出たところで大内氏が陣を置いたという京羅木山城へ続く径とは反対方向の南へ下る。 途中にもピークがあるが城跡はその先の尾根の突端のピーク。
せっかく登ってきたのに~と思いつつ下って、少し上がると、尾根を断ち切る3本の堀切と切岸状の壁。 この切岸を東に迂回して畝状竪堀群の北端から土塁で囲まれた虎口である枡形虎口(「人桝」)に入る。削平地を1段、2段上がって南の主郭部へ。そこから東に下りながら屈曲する5段の削平地。南側と4・5段の間に土塁遺構。馬出状の半円形をした5段の北側に土塁と虎口。眼下に冨田城と広瀬の街並み。

城跡は、「く」の字状。飯梨川・冨田城に向かう東側の全面と南東側に隙間なく連続した40数本の畝状竪堀群。これほど多くの畝状竪堀をもつ城跡は不知。 その畝状竪堀群の上端を南東部の虎口から北の虎口まで歩く。 主郭部の「く」の字状になった両端とその間に確認した2ヶ所の「折れ」により攻め手は難儀。 急坂を登り辿りついたところで横矢が掛かる縄張りになっている。

下山後、冨田城(安来市。標高189m。尼子氏本城)へ。

厳倉寺の上方に、今年、新たにP(10台以上駐車可)が整備されていた。

Pから城跡に進むと軍用大井戸の下で路は大きく左に回るのだが、不自然なことに、この一画と曲がった先にある溜池の山側(山中御殿の拡張郭)の2ヶ所、大きく剥ぎ取られたかのように石垣がなくなっている。
後者は虎口の雰囲気を少し残しているものの後世のような開かれた大手口の姿になっている。
いっぽう、前者、本来の大手口であった御子守口は、虎口があったのか全く窺い知ることができないほど形状が変わってしまっている・・・破城??
ただ、少し気になるのは剥ぎ取られた側に残る石積。 算木積に積まれた隅石垣と同じくらいの大きな石・・・両者の間の石に比べて大きいこと。

まずは、軍用大井戸から山中御殿(御殿平)。
上下2段からなる冨田城の心臓部とも謂われる広い建物跡。
ここに冨田城の絵図や歴史などの案内板が設置されているのを確認後、相坂コースから山上の三の丸を目指す。
石畳の七曲りを上ったところに山吹井戸。
さらに進んだところで珍客。
記念撮影に1枚。
下山後に再会したので話を訊くと、大坂からリヤカーを曳いて日本一周の途中とのこと。
また、登城の際に着用していた甲冑は「紙製なので、とても軽い~。」とのこと(^J^)

郭(「西の袖平」)とその上に築かれた西北から南東に細長い三の丸。 径が整備されているので今朝登った勝山城に比べて早く楽に上れた。 西の袖平は西方向に先萎み状に伸びており、その伸びた平坦部の両側は石垣でかためられている模様。 その先端は切通し状(虎口?)になっていることから、元々登城路の一つであったかも・・・??
三の丸から一段上がって二の丸、三の丸との間に堀切があったものの埋められたのか、現状は一体のモノとして繋がっている。 この両丸は(場所によれば2段あるいは3段の階段状に)石垣が施されている。 隅石は算木積ではなく重箱積の様子だが・・・ちょっと微妙。 中腹の山中御殿などの石垣と明らかに時代が異なる。 二の丸・三の丸、それぞれに途中で2回、進行方向を変えないと入ることの出来ない二重虎口が一ヶ所ずつある。 進入するには、横矢に晒される巧妙な縄張り。
二の丸の虎口の石垣最下段に開いていた大きな穴、これは?
二の丸の南東、大きな堀切(10mほどの深さ)を挟んで本丸、二の丸とほぼ同高。
中央部に建つ山中鹿之助の供養塔付近からは好展望。
最南部の一段高くなったところに冨田八幡宮の奥宮・勝日高守神社。その東南部に浅い鞍部を隔てて石垣、破城された櫓台?
この本丸には石垣の普請はないようす・・・先刻の二の丸・三の丸が本来の主郭だった・・・かな??
とは言っても、先の大戦の際、高射砲陣地が設置されたとのことであり、往時の姿はわからない。
縄張図を参考に主郭直下、櫓台との間から十二所神社をとおり新宮党館方面に下りようとしたが、ブッシュと急斜面のため断念。Pまで下山してクルマで移動することにした。

下りは軍用径コースを選択.御殿平に降りたところは左右を石垣に挟まれている。左手の石垣は一部2段築造。 この隘路を抜けたところの右手に、山腹では唯一残存している虎口らしい虎口の菅谷口、大きな石を使った算木積がある。 その内側に、今も水を溜めている雑用井戸と櫓台。
この辺りは山中御殿の拡張域? この先、Pの北側尾根に普請された花ノ壇、奥書院、太鼓壇、千畳平まで下りて、尼子神社の脇から塩冶興久の墓地に向かう。

山中御殿から一段下がって西に伸びた尾根を堀切で遮断されて花ノ壇の郭がある。この堀切は通路としても使われていたとのことで、西側に版築工法を残す断面が分かるように展示されている。
反対の東側は竪堀となって落ち込んでいるが、その手前右(南)側の郭、訪ね来る人は殆どないのか草生しているが、良く観ると見事な石垣・・・。
花ノ壇の南端に発掘調査で発見された柱穴を基に2棟の建物、主屋と侍所が復元されている。

花の壇から北に2段ほど下がると奥書院。
西に向かって合掌する山中鹿介幸盛の立像がある。
その西に太鼓壇。 その北端の櫓台?上に尼子氏之碑が建っている。
碑文には、陰陽11州を治のめ殷盛を極めた尼子氏の紹介している。
さらに緩やかな坂を下りると千畳平。ここに尼子氏三代城主と尼子十勇士の霊を祀る尼子神社がある。
ここから、太鼓壇から北に続く出郭の下を進んで山麓の塩冶興久の墓に下りる。

再び赤門から登城し、御子守口の巌倉寺にある豊臣三中老のひとりであり、孫である松江城主・堀尾忠晴の後見であった堀尾吉晴の墓と山中鹿介幸盛の供養塔に参る。
この巌倉寺の石垣は素晴らしく、冨田城の最下段近くに位置する郭であることが容易に解かる。

巌倉寺登り口の西側にある御子守神社の出郭を確認した後、資料館にお礼に伺うと発掘調査現場の確認の有無を訊ねられた。
・・・、勿論、まったく気付いておらず観ていない旨を伝えると、案内して下さった。
資料館の真上、千畳平の西面に石垣が現れていた。この日は土曜日だったため、調査は休みで現場はブルーシートで覆われていたものの、ところどころ石垣が確認できた。
大きな石、算木積み等々、堀尾氏の入城後において普請されたものと考えているとのこと。
今回は天気に恵まれ、桜をはじめ花盛りのいろんな草花が城内アチコチに咲いているのを観ることができた。花々をカメラにおさめている人の姿もあり、珍しいという白色のイカリソウを教えていただいた。
このあと新宮谷にまわり新宮党館跡の太夫神社、毛利元秋の墓に詣でて、この日の探訪は終了。
出雲の最終日、宍道湖の西方、大船山(標高327m)・鍋池山(標高358m)と仏経山(標高366m)に登ったあと高瀬山城(尼子10旗の一(第6旗)。標高316m)を登る。
県道183号にあった案内表示に従って南の脇道に入ったものの高瀬不動橋の手前でロープが張られており、「車両進入禁止」の表示。 仕方なく道路脇にクルマを停めて周辺を窺うと登山口の表示版があり、高瀬山城について概説されていた。
尼子氏の重臣であった城主米原氏(佐々木六角氏の支流?)は、近江国米原郷の発祥で出雲国守護代となった尼子氏の被官として下向したもの~ここにも近江の国人が・・・

良く踏み込まれ整備された径は細いけれど歩きやすい。登山路を発ち直ぐに尾根に三の丸に向かう尾根に出る。ここから山頂までの径のほとんどは複数の人が横になって歩けないほどの細い痩せ尾根、それも適度に屈曲している。 頭上から射かけられるなか、列になって進むしかない攻め難い径。 城域は大きく3つに分かれており、二の丸から西北に突き出たところにある三の丸(鉄砲立)。左右に神庭谷と宇屋谷を眼下に見下ろすことが出来る場所である。
七曲の坂という屈曲した急坂を上がった所が駄知馬。 ここは、尾根続きの中にあって比較的広い100㎡ほどの削平地で二の丸(小高瀬)と甲の丸(大高瀬・山頂)の分岐点。 武器や兵糧などを馬により運び上げ貯蔵していた場所とか~。 狭い尾根道を馬が上がってきたということに大いに感心した・・・。
まずは、西側の二の丸を目指す。 甲の丸のある山頂より50mほど低く、高瀬防御の最重要拠点とか・・・三の丸を上がって来る敵は、その尾根筋に取付いた時から丸見えの様子。しかし、毛利軍はここまで攻め上り焼き払ったとか・・・。

西進して直ぐに笹竹とブッシュで行く手を塞がれる。 踏み跡の確認がし難く、イバラの群生に悩まされながら岩が散在するところまできたものの先に進むのを諦め引き返す。


駄知馬まで戻って、東側の山頂を目指す。
所どころ崩れかかった石垣を確認しつつ階段状に連なる郭を登って行くと梯子が現れた。
横堀・竪堀?、複雑~?? あと数段上がると頂上。
甲の丸(大高瀬・山頂)は岩山の様相。360度の展望。
その先、神庭谷・光明寺へ続く径は、細い尾根上に段々と郭が連なる様子。
山頂の案内表示には、
「高瀬山の名の由来は太古、宇夜都弁命がこの山に遊ばれたところ、山の頂に清水が湧いていたので「高清水」と詔り給うたので山の名にした。しかし、その後いつか「高瀬」と呼ぶようになったという。・・・」と述べられていた。

不思議なことにこの山城、尾根上にありながら堀切の確認ができなかった、見落とした??
山頂と直ぐ下の郭に岩場を刳り抜いた穴があったが、何??・・・埋蔵金伝説の採掘坑? (笑)

下山後、高瀬山城跡を訪ねたあと出雲探訪の〆として、曽枳能夜神社に参拝のあと、真新しい松江自動車道を経由して帰宅。
最後の日の昼食&夕食は・・・こんなのでした。 (^J^)


総走行キロ:1144.9km。滞在4日間の総歩数69150歩
※文中に出てくる社寺・古墳や記載を省略した茶臼山城などの探訪録は、
以下の「あきのブログ」をご覧ください。
http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2
下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
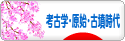
にほんブログ村
※ 探訪録は、以下の「あきのブログ http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2」をご覧ください。
翌々日、広瀬町の歴史資料館(この日、K館長さんは、お休みで会えず。)に立寄ったあと尼子氏関係の遺跡を巡った。

まずは、対岸の勝山城(安来市。標高250m。尼子十砦の一つ)へ。
広瀬の街並みの北外れ、飯梨川(冨田川)の支流・洞貫川に走る県道45号、交通安全祈願の母子像のところを山側の石原の集落に入る。川沿いの道を進むと三叉路があり右側(墓地の反対側)に「勝山城」の小さな案内板。未舗装の細い道を上ると農家の作業小屋の前に出る。左側の細い林道を道なりに進むと木橋のところで道がなくなる。そこが登山口。5台ほどP可能。
ただし、作業小屋からの林道はぬかるみが酷いので、雨後の場合、車幅の広い普通車は進入しないほうが賢明。深さ30cm以上の轍が10m以上続いている。(四駆の軽トラなら通行可かも・・・)

ぬかるみの手前にクルマを置いて「登山」開始。 木橋を渡り、右岸、左岸に移動しながら沢沿いの流石・流木の多い径を進む。

途中、右岸に2ヶ所の石垣を観たが、いつ頃のモノなのか? (下山後、資料館で訊ねたが、不詳とのこと)

沢を詰めたところから尾根に向かって壁を登る。 標高500mほどの尾根に出たところで大内氏が陣を置いたという京羅木山城へ続く径とは反対方向の南へ下る。 途中にもピークがあるが城跡はその先の尾根の突端のピーク。
せっかく登ってきたのに~と思いつつ下って、少し上がると、尾根を断ち切る3本の堀切と切岸状の壁。 この切岸を東に迂回して畝状竪堀群の北端から土塁で囲まれた虎口である枡形虎口(「人桝」)に入る。削平地を1段、2段上がって南の主郭部へ。そこから東に下りながら屈曲する5段の削平地。南側と4・5段の間に土塁遺構。馬出状の半円形をした5段の北側に土塁と虎口。眼下に冨田城と広瀬の街並み。

城跡は、「く」の字状。飯梨川・冨田城に向かう東側の全面と南東側に隙間なく連続した40数本の畝状竪堀群。これほど多くの畝状竪堀をもつ城跡は不知。 その畝状竪堀群の上端を南東部の虎口から北の虎口まで歩く。 主郭部の「く」の字状になった両端とその間に確認した2ヶ所の「折れ」により攻め手は難儀。 急坂を登り辿りついたところで横矢が掛かる縄張りになっている。

下山後、冨田城(安来市。標高189m。尼子氏本城)へ。

厳倉寺の上方に、今年、新たにP(10台以上駐車可)が整備されていた。

Pから城跡に進むと軍用大井戸の下で路は大きく左に回るのだが、不自然なことに、この一画と曲がった先にある溜池の山側(山中御殿の拡張郭)の2ヶ所、大きく剥ぎ取られたかのように石垣がなくなっている。
後者は虎口の雰囲気を少し残しているものの後世のような開かれた大手口の姿になっている。
いっぽう、前者、本来の大手口であった御子守口は、虎口があったのか全く窺い知ることができないほど形状が変わってしまっている・・・破城??
ただ、少し気になるのは剥ぎ取られた側に残る石積。 算木積に積まれた隅石垣と同じくらいの大きな石・・・両者の間の石に比べて大きいこと。

まずは、軍用大井戸から山中御殿(御殿平)。
上下2段からなる冨田城の心臓部とも謂われる広い建物跡。
ここに冨田城の絵図や歴史などの案内板が設置されているのを確認後、相坂コースから山上の三の丸を目指す。
石畳の七曲りを上ったところに山吹井戸。
さらに進んだところで珍客。
記念撮影に1枚。
下山後に再会したので話を訊くと、大坂からリヤカーを曳いて日本一周の途中とのこと。
また、登城の際に着用していた甲冑は「紙製なので、とても軽い~。」とのこと(^J^)

郭(「西の袖平」)とその上に築かれた西北から南東に細長い三の丸。 径が整備されているので今朝登った勝山城に比べて早く楽に上れた。 西の袖平は西方向に先萎み状に伸びており、その伸びた平坦部の両側は石垣でかためられている模様。 その先端は切通し状(虎口?)になっていることから、元々登城路の一つであったかも・・・??
三の丸から一段上がって二の丸、三の丸との間に堀切があったものの埋められたのか、現状は一体のモノとして繋がっている。 この両丸は(場所によれば2段あるいは3段の階段状に)石垣が施されている。 隅石は算木積ではなく重箱積の様子だが・・・ちょっと微妙。 中腹の山中御殿などの石垣と明らかに時代が異なる。 二の丸・三の丸、それぞれに途中で2回、進行方向を変えないと入ることの出来ない二重虎口が一ヶ所ずつある。 進入するには、横矢に晒される巧妙な縄張り。
二の丸の虎口の石垣最下段に開いていた大きな穴、これは?
二の丸の南東、大きな堀切(10mほどの深さ)を挟んで本丸、二の丸とほぼ同高。
中央部に建つ山中鹿之助の供養塔付近からは好展望。
最南部の一段高くなったところに冨田八幡宮の奥宮・勝日高守神社。その東南部に浅い鞍部を隔てて石垣、破城された櫓台?
この本丸には石垣の普請はないようす・・・先刻の二の丸・三の丸が本来の主郭だった・・・かな??
とは言っても、先の大戦の際、高射砲陣地が設置されたとのことであり、往時の姿はわからない。
縄張図を参考に主郭直下、櫓台との間から十二所神社をとおり新宮党館方面に下りようとしたが、ブッシュと急斜面のため断念。Pまで下山してクルマで移動することにした。

下りは軍用径コースを選択.御殿平に降りたところは左右を石垣に挟まれている。左手の石垣は一部2段築造。 この隘路を抜けたところの右手に、山腹では唯一残存している虎口らしい虎口の菅谷口、大きな石を使った算木積がある。 その内側に、今も水を溜めている雑用井戸と櫓台。
この辺りは山中御殿の拡張域? この先、Pの北側尾根に普請された花ノ壇、奥書院、太鼓壇、千畳平まで下りて、尼子神社の脇から塩冶興久の墓地に向かう。

山中御殿から一段下がって西に伸びた尾根を堀切で遮断されて花ノ壇の郭がある。この堀切は通路としても使われていたとのことで、西側に版築工法を残す断面が分かるように展示されている。
反対の東側は竪堀となって落ち込んでいるが、その手前右(南)側の郭、訪ね来る人は殆どないのか草生しているが、良く観ると見事な石垣・・・。
花ノ壇の南端に発掘調査で発見された柱穴を基に2棟の建物、主屋と侍所が復元されている。

花の壇から北に2段ほど下がると奥書院。
西に向かって合掌する山中鹿介幸盛の立像がある。
その西に太鼓壇。 その北端の櫓台?上に尼子氏之碑が建っている。
碑文には、陰陽11州を治のめ殷盛を極めた尼子氏の紹介している。
さらに緩やかな坂を下りると千畳平。ここに尼子氏三代城主と尼子十勇士の霊を祀る尼子神社がある。
ここから、太鼓壇から北に続く出郭の下を進んで山麓の塩冶興久の墓に下りる。

再び赤門から登城し、御子守口の巌倉寺にある豊臣三中老のひとりであり、孫である松江城主・堀尾忠晴の後見であった堀尾吉晴の墓と山中鹿介幸盛の供養塔に参る。
この巌倉寺の石垣は素晴らしく、冨田城の最下段近くに位置する郭であることが容易に解かる。

巌倉寺登り口の西側にある御子守神社の出郭を確認した後、資料館にお礼に伺うと発掘調査現場の確認の有無を訊ねられた。
・・・、勿論、まったく気付いておらず観ていない旨を伝えると、案内して下さった。
資料館の真上、千畳平の西面に石垣が現れていた。この日は土曜日だったため、調査は休みで現場はブルーシートで覆われていたものの、ところどころ石垣が確認できた。
大きな石、算木積み等々、堀尾氏の入城後において普請されたものと考えているとのこと。
今回は天気に恵まれ、桜をはじめ花盛りのいろんな草花が城内アチコチに咲いているのを観ることができた。花々をカメラにおさめている人の姿もあり、珍しいという白色のイカリソウを教えていただいた。
このあと新宮谷にまわり新宮党館跡の太夫神社、毛利元秋の墓に詣でて、この日の探訪は終了。
出雲の最終日、宍道湖の西方、大船山(標高327m)・鍋池山(標高358m)と仏経山(標高366m)に登ったあと高瀬山城(尼子10旗の一(第6旗)。標高316m)を登る。
県道183号にあった案内表示に従って南の脇道に入ったものの高瀬不動橋の手前でロープが張られており、「車両進入禁止」の表示。 仕方なく道路脇にクルマを停めて周辺を窺うと登山口の表示版があり、高瀬山城について概説されていた。
尼子氏の重臣であった城主米原氏(佐々木六角氏の支流?)は、近江国米原郷の発祥で出雲国守護代となった尼子氏の被官として下向したもの~ここにも近江の国人が・・・

良く踏み込まれ整備された径は細いけれど歩きやすい。登山路を発ち直ぐに尾根に三の丸に向かう尾根に出る。ここから山頂までの径のほとんどは複数の人が横になって歩けないほどの細い痩せ尾根、それも適度に屈曲している。 頭上から射かけられるなか、列になって進むしかない攻め難い径。 城域は大きく3つに分かれており、二の丸から西北に突き出たところにある三の丸(鉄砲立)。左右に神庭谷と宇屋谷を眼下に見下ろすことが出来る場所である。
七曲の坂という屈曲した急坂を上がった所が駄知馬。 ここは、尾根続きの中にあって比較的広い100㎡ほどの削平地で二の丸(小高瀬)と甲の丸(大高瀬・山頂)の分岐点。 武器や兵糧などを馬により運び上げ貯蔵していた場所とか~。 狭い尾根道を馬が上がってきたということに大いに感心した・・・。
まずは、西側の二の丸を目指す。 甲の丸のある山頂より50mほど低く、高瀬防御の最重要拠点とか・・・三の丸を上がって来る敵は、その尾根筋に取付いた時から丸見えの様子。しかし、毛利軍はここまで攻め上り焼き払ったとか・・・。

西進して直ぐに笹竹とブッシュで行く手を塞がれる。 踏み跡の確認がし難く、イバラの群生に悩まされながら岩が散在するところまできたものの先に進むのを諦め引き返す。


駄知馬まで戻って、東側の山頂を目指す。
所どころ崩れかかった石垣を確認しつつ階段状に連なる郭を登って行くと梯子が現れた。
横堀・竪堀?、複雑~?? あと数段上がると頂上。
甲の丸(大高瀬・山頂)は岩山の様相。360度の展望。
その先、神庭谷・光明寺へ続く径は、細い尾根上に段々と郭が連なる様子。
山頂の案内表示には、
「高瀬山の名の由来は太古、宇夜都弁命がこの山に遊ばれたところ、山の頂に清水が湧いていたので「高清水」と詔り給うたので山の名にした。しかし、その後いつか「高瀬」と呼ぶようになったという。・・・」と述べられていた。

不思議なことにこの山城、尾根上にありながら堀切の確認ができなかった、見落とした??
山頂と直ぐ下の郭に岩場を刳り抜いた穴があったが、何??・・・埋蔵金伝説の採掘坑? (笑)

下山後、高瀬山城跡を訪ねたあと出雲探訪の〆として、曽枳能夜神社に参拝のあと、真新しい松江自動車道を経由して帰宅。
最後の日の昼食&夕食は・・・こんなのでした。 (^J^)


総走行キロ:1144.9km。滞在4日間の総歩数69150歩
※文中に出てくる社寺・古墳や記載を省略した茶臼山城などの探訪録は、
以下の「あきのブログ」をご覧ください。
http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2
下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
にほんブログ村





