2014年03月01日
河内の国・野中寺を訪ねる
好天気に恵まれた日、河内、和泉そして紀州の古代史跡などを訪ねてきた。
まずは、羽曳野市にある名刹・野中寺(中之太子。羽曳野市)へ。


ここにあるのが、弥勒菩薩半跏思惟像。
仏像に関心のある人にとっては、天使あるいは妖精的存在?
聖徳太子の命を受けた蘇我馬子が開基したと伝えられている。境内に、飛鳥期に多く用いられた四天王寺の配置方法より新しく、法隆寺より古い形態で、白鳳期の官寺に用いられていた川原寺の変形した伽藍配置を示す金堂跡(山門を入って右・東側)と塔跡(左・西側)の礎石を観ることが出来る。

案内表示には以下のような説明あり。
「当寺の創立は蘇我大臣といい、また聖徳太子建立46院の一とも称するところから、叡福寺の「上の太子」、将軍寺の「下の太子」に対し「中の太子」と俗称せられている。 所在地の旧郷名が野中郷であってその地名による俗名を野中寺といい『日本霊異記』には野中堂と記している。また正倉院文書によれば当郷は百済系渡来系氏族船氏のちの船連の本貫であったことから、その氏寺であったことが察せられる。 その創立年代は境内出土屋瓦から飛鳥時代にあることが考えられる。 境域には良く旧伽藍跡の土壇および礎石配列を止めるが、対抗する東の金堂と西の塔婆とを中心とするもので、その伽藍配置は野中寺式とでも称すべき特色あるものである。なかんずく塔跡の刹柱礎石は刹柱の四柱座の周囲三方に添柱のそれをも彫り加えていて当市古市の西琳寺、法隆寺創建伽藍、橿原市橘寺等のそれに類例があり、ことにその舎利納置施設として柱穴側面に横穴を穿っているのが注目される点である。 なお創建当時の軒丸瓦には弁上に忍冬文を配した特色あるものも含まれている。 当寺の現堂宇は享保年間以後、律僧恵猛により狭山藩主北條氏を檀越として再興されたもので、その僧堂は簡素な建物ではあるが、めずらしい遺構である。 なお僧恵猛は現寝屋川市太秦の秦氏の出身であって『律苑僧宝伝』、『日本高僧伝』等の伝記に記載されている高僧である。」
本堂の左側にヒチンジョ池西古墳の横口式石槨が展示されており、
「・・・二上山で採れる凝灰岩を精巧に加工して、10個の石材を組み合わせて作られています。内法は、長さ約2.4m・幅約1.1m・高さ約1mを測ります。この中から銅製の釘、漆の膜や木の破片が見つかっていますので、漆塗木棺が安置されていたものと考えられます。 このように棺を納めるための石の部屋を、一般には横口式石槨あるいは石棺式石室といい、河内や大和の飛鳥に分布する7世紀代の古墳にしばしば見られるものです。 ヒチンジョ池西古墳も、この部屋の形態から7世紀終わりから8世紀初め頃(今から約1,300年前)のものと思われます。 この古墳は、ここから南西に約1km離れた場所にありました。 横口式石槨は、1946(昭和21)年に発見され、野中寺境内に移築されました。 その後恒久的な保護を目指して、1994~1996(平成6~8)年に野中寺・大阪府・羽曳野市によって保存修理が行われました。」との説明あり。
本堂奥、西北側の墓地にお染・久松の墓所がある。
お染の父親の菩提寺が野中寺であった関係だ。
境内には、豪商であった父親の里である八尾の地から移植したという樹齢四百数十年の山茶花が植わっており、初冬に数千と鈴なりに白い花を咲かせるそうだ。
年月を経たこの山茶花、いつの間にか幹と幹がくっつき連理の枝となった。 まさに二人の情念のなせる技なのか???
「縁結び」の山茶花と呼ばれているらしいが、死んで一緒になっても・・・。
~ 野崎参りは 屋形舟でまいろ お染久松 せつない恋に 残る紅梅 久作屋敷 今もふらすか 春の雨 ~ ・・・・
古色蒼然とした墓碑の表面には「宗味信武士 妙法信女」、裏面には「享保七年十月七日 俗名 お染 久松 大坂東掘 天王寺屋権右衛門」と刻まれている。
野中寺の西隣、小さな丘の上に野々上八幡神社がある。 境内にある昭和63年に建立された由来記によると、
「当神社は奈良朝から平安初期(約1207年前)にかけて野中寺とは宮寺形式となっていた。 永和元年(約614年前)南北朝の争乱で社殿附近が野中寺城としての戦場となったためお寺と共に焼失する。 その後江戸寛文年間(約328年前)に至って覺英律師や恵猛律師による野中寺復興の折お寺の鎮守、八幡宮として再建される。 祭神は「八幡大菩薩」さまであった。 明治初年(約120年前)の神佛分離令により野中寺と別れ独立して「村社」となり、その後、北宮大津神社に合祀され昭和23年当山に復帰される。・・・」
とのこと。
なお、燈籠は宝暦5年、敷石は安政6年、狛犬は文化8年のものという。
この後、先月訪ねた黒姫山古墳の近くをとおり、土塔に向かった。
まずは、羽曳野市にある名刹・野中寺(中之太子。羽曳野市)へ。


ここにあるのが、弥勒菩薩半跏思惟像。
仏像に関心のある人にとっては、天使あるいは妖精的存在?
聖徳太子の命を受けた蘇我馬子が開基したと伝えられている。境内に、飛鳥期に多く用いられた四天王寺の配置方法より新しく、法隆寺より古い形態で、白鳳期の官寺に用いられていた川原寺の変形した伽藍配置を示す金堂跡(山門を入って右・東側)と塔跡(左・西側)の礎石を観ることが出来る。


案内表示には以下のような説明あり。
「当寺の創立は蘇我大臣といい、また聖徳太子建立46院の一とも称するところから、叡福寺の「上の太子」、将軍寺の「下の太子」に対し「中の太子」と俗称せられている。 所在地の旧郷名が野中郷であってその地名による俗名を野中寺といい『日本霊異記』には野中堂と記している。また正倉院文書によれば当郷は百済系渡来系氏族船氏のちの船連の本貫であったことから、その氏寺であったことが察せられる。 その創立年代は境内出土屋瓦から飛鳥時代にあることが考えられる。 境域には良く旧伽藍跡の土壇および礎石配列を止めるが、対抗する東の金堂と西の塔婆とを中心とするもので、その伽藍配置は野中寺式とでも称すべき特色あるものである。なかんずく塔跡の刹柱礎石は刹柱の四柱座の周囲三方に添柱のそれをも彫り加えていて当市古市の西琳寺、法隆寺創建伽藍、橿原市橘寺等のそれに類例があり、ことにその舎利納置施設として柱穴側面に横穴を穿っているのが注目される点である。 なお創建当時の軒丸瓦には弁上に忍冬文を配した特色あるものも含まれている。 当寺の現堂宇は享保年間以後、律僧恵猛により狭山藩主北條氏を檀越として再興されたもので、その僧堂は簡素な建物ではあるが、めずらしい遺構である。 なお僧恵猛は現寝屋川市太秦の秦氏の出身であって『律苑僧宝伝』、『日本高僧伝』等の伝記に記載されている高僧である。」
本堂の左側にヒチンジョ池西古墳の横口式石槨が展示されており、
「・・・二上山で採れる凝灰岩を精巧に加工して、10個の石材を組み合わせて作られています。内法は、長さ約2.4m・幅約1.1m・高さ約1mを測ります。この中から銅製の釘、漆の膜や木の破片が見つかっていますので、漆塗木棺が安置されていたものと考えられます。 このように棺を納めるための石の部屋を、一般には横口式石槨あるいは石棺式石室といい、河内や大和の飛鳥に分布する7世紀代の古墳にしばしば見られるものです。 ヒチンジョ池西古墳も、この部屋の形態から7世紀終わりから8世紀初め頃(今から約1,300年前)のものと思われます。 この古墳は、ここから南西に約1km離れた場所にありました。 横口式石槨は、1946(昭和21)年に発見され、野中寺境内に移築されました。 その後恒久的な保護を目指して、1994~1996(平成6~8)年に野中寺・大阪府・羽曳野市によって保存修理が行われました。」との説明あり。

本堂奥、西北側の墓地にお染・久松の墓所がある。
お染の父親の菩提寺が野中寺であった関係だ。
境内には、豪商であった父親の里である八尾の地から移植したという樹齢四百数十年の山茶花が植わっており、初冬に数千と鈴なりに白い花を咲かせるそうだ。
年月を経たこの山茶花、いつの間にか幹と幹がくっつき連理の枝となった。 まさに二人の情念のなせる技なのか???
「縁結び」の山茶花と呼ばれているらしいが、死んで一緒になっても・・・。
~ 野崎参りは 屋形舟でまいろ お染久松 せつない恋に 残る紅梅 久作屋敷 今もふらすか 春の雨 ~ ・・・・
古色蒼然とした墓碑の表面には「宗味信武士 妙法信女」、裏面には「享保七年十月七日 俗名 お染 久松 大坂東掘 天王寺屋権右衛門」と刻まれている。

野中寺の西隣、小さな丘の上に野々上八幡神社がある。 境内にある昭和63年に建立された由来記によると、
「当神社は奈良朝から平安初期(約1207年前)にかけて野中寺とは宮寺形式となっていた。 永和元年(約614年前)南北朝の争乱で社殿附近が野中寺城としての戦場となったためお寺と共に焼失する。 その後江戸寛文年間(約328年前)に至って覺英律師や恵猛律師による野中寺復興の折お寺の鎮守、八幡宮として再建される。 祭神は「八幡大菩薩」さまであった。 明治初年(約120年前)の神佛分離令により野中寺と別れ独立して「村社」となり、その後、北宮大津神社に合祀され昭和23年当山に復帰される。・・・」
とのこと。
なお、燈籠は宝暦5年、敷石は安政6年、狛犬は文化8年のものという。

この後、先月訪ねた黒姫山古墳の近くをとおり、土塔に向かった。
下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
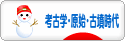
にほんブログ村
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
にほんブログ村
大和の国を歩く ~ 本薬師寺
飛鳥へ ~ 都塚古墳を訪ねる
奈良・春日山原始林を歩く
大和の国を訪ねる(2)・・・多神社・多遺跡、新沢千塚古墳群、室大墓へ
大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その3)
大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その2)
飛鳥へ ~ 都塚古墳を訪ねる
奈良・春日山原始林を歩く
大和の国を訪ねる(2)・・・多神社・多遺跡、新沢千塚古墳群、室大墓へ
大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その3)
大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その2)










