2014年01月09日
近江の国・穴太の里を歩く
正月3ヶ日を過ぎてやっと新年の行動開始。
この間、家籠りの日々が続いたためか、体がだるく頭痛。
毎食後、鎮痛剤の世話になっている。

久し振りに冷え込んだ比叡山麓、京阪石坂線の穴太駅周辺を散策。

穴太駒込古墳群
穴太駅を降りて西側、県道伊香立浜大津線を渡る。ここは県道が建設された昭和43年度に、また長さ60mほどのコンクリート壁の場所は、歩道拡幅工事に先立って平成15年度に発掘調査が行われたところ。
今は見る影もないが、昭和43年度に調査した石室が近くの「びわこ老人の家」の敷地内に移築されているとのこと(確認せず!)

県道を横断して比叡山に向かって登ると直ぐに右側の木々の間に由緒ありそうな石の祠、これって何?



仲哀天皇産湯の水
「湖の美が丘」住宅団地・壺坂城跡方面に向け引続き緩やかな舗装道路(※)を登ると、右の林間に井泉に向かう分岐道。
以前はフェンスに囲まれた禁足地で入れなかったのだが、今回、進入口のフェンスだけが無くなっていた。
四ツ谷川を右下に見ながら進むと左方向、一段高くなったところに「高穴穂神社 お旅所」の石柱。裏側には「穴穂神」と彫り込まれている。
その後ろに、まるで古墳の石室のような石囲いの水場。
これが「仲哀天皇の産湯に使った井泉」?
(※)この道、以前、平子谷林道が崩落して登れなかった時に辿った路。
送電線鉄塔のピークを過ぎ、青山城跡の南麓を巻いて壺笠城跡に至る。
尾根にある小さな谷路。倒木が多く登り難いが、 戦国時代の登城路はかくありなんと想わせてくれる趣がある。

高穴穂神社(御祭神:景行天皇、本殿:一間社流造)
伝・高穴穂宮跡
来た道を下り京阪線を越え少し歩くと左手、新興住宅地の奥にある児童公園から「高穴穂神社」の境内に入る。




山側の一段高くなったところに「高穴穂宮趾」の石碑。裏側には謂れが刻まれているようだが風化して判然としない。
境内を本殿に向かう途中に小さな石祠。 これって、何?
正月明けで静かな境内に参拝者は、無し~。
成務天皇は、先帝・景行天皇の遺徳を追頌し高穴穂宮内に祀り「天徳前王社(全王宮)」と称し、これがこの社の発祥と伝わっているとのこと。
鳥居の横に以下のような解説
『第十二代景行天皇、第十三代成務天皇、第十四代仲哀天皇と三帝の都の跡が高穴穂宮と称せられるものである。景行天皇の御代六十一年、仲哀天皇のおられたのは半年にしかならない。穴太を中心に扇状台地を領し都を営まれる好適地であったろうと思われる。現在の高穴穂神社の社殿が内裏のあった跡だとか、又はその西の住宅の中がその跡だとか云われている。』



高穴穂神社から宝光寺・盛安寺に向かう道(古代北陸道?)の脇に、石仏群、祠などが・・・比叡山麓には数多くある。

宝光寺 真如堂とも。
永観2年(984)、一条天皇の生母東三条院藤原詮子(ふじわらのせんし)が、比叡山常行堂にあった阿弥陀仏を祀って今の京都市左京区に造立した真正極楽寺(真如堂)が起こりとされる。応仁の乱で焼け、文明2年(1470)に現在地に移したとのこと。
木造阿弥陀如来立像(重要文化財・鎌倉後期)があるそうな・・・。


盛安寺との間にある観世音菩薩堂の石垣には、石仏が多用されている。



盛安寺(天台真盛宗)
穴太衆積みの石垣が美しい。
一際目立つ太鼓櫓には、天正年間、敵の急襲を知らせた恩賞として、光秀から庄田八石を賜ったと伝わる「明智の陣太鼓」がかかっているそうだ。
山門をくぐると境内には本堂、客殿、そして六体地蔵尊の横に明智光秀公の供養塔。
社伝によると、越前朝倉氏の家臣・杉若盛安(すぎわかもりやす)が天文年間(1532~1555)に再建したとのこと。
坂本城主・明智光秀の祈願所だったこともあり、「明智寺」とも。
天正年間には、明智光秀はもちろん豊臣秀吉が相次いでこの寺に天下泰平、玉体安穏の祈念を行ったこともあったが、元亀年間の兵火で焼失したと伝わっているとのこと。
天智天皇の勅願寺「崇福寺」(すうふくじ)伝来の十一面観音菩薩(重要文化財)が安置されており、正月三が日は特別公開されていた?

門前ニは、昔ながらの「畳屋」さん。

ここで、小雪が散らついて来たので駅に向かう。
湖東の近江富士(三上山)が琵琶湖越しに良く見える。
ここまでで、散策開始から1時間弱ほど。
雪も止み、お昼にはまだ十分時間があるので、駅を通り越して平子谷林道を壺笠城跡へ進む。






穴太野添古墳群(古墳時代後期の群集墳。昭和54年の分布調査で152基を確認)
盛安寺の墓地にはお参りの人がチラホラ・・・。
林道の北側(墓地の反対側)の木々が伐採されている。
墓地を拡張するのだろうか・・・近々に発掘調査が行われる?
古墳が5基ほど確認できる。墳丘上に天井石が露出しているものも。
奥の墳丘は中央部が凹んでいる。盗掘にあったというより壁石そのものが持ち去られた?
この墳丘の裾、西側の藪の中に石組みが見えるが、これは?
歩を進め、昭和61年~62年に17基を発掘調査が行われた古墳公園へ。
12号墳と16号墳のみ石室が露出展示(天井石なし)。
西端の17号墳に掌大の開口部があったので石室内部を撮影。
この比叡山麓穴太周辺の古墳からミニチュア炊飯具・カマドなど煮炊き用土器の副葬やドーム状の天井を持つ石室が、また古墳群から琵琶湖側に下がったところには弥生時代のオンドルや大壁つくりの建物遺構が出土しており、往時、朝鮮半島からの渡来系の人達が住んでいたと考えられている。
風も冷たくシャッターを切る手も凍えてきたので、
林の中の古墳群は次回に持ち越し・・・。
1時間半ほどの散策。
【参考】
12代景行、13代成務、14代仲哀の3天皇は実在性に疑問がもたれている。
景行天皇(大足彦忍代別天皇)は、垂仁天皇の第三皇子。
晩年、即位58年(西暦340年頃?)に磯城宮を離れ、近江の高穴穂宮に移り、当地で即位60年に106歳で亡くなり、翌々年、倭の山辺道上陵に葬られた。
成務天皇(稚足彦天皇)は、景行天皇の第四皇子。即位60年に107歳で亡くなり、倭の狭城楯列陵に葬られた。
仲哀天皇(足仲彦天皇)は、日本武尊(景行天皇の第二皇子)の第二子。即位9年にして病を患い、翌日、橿日宮(香椎宮?)にて死亡。52歳。河内の長野陵に葬られた。
(以上「日本書紀」)
兵主大社の社伝(「兵主大明神縁起」)によれば、『景行天皇58年、天皇は皇子・稲背入彦命に命じて大和国穴師(奈良県桜井市、現 穴師坐兵主神社?)に八千矛神(兵主大神)を祀らせた。近江国・高穴穂宮への遷都に伴い、稲背入彦命は宮に近い穴太に社地を定め、遷座した(高穴穂宮跡の「元兵主」)。のち欽明天皇の時代、播磨別(兵主族の祖先)らが琵琶湖を渡って東に移住する際、再び遷座して現在地に社殿を造営し鎮座したと伝え、以降、播磨別の子孫が神職を世襲している』とのこと。
この間、家籠りの日々が続いたためか、体がだるく頭痛。
毎食後、鎮痛剤の世話になっている。
久し振りに冷え込んだ比叡山麓、京阪石坂線の穴太駅周辺を散策。
穴太駒込古墳群
穴太駅を降りて西側、県道伊香立浜大津線を渡る。ここは県道が建設された昭和43年度に、また長さ60mほどのコンクリート壁の場所は、歩道拡幅工事に先立って平成15年度に発掘調査が行われたところ。
今は見る影もないが、昭和43年度に調査した石室が近くの「びわこ老人の家」の敷地内に移築されているとのこと(確認せず!)
県道を横断して比叡山に向かって登ると直ぐに右側の木々の間に由緒ありそうな石の祠、これって何?
仲哀天皇産湯の水
「湖の美が丘」住宅団地・壺坂城跡方面に向け引続き緩やかな舗装道路(※)を登ると、右の林間に井泉に向かう分岐道。
以前はフェンスに囲まれた禁足地で入れなかったのだが、今回、進入口のフェンスだけが無くなっていた。
四ツ谷川を右下に見ながら進むと左方向、一段高くなったところに「高穴穂神社 お旅所」の石柱。裏側には「穴穂神」と彫り込まれている。
その後ろに、まるで古墳の石室のような石囲いの水場。
これが「仲哀天皇の産湯に使った井泉」?
(※)この道、以前、平子谷林道が崩落して登れなかった時に辿った路。
送電線鉄塔のピークを過ぎ、青山城跡の南麓を巻いて壺笠城跡に至る。
尾根にある小さな谷路。倒木が多く登り難いが、 戦国時代の登城路はかくありなんと想わせてくれる趣がある。
高穴穂神社(御祭神:景行天皇、本殿:一間社流造)
伝・高穴穂宮跡
来た道を下り京阪線を越え少し歩くと左手、新興住宅地の奥にある児童公園から「高穴穂神社」の境内に入る。
山側の一段高くなったところに「高穴穂宮趾」の石碑。裏側には謂れが刻まれているようだが風化して判然としない。
境内を本殿に向かう途中に小さな石祠。 これって、何?
正月明けで静かな境内に参拝者は、無し~。
成務天皇は、先帝・景行天皇の遺徳を追頌し高穴穂宮内に祀り「天徳前王社(全王宮)」と称し、これがこの社の発祥と伝わっているとのこと。
鳥居の横に以下のような解説
『第十二代景行天皇、第十三代成務天皇、第十四代仲哀天皇と三帝の都の跡が高穴穂宮と称せられるものである。景行天皇の御代六十一年、仲哀天皇のおられたのは半年にしかならない。穴太を中心に扇状台地を領し都を営まれる好適地であったろうと思われる。現在の高穴穂神社の社殿が内裏のあった跡だとか、又はその西の住宅の中がその跡だとか云われている。』
高穴穂神社から宝光寺・盛安寺に向かう道(古代北陸道?)の脇に、石仏群、祠などが・・・比叡山麓には数多くある。
宝光寺 真如堂とも。
永観2年(984)、一条天皇の生母東三条院藤原詮子(ふじわらのせんし)が、比叡山常行堂にあった阿弥陀仏を祀って今の京都市左京区に造立した真正極楽寺(真如堂)が起こりとされる。応仁の乱で焼け、文明2年(1470)に現在地に移したとのこと。
木造阿弥陀如来立像(重要文化財・鎌倉後期)があるそうな・・・。
盛安寺との間にある観世音菩薩堂の石垣には、石仏が多用されている。
盛安寺(天台真盛宗)
穴太衆積みの石垣が美しい。
一際目立つ太鼓櫓には、天正年間、敵の急襲を知らせた恩賞として、光秀から庄田八石を賜ったと伝わる「明智の陣太鼓」がかかっているそうだ。
山門をくぐると境内には本堂、客殿、そして六体地蔵尊の横に明智光秀公の供養塔。
社伝によると、越前朝倉氏の家臣・杉若盛安(すぎわかもりやす)が天文年間(1532~1555)に再建したとのこと。
坂本城主・明智光秀の祈願所だったこともあり、「明智寺」とも。
天正年間には、明智光秀はもちろん豊臣秀吉が相次いでこの寺に天下泰平、玉体安穏の祈念を行ったこともあったが、元亀年間の兵火で焼失したと伝わっているとのこと。
天智天皇の勅願寺「崇福寺」(すうふくじ)伝来の十一面観音菩薩(重要文化財)が安置されており、正月三が日は特別公開されていた?
門前ニは、昔ながらの「畳屋」さん。
ここで、小雪が散らついて来たので駅に向かう。
湖東の近江富士(三上山)が琵琶湖越しに良く見える。
ここまでで、散策開始から1時間弱ほど。
雪も止み、お昼にはまだ十分時間があるので、駅を通り越して平子谷林道を壺笠城跡へ進む。
穴太野添古墳群(古墳時代後期の群集墳。昭和54年の分布調査で152基を確認)
盛安寺の墓地にはお参りの人がチラホラ・・・。
林道の北側(墓地の反対側)の木々が伐採されている。
墓地を拡張するのだろうか・・・近々に発掘調査が行われる?
古墳が5基ほど確認できる。墳丘上に天井石が露出しているものも。
奥の墳丘は中央部が凹んでいる。盗掘にあったというより壁石そのものが持ち去られた?
この墳丘の裾、西側の藪の中に石組みが見えるが、これは?
歩を進め、昭和61年~62年に17基を発掘調査が行われた古墳公園へ。
12号墳と16号墳のみ石室が露出展示(天井石なし)。
西端の17号墳に掌大の開口部があったので石室内部を撮影。
この比叡山麓穴太周辺の古墳からミニチュア炊飯具・カマドなど煮炊き用土器の副葬やドーム状の天井を持つ石室が、また古墳群から琵琶湖側に下がったところには弥生時代のオンドルや大壁つくりの建物遺構が出土しており、往時、朝鮮半島からの渡来系の人達が住んでいたと考えられている。
風も冷たくシャッターを切る手も凍えてきたので、
林の中の古墳群は次回に持ち越し・・・。
1時間半ほどの散策。
【参考】
12代景行、13代成務、14代仲哀の3天皇は実在性に疑問がもたれている。
景行天皇(大足彦忍代別天皇)は、垂仁天皇の第三皇子。
晩年、即位58年(西暦340年頃?)に磯城宮を離れ、近江の高穴穂宮に移り、当地で即位60年に106歳で亡くなり、翌々年、倭の山辺道上陵に葬られた。
成務天皇(稚足彦天皇)は、景行天皇の第四皇子。即位60年に107歳で亡くなり、倭の狭城楯列陵に葬られた。
仲哀天皇(足仲彦天皇)は、日本武尊(景行天皇の第二皇子)の第二子。即位9年にして病を患い、翌日、橿日宮(香椎宮?)にて死亡。52歳。河内の長野陵に葬られた。
(以上「日本書紀」)
兵主大社の社伝(「兵主大明神縁起」)によれば、『景行天皇58年、天皇は皇子・稲背入彦命に命じて大和国穴師(奈良県桜井市、現 穴師坐兵主神社?)に八千矛神(兵主大神)を祀らせた。近江国・高穴穂宮への遷都に伴い、稲背入彦命は宮に近い穴太に社地を定め、遷座した(高穴穂宮跡の「元兵主」)。のち欽明天皇の時代、播磨別(兵主族の祖先)らが琵琶湖を渡って東に移住する際、再び遷座して現在地に社殿を造営し鎮座したと伝え、以降、播磨別の子孫が神職を世襲している』とのこと。
下のバナー「歴史ブログ」をクリックしてね ・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)



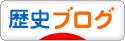
にほんブログ村



にほんブログ村
大和の国を歩く ~ 本薬師寺
飛鳥へ ~ 都塚古墳を訪ねる
奈良・春日山原始林を歩く
大和の国を訪ねる(2)・・・多神社・多遺跡、新沢千塚古墳群、室大墓へ
大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その3)
大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その2)
飛鳥へ ~ 都塚古墳を訪ねる
奈良・春日山原始林を歩く
大和の国を訪ねる(2)・・・多神社・多遺跡、新沢千塚古墳群、室大墓へ
大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その3)
大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その2)










