2014年10月04日
大和の国を歩く ~ 江戸時代の風情を今に伝える「今井町」

本薬師寺のホテイアオイを観たあと、
近鉄で北に1駅戻って八木西口駅下車。

JR線を支えるイギリス積の橋脚。

JR万葉まほろば線を潜って飛鳥川を蘇武橋で渡る。
今井町の東は、飛鳥川と環濠で2重に守られていた・・・。
橋の西詰に榎の大木、樹高15m・幹周5m・枝張20m。

その近くに
奈良縣里程元標(旧設置場所)の石標。

町を取囲む環濠はなくなっているのだけれど、
ここは北東側の入口・北尊坊門跡。

飛鳥川に沿って2つの蘇武井(そぶのい)。
いかなる日照りが続いても涸れることはなく、
今井の里千軒の家々に使われていたそうな~。
川面に井戸と柳・・・時代劇さながらの景色・・・?

南北2つの蘇武井の間の細い水路は、
かつてここに環濠があったことを示しており、
濠に降りる「洗い場」も復元されていた。


中尊坊門跡、南尊坊門跡を過ぎると華甍(今井まちなみ交流センター)。
明治36年(1903)建築の旧高市郡教育博物館。

エントランス。

手焙り。

町屋の復元模型
(17C後半の音村家主屋(推定))
格子の間から室内を覗いてみた・・・。

建物北側に、かつての環濠を復元。
この復元水路と
その先にわずかに残る細い水路に沿って西進。

辻に祀られている井上地蔵尊ほか。

今井町を
東西に分かつほぼ中心にある
辰巳口門跡を過ぎると
間もなく、唯一、
往時の姿に復元された南口門跡、土居。

ここから町内に入り
北に進むと称念寺。

真宗。
山門は明治10年、
明治天皇行幸に際して多武峰から移築、
太鼓楼は弘化2年(1845)建設。
本堂をはじめ、庫裏や客殿は
17C初期の建物だということなのだが、
修理中のため見学できず・・・。
そのため、道路際に写真パネルにより修理の模様を展示・説明。
(※ 後日、修理完了後に説明会を開催したそうな・・・)

今井町・・・16C中頃に、本願寺の一家衆であった今井氏により武装宗教都市としての「寺内町」が形成され、称念寺はその中核として興隆した。
武士と僧侶を兼ねていた今井氏が代々世襲していたが、江戸時代から釈門に専念したとのこと。
往時は東西4町半(約610m)・南北2兆20間(約31m)、
6町・1,200戸からなる町場を幅3間以上の環濠と土塁で囲まれていたとのこと。
現在は760戸ほどであるが、うち約550戸が江戸時代の伝統的形式の町屋だそうだ。

称念寺の向かいに夢ら咲長屋(案内・休憩所)。

中庭に、煙突の付いた甕。
・・・かつて、醤油の原料が不足していた時代、昭和初期に、大豆粕のタンパク質を加水分解したものを水酸化ナトリウムで中和してアミノ酸と食塩水を作り出し、このアミノ酸液に風味を加えたり醸造醤油とブレンドして、代用アミノ酸醤油を作っていたそうな~。
この煙突は、加水分解の際に圧力を逃がすとともに塩酸が漏れるのを防ぐ還流塔とのこと。

中橋家(米屋、のちに肥料、金物も商う)、細格子の出窓。
19C初期に上部の柱を継ぎ足して低い「つし2階(中2階)」建てに変更されたとのこと。
町内を歩くと、エリアごとに軒高が低い家と高い家が並んでいることに気がつく。
この街を歩くと平屋から2階建てへの町屋の変化を観ることが出来る。

豊田家・・・豪壮な町屋。材木商『紙八』。

玄関口に駒つなぎ、
1階の太い大和格子、2階に白い漆喰の塗り込め壁。

遅くなった昼食は、
路地に入り、一筋北にある古伊で、
「柿の葉寿司&そば」を食する。

田舎づくりなのか醤油辛い出汁は、
そばを活かせていない。


本町筋を西に進み、
今西家の西側・西口門跡で復元された環濠を見る。

今西家・・・町の西端、城郭のような八ツ棟造。
もとは中世に当地を治めていた十市氏の一族で、
代々今井町の惣年寄の筆頭として、
町方支配の一翼を担っていたそうな・・・。

2階の壁に
ご当家旧姓の河合氏定紋と
3段菱形の旗印。


ここから南東隅の環濠は、
内、中、外と3重になっていたそうで、
外環濠は発掘調査中だった。


環濠に挟まれた中堤を進み、
壁絵が印象的な春日神社へ・・・。
復元された船着場の南側から境内に入る。
 端正な佇まいの旧常福寺観音堂と
端正な佇まいの旧常福寺観音堂と一面二体の『叶』地蔵尊。
この後、家並みの中をぶらぶら歩く。







上田家・・・ここも江戸時代の惣年寄の一つ。片岡城主片岡氏の子孫。酒造業『壺屋』。「つし2階」の低い2階建て。
米谷家・・・農家風の民家のイメージ。金物・肥料商『米忠』。「つし2階」の低い2階建て。
音村家・・・金物商『細九』。「つし2階」の低い2階建て。
などなど~。
道標。



右往左往して町の東端に出たところで、きょうの散策はおしまい。
旧家が、線ではなく面としてたくさん残っていて、
街もキレイで歩きやすく
「凄~い!」とは思うのだけれど
そのことが逆に数時間も滞在していると、
変化を感じなくなって(面白みもなくなり)
少々、食傷気味になって、観察する眼もお疲れモードに・・・
無料の休憩所もあるのだけれど・・・なにか物足りなさを感じる。
そんな印象の町だった。
この日の歩数:14,709歩
ところで、町を歩いていて気になったこと・・・豊かさの表れなのか、この街には銅を使った雨といが目につく。
帰宅後、ネットで検索したが、意外と雨といに関する記事が少なく、見つかったのがPanasonicのHP。他にも記事はあったが、多くはPanaの記事を転用したものか・・・。で、以下Pana記事の要約。
①雨といのはじまり・・・多棟住宅の谷の部分「あわい」に取り付けた「受け樋」(「懸樋(かけひ)」とも)で、雨水を排水する役目よりも、むしろ飲料水や生活用水として貴重であった雨水を、屋根から水槽に導く「上水道」の役割を果たしていた。
屋根の雨水を排水するという役割の雨といで、わが国に現存する最古のものは、奈良時代(733年)に建立された東大寺三月堂の木製、厚さ約5cmの板3枚をU字型に組み立てたもの。
雨といは江戸時代まで、神社仏閣を中心に普及。当時の神社仏閣には、すでに飛鳥時代に中国、朝鮮から伝来した瓦が使われ、雨水を処理する雨といが必要だった。
しかし、一般の住宅は「草ぶき」や「かやぶき」がほとんどで、屋根自体が水分を吸収することや、軒先を作業場として利用する必要から庇(ひさし)を長く張り出して軒を深く取っていたため、雨といの必要がなかった。
②雨といの普及・・・江戸時代に入ると商業が盛んになり、江戸、大阪、京都などを中心に人口が集中し、都市が形成されるに伴って住宅も密集して隣家と軒を接するようになり、隣家の雨水が流れ込む、雨だれが跳ね返って壁を汚す、土台を腐らせる、といったトラブルが起こる。
一方、密集した「かやぶき、板ぶき屋根」の町家は火災に弱く、ひとたび出火すれば次々と類焼して、町中が火の海ということがたびたび起こった。大火に悩んだ幕府は1720年、防火のために民家の屋根を「瓦ぶき」にするよう奨励。
また、商家では財産を火災や盗難から守る土蔵をはじめ、経済力にものをいわせて住宅を豪華にすることで武士階級に対抗したため、瓦屋根でしかも複雑な屋根構造の町家が出現。
瓦ぶき屋根の普及により、雨水の落下で柱の根元や土台が腐ったり、傷んだりするのを防ぐため、雨といが使われるようになる。
当時は、雨といの材料として一般的に手に入るものとしては、木や竹など自然のもの。とりわけ竹は、奈良時代の「懸樋」の頃から利用されており、節を抜けばパイプ状になる、半分に割れば半円形になるなど、雨といの材料としてはたいへん好都合であったことから、最もよく使われた。
当時の施工方法は、軒先の垂木に板を削った雨とい受けを打ちつけ、その上に竹製の雨といを乗せていた。その他には、板をU字型に打ちつけた「箱とい」や2枚の板をV字型に打ちつけた簡素なものがあった。
③雨といの発展・・・文明開化とともに海外との交流が盛んになり、洋風の建築技術も流入。
そのなかに、すでに高度な加工技術による装飾性にすぐれた雨といも当然含まれていた。
「ブリキ(Brrick、薄い鉄板に錫をメッキしたもの)屋」と呼ばれる専門職の誕生。
当時は輸入したレンガの包装材料や石油の容器などに使われており、これらの廃品を加工して、
煙突や流し台、半円形の軒とい、円筒のたてといなどをつくる職人が出現した。これが現在の「板金店」のルーツ。
金属性の雨といが出現する下地となった金属加工技術は、古く鎌倉時代から、なべ、かま、農具などの修理をしていた鋳掛(いかけ)屋、銅を加工して長もち、たんす、灯籠などの装飾金物をつくっていた銅(あかがね)細工師、江戸時代後期には錺(かざり)師と呼ばれた人たちの技術による。
明治になって海外から入ってきた新しい材料の金属板を加工するうえで役立った。 金属材料による雨といづくりが一般に普及していった明治時代、当時の板金職人たちは、お互いの技能を磨くために諸国をまわり、各地の職人たちを訪ねて修行の旅をして自分独自の流儀をつくり上げた。
また、この頃に銅板が徐々に普及し、高級感や緑青の発生などが、わび、さびといった風流好みの日本人の感覚に受け入れられて、一文字屋根や雨といの材料として使用された。
一部の高級な建物には、雨といに竹や梅のデザインを細工したものや、縁起をかついで蛇や龍などの飾り物を取り付けた「装飾雨とい」が出現。
こうした技術や軒先を引き立てる装飾性が、雨といの顔といわれる集水器(アンコー)に引き継がれ現在に至っている。
なお、一般住宅では、ブリキ板や後にトタン板と呼ばれる亜鉛引鉄板が登場し主流となった。
とあり、銅製の雨といの採用は、明治以降の風流の結果であることを再確認した。
下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
にほんブログ村
主に滋賀県内の遺跡・史跡などの探訪録は、
コチラ ⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2
2014年10月01日
大和の国を歩く ~ 本薬師寺
碧花の海に浮かぶ寺跡を訪ねてきた。

出発は、近鉄・畝傍御陵前駅の東口。
駅広にあるモニュメント・・・何?? (※1)
東に、本薬師寺跡(※2)に向かう。



ホテイアオイ。

西には、西塔跡と畝傍山。

東には、東塔跡と天香久山。


東塔跡の礎石。 帯状の凹が四角に廻る。
 本薬師寺跡に建つ「白鳳山醫王院」と「本薬師寺金堂の礎石」。
本薬師寺跡に建つ「白鳳山醫王院」と「本薬師寺金堂の礎石」。
その壁に張られた1枚の紙。
(※ 表記は原文のまま)

無題(「わが憩いの場所」欄)
拙宅から20分ほどゆけば、大和盆地への峠がある。
それをこえて3、40分もゆくと飛鳥の古墳と丘陵のむれのなかに入る。
近所だと思って、ときどきゆく。
飛鳥はおなじ大和でも奈良、西ノ京、斑鳩などとはちがい、荒れることからややまぬがれている。
修学旅行団も、観光バスもここまではあまり来ない。
きょう、田の中にある元薬師寺の礎石の群れをさがしあてた。
礎石のむこうは葦牙のにおいたつような万葉ふうの野、といいたいが、そこまで注文どおりにはいかない。
畝傍の裏のただの麦畑である。
(昭和41年6月「司馬遼太郎が考えたこと 3」)


この後、近世の家並みが残る環濠集落の今井町に向かった。
(※1) 帰宅後、橿原市に照会したところ、以下の回答を得た。
「モニュメントは、‟龍の玉″です。モニュメントの北側に喫茶店があります。その裏手に龍の噴水があり、駅前整備の際に龍の噴水と合わせて、当時、建設コンサルタントの意見を基に設置されました。」とのこと。
「なんで、‟龍の玉″なんだろう?」との疑問をMFさんに伝えたところ、以下の記事をご教示いただいた。
「畝傍御陵前駅の東側、社会福祉総合センターのあたりには、昔、池があった。「雨字池(あめじいけ)」、通称「大久保池」と呼ばれた。雨字池とは、雨水をイメージして名付けられたという。その昔、何人もの人が入水自殺をしたという伝聞もある。雨字池は、畝傍御陵前駅周辺の都市開発のため、1988(昭和63)年、橿原市によって買収され、1989(平成元)年埋め立てられた。
社会福祉総合センターの玄関前には、龍の噴水がある。駅の東側ということで、東方を守護する四神(青龍・朱雀・白虎・玄武)の一人「青龍」を設置したということである。また、水の神といわれる龍を設置したことは、ここに池があったことを後世に伝えるためでもあり、入水者たちの霊を慰めるためでもあるといわれている。
また、地元の要望により、池の由来が記された石碑も残され、市営立体駐車場の北西の角に移転された。」
出典:植田寿之HP「対人援助のお勉強ブログ」2013年1月6日(日)、10日(木) 奈良県 介護支援専門員実務研修 から抜粋
(※2)本薬師寺跡(もとやくしじあと)

藤原京の薬師寺、後の持統天皇となる皇后の病気平癒を祈って天武天皇が建立を誓願した官寺。平城京遷都で薬師寺が西ノ京に移ると、両寺を区別するために本薬師寺と呼ばれる。
発掘調査により、11世紀初頭まで存続していたことが認められた。
現在は、白鳳山醫王院の境内に、伽藍遺構のうち金堂の礎石の一部が残り、東塔や西塔の心礎などホテイアオイに囲まれた基壇が残存している。
下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
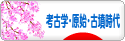
にほんブログ村
主に滋賀県内の遺跡・史跡などの探訪録は、
コチラ ⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2

出発は、近鉄・畝傍御陵前駅の東口。
駅広にあるモニュメント・・・何?? (※1)
東に、本薬師寺跡(※2)に向かう。



ホテイアオイ。

西には、西塔跡と畝傍山。

東には、東塔跡と天香久山。


東塔跡の礎石。 帯状の凹が四角に廻る。
 本薬師寺跡に建つ「白鳳山醫王院」と「本薬師寺金堂の礎石」。
本薬師寺跡に建つ「白鳳山醫王院」と「本薬師寺金堂の礎石」。その壁に張られた1枚の紙。
(※ 表記は原文のまま)

無題(「わが憩いの場所」欄)
拙宅から20分ほどゆけば、大和盆地への峠がある。
それをこえて3、40分もゆくと飛鳥の古墳と丘陵のむれのなかに入る。
近所だと思って、ときどきゆく。
飛鳥はおなじ大和でも奈良、西ノ京、斑鳩などとはちがい、荒れることからややまぬがれている。
修学旅行団も、観光バスもここまではあまり来ない。
きょう、田の中にある元薬師寺の礎石の群れをさがしあてた。
礎石のむこうは葦牙のにおいたつような万葉ふうの野、といいたいが、そこまで注文どおりにはいかない。
畝傍の裏のただの麦畑である。
(昭和41年6月「司馬遼太郎が考えたこと 3」)


この後、近世の家並みが残る環濠集落の今井町に向かった。
(※1) 帰宅後、橿原市に照会したところ、以下の回答を得た。
「モニュメントは、‟龍の玉″です。モニュメントの北側に喫茶店があります。その裏手に龍の噴水があり、駅前整備の際に龍の噴水と合わせて、当時、建設コンサルタントの意見を基に設置されました。」とのこと。
「なんで、‟龍の玉″なんだろう?」との疑問をMFさんに伝えたところ、以下の記事をご教示いただいた。
「畝傍御陵前駅の東側、社会福祉総合センターのあたりには、昔、池があった。「雨字池(あめじいけ)」、通称「大久保池」と呼ばれた。雨字池とは、雨水をイメージして名付けられたという。その昔、何人もの人が入水自殺をしたという伝聞もある。雨字池は、畝傍御陵前駅周辺の都市開発のため、1988(昭和63)年、橿原市によって買収され、1989(平成元)年埋め立てられた。
社会福祉総合センターの玄関前には、龍の噴水がある。駅の東側ということで、東方を守護する四神(青龍・朱雀・白虎・玄武)の一人「青龍」を設置したということである。また、水の神といわれる龍を設置したことは、ここに池があったことを後世に伝えるためでもあり、入水者たちの霊を慰めるためでもあるといわれている。
また、地元の要望により、池の由来が記された石碑も残され、市営立体駐車場の北西の角に移転された。」
出典:植田寿之HP「対人援助のお勉強ブログ」2013年1月6日(日)、10日(木) 奈良県 介護支援専門員実務研修 から抜粋
(※2)本薬師寺跡(もとやくしじあと)

藤原京の薬師寺、後の持統天皇となる皇后の病気平癒を祈って天武天皇が建立を誓願した官寺。平城京遷都で薬師寺が西ノ京に移ると、両寺を区別するために本薬師寺と呼ばれる。
発掘調査により、11世紀初頭まで存続していたことが認められた。
現在は、白鳳山醫王院の境内に、伽藍遺構のうち金堂の礎石の一部が残り、東塔や西塔の心礎などホテイアオイに囲まれた基壇が残存している。
下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
にほんブログ村
主に滋賀県内の遺跡・史跡などの探訪録は、
コチラ ⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2
2014年08月17日
飛鳥へ ~ 都塚古墳を訪ねる
飛鳥と纏向、毎年、
互いに競うように『新発見!』という文字が躍る
大和盆地の東南エリアの考古の世界・・・
今回は、その最端部にある古墳の説明会に行ってきた。
スタートは、
この地方固有の大和棟を模した駅舎を持つことなどから
「近畿の駅百選」に選ばれた近鉄・橿原神宮駅の東口。


明日香周遊バス「かめバス(赤かめ)」に乗って石舞台BSへ。
(※ 写真は飛鳥資料館前BSのかめバス)

 ここから冬野川とその支流・都塚川に
ここから冬野川とその支流・都塚川に
ほぼ並行して緩やかな坂道を進むこと1時間ほど
(この日は見学の順番待ちのため・・・何もなければ10分ほど?)


以下、見学順路にしたがって主な調査区ごとに見ると

1区・・・墳丘裾北端の確認。幅1~1.5m、深さ≒0.4mの周濠。周濠護岸およびテラス面に拳~人頭大の石材。

3区・・・墳丘裾南西端の確認。1段目のテラス幅員≒6m。

 4区・・・墳丘2段目の西法面、高さ≒3m。
4区・・・墳丘2段目の西法面、高さ≒3m。
石室・・・南西に開口した両袖式横穴石室。全長=12.2m、玄室長=5.3m・幅=2.8m・高=3.55m、羨道長=6.9m・幅=1.9~2.0m・高≒2m。石材は、「飛鳥石(石英閃緑岩)」。玄室内に暗渠排水溝あり。

石棺・・・二上山凝灰岩製の刳抜式家形石棺。石棺の総高=1.74m。棺身長=2.23m・幅=1.46m・高=1.08m(内法長=1.74m・幅=0.82m・深=0.65m)


8区・・・墳丘裾南東端の確認。
7区・・・上部墳丘上の段状になった石積み4段を確認。

以下、都塚古墳の概要
6C後半。東西≒41m・南北≒42m・高≧4.5m(尾根先に築かれているため、西側からの見かけ上の高さは7m以上)。
古墳周辺は、6~7Cにおける蘇我氏の本拠地。


当初、都塚古墳を見学後、
ミニチュア竃などを出土した細川谷古墳群(蘇我氏の奥津城?)の探訪を予定していたが・・・
変更して、奈文研・飛鳥資料館へ。

前庭に置かれた
亀石・猿石、石人像、須弥山石など
飛鳥の石造物(レプリカ)は、いつ観ても楽しい~。













この日の歩行数 7,319歩
下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
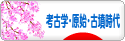
にほんブログ村
滋賀県内の遺跡・史跡などの探訪録は、
コチラ ⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2
互いに競うように『新発見!』という文字が躍る
大和盆地の東南エリアの考古の世界・・・
今回は、その最端部にある古墳の説明会に行ってきた。
スタートは、
この地方固有の大和棟を模した駅舎を持つことなどから
「近畿の駅百選」に選ばれた近鉄・橿原神宮駅の東口。


明日香周遊バス「かめバス(赤かめ)」に乗って石舞台BSへ。
(※ 写真は飛鳥資料館前BSのかめバス)

 ここから冬野川とその支流・都塚川に
ここから冬野川とその支流・都塚川にほぼ並行して緩やかな坂道を進むこと1時間ほど
(この日は見学の順番待ちのため・・・何もなければ10分ほど?)


以下、見学順路にしたがって主な調査区ごとに見ると

1区・・・墳丘裾北端の確認。幅1~1.5m、深さ≒0.4mの周濠。周濠護岸およびテラス面に拳~人頭大の石材。

3区・・・墳丘裾南西端の確認。1段目のテラス幅員≒6m。

 4区・・・墳丘2段目の西法面、高さ≒3m。
4区・・・墳丘2段目の西法面、高さ≒3m。石室・・・南西に開口した両袖式横穴石室。全長=12.2m、玄室長=5.3m・幅=2.8m・高=3.55m、羨道長=6.9m・幅=1.9~2.0m・高≒2m。石材は、「飛鳥石(石英閃緑岩)」。玄室内に暗渠排水溝あり。

石棺・・・二上山凝灰岩製の刳抜式家形石棺。石棺の総高=1.74m。棺身長=2.23m・幅=1.46m・高=1.08m(内法長=1.74m・幅=0.82m・深=0.65m)


8区・・・墳丘裾南東端の確認。
7区・・・上部墳丘上の段状になった石積み4段を確認。

以下、都塚古墳の概要
6C後半。東西≒41m・南北≒42m・高≧4.5m(尾根先に築かれているため、西側からの見かけ上の高さは7m以上)。
古墳周辺は、6~7Cにおける蘇我氏の本拠地。


当初、都塚古墳を見学後、
ミニチュア竃などを出土した細川谷古墳群(蘇我氏の奥津城?)の探訪を予定していたが・・・
変更して、奈文研・飛鳥資料館へ。

前庭に置かれた
亀石・猿石、石人像、須弥山石など
飛鳥の石造物(レプリカ)は、いつ観ても楽しい~。













この日の歩行数 7,319歩
下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
にほんブログ村
滋賀県内の遺跡・史跡などの探訪録は、
コチラ ⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2
2014年08月01日
奈良・春日山原始林を歩く
少し前のことだけれど、明後日は梅雨明け~という日、
イベントに参加して、原始林の中を歩いてきた。

原始林?、原生林??
ネットで検索すると、
「原生林(げんせいりん)はある程度昔から現在まで、伐採や災害などによって破壊(森林破壊)されたことがなく、またほとんど人手が加えられたことのない自然のままの森林をさす。それらが一切無いものを原始林というが、それに準ずるものである。」とのことだが、
「春日山原始林 - 古都奈良に存在する原生林(1998年世界遺産文化遺産)。」の記載もあり、意味不明~(笑)
これまで、登山などで『原生林』を多く訪ねてきたことはある。
それらの多くは、古代から人の手が入っていないような登山路すら満足にないブナ林や照葉樹林など・・・。
春日大社の山として禁伐令が841年に出されてから積極的に保護された結果、極相に達した原生林が6千年前から変わらず広がっているとのこと。
さて、雲行の怪しいなか、近鉄・奈良駅から路線バスに乗って、奈良公園へ。

道に迷いつつ春日大社近くの駐車場から遊歩道に入り、水谷川に沿って歩く。

川岸には趣のある茶店。


木々の間、緩やかな登りの続く道はやがて鎌研交番所に・・・。
駐車場の脇を西に進むと鶯塚古墳。

鹿の群れの横を通って若草山の山頂(342m)に到達。
あいにくの天気で遠望は利かなかったが、それでも山麓の東大寺をはじめ奈良市内は良く観えた。

若草山・・・山全体が芝生でおおわれている。
この芝生、日本固有のシバで、近畿では若草山付近が唯一の自生地とのこと。
ノシバの種は堅い殻に覆われており、鹿がシバの葉と共に種を食べても、鹿の歯と胃液による消化などから堅い殻が種を守る。
ただ守るだけでなく、鹿の胃に入ると、胃液と体温(40度程度)で殻は速やかに溶けて発芽できる状態になり、未消化の種は糞とともに山に散布されることにより、ノシバは発芽する。
このサイクルを繰り返し、古来よりこの地で生息してきたそうだ。
鶯塚古墳・・・5C、全長103m・前方部幅約50m・後円部径61m、二段築成の前方後円墳。
前方部に露出している葺石の確認ができる。
日本考古学の大先達・濱田耕作はここでも埴輪を採集したとか・・・。
後円部の墳丘上に享保13年(1733)に建てられたという「鶯陵」の顕彰碑がある。


清少納言が「枕草子」の第17段に、
陵(みささぎ)は うぐひすの陵(みささぎ)。柏原の陵。あめの陵。
と書いている「うぐひすのみささぎ」がここだとも・・・。
16代仁徳天皇の皇后、磐之媛命の墓は、現在、奈良市の北郊にある佐紀盾列古墳群のヒシアゲ古墳(平城坂上陵)が比定されている。
現在の位置に比定されたのは明治になってからで、それまでは「平城天皇陵」とされていたそうである。

ところで、この磐之媛命、葛城襲津彦の娘だが、なぜ仁徳天皇と離ればなれに葬られているのかというと・・・、「書紀」(巻第十一 大鷦鷯天皇 仁德天皇)によれば、皇后である磐之媛命が紀の国へ出かけている留守に、天皇は八田皇女を難波宮に呼び寄せて寵愛したので、怒った皇后はそれ以後、筒城宮(現・京都府綴喜郡)に入って天皇の求めにも応じず、その後その地で亡くなる。
「書紀」には、
卅五年夏六月、皇后磐之媛命、薨於筒城宮。
卅七年冬十一月甲戌朔乙酉、葬皇后於乃羅山。
即ち、
仁徳天皇35年夏6月、皇后磐之媛命は筒城宮でなくなられた。
37年冬11月12日、皇后をナラ山に葬った。
と、ごく簡単に記載している。
なお、磐之媛は、履中・反噬正・允恭の各天皇の母。
駐車場まで戻って春日奥山道路を進むと、直ぐに十八丁休憩所。
この休憩所の傍らにある石仏。
白粉を塗って、唇に紅が・・・悪戯?。
なんとも異様な顔になっていた。

花山・地蔵の背を過ぎ、春日奥山の最大の山桜の下を通り、さらに進むと谷から水音が聞こえてきた。


案内の石碑に導かれ、遊歩道から分れて下降すると落差10mほどの鶯の瀧。
滝の名は、この辺りで美しく囀る金色の小鳥を、神功皇后が「うぐいす」と名付け愛玩したことに、あるいは滝から落ちる水音がうぐいすの鳴声のように聞こえることに由来するともいわれているそうな・・・。

元の遊歩道に戻ると直ぐに大原橋休憩所。
ここに「春日山原始林」の石標が建っている。
その横からも鶯の瀧に至るルートがある。
変化のない樹林帯を進むと、間もなく芳山交番所。
ここでクルマの通る春日奥山道路と別れ、未舗装の「柳生街道(滝坂道)」を下るとやがて江戸時代に奈良奉行によって敷かれたという石畳道に・・・。

ここは、柳生の道場を目指す剣豪たちが往来した道。
そこの三叉路に高さ2mほどの首切地蔵が立っている。
柳生十兵衛の弟子・荒木又右衛門がためし切りしたと伝わるとおり、首のところは、真一文字にセメントで繋がれている様子。

原始林の中、能登川沿いに石畳道を下っていくと間もなく、磨崖仏・朝日観音。
真ん中に弥勒菩薩像、その両側に地蔵菩薩が刻まれている。
東面しており、朝日に映えるのでこの名が付いたとか・・・。

続いて、壁面に夕日観音。

そのすぐ先の道端に、崖から転がり落ちてきたのか、横向きの大日如来像・寝仏。

右手に古墳状の連なるマウンドを見ながら下ると白乳神社、飛鳥中学校、志賀直哉旧居を経て砥石町のBSに辿り着いた。


春日山原始林・・・寒地性植物群と亜熱帯性植物群など多様な植物相が評価された特別天然記念物。
また、春日大社や東大寺などの建造物群と合わせて世界文化遺産にも登録されている。


千年以上、手つかずの樹林の中を歩いていると自然の力・強風のためか、所々で幹の途中から折れた大木や根元から倒れた木々が目に付いた。
その中で育っているのがナギやナンキンハゼ。
これらの木々の出現によって春日山原始林の多様性が劣化し、春日山の照葉樹林も徐々に崩壊しつつあるのだろうか・・・。

この日の総歩行数:26,676歩
下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
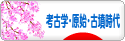
にほんブログ村
滋賀県内の遺跡・史跡などの探訪録は、
コチラ ⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2
イベントに参加して、原始林の中を歩いてきた。

原始林?、原生林??
ネットで検索すると、
「原生林(げんせいりん)はある程度昔から現在まで、伐採や災害などによって破壊(森林破壊)されたことがなく、またほとんど人手が加えられたことのない自然のままの森林をさす。それらが一切無いものを原始林というが、それに準ずるものである。」とのことだが、
「春日山原始林 - 古都奈良に存在する原生林(1998年世界遺産文化遺産)。」の記載もあり、意味不明~(笑)
これまで、登山などで『原生林』を多く訪ねてきたことはある。
それらの多くは、古代から人の手が入っていないような登山路すら満足にないブナ林や照葉樹林など・・・。
春日大社の山として禁伐令が841年に出されてから積極的に保護された結果、極相に達した原生林が6千年前から変わらず広がっているとのこと。
さて、雲行の怪しいなか、近鉄・奈良駅から路線バスに乗って、奈良公園へ。

道に迷いつつ春日大社近くの駐車場から遊歩道に入り、水谷川に沿って歩く。

川岸には趣のある茶店。


木々の間、緩やかな登りの続く道はやがて鎌研交番所に・・・。
駐車場の脇を西に進むと鶯塚古墳。

鹿の群れの横を通って若草山の山頂(342m)に到達。
あいにくの天気で遠望は利かなかったが、それでも山麓の東大寺をはじめ奈良市内は良く観えた。

若草山・・・山全体が芝生でおおわれている。
この芝生、日本固有のシバで、近畿では若草山付近が唯一の自生地とのこと。
ノシバの種は堅い殻に覆われており、鹿がシバの葉と共に種を食べても、鹿の歯と胃液による消化などから堅い殻が種を守る。
ただ守るだけでなく、鹿の胃に入ると、胃液と体温(40度程度)で殻は速やかに溶けて発芽できる状態になり、未消化の種は糞とともに山に散布されることにより、ノシバは発芽する。
このサイクルを繰り返し、古来よりこの地で生息してきたそうだ。
鶯塚古墳・・・5C、全長103m・前方部幅約50m・後円部径61m、二段築成の前方後円墳。
前方部に露出している葺石の確認ができる。
日本考古学の大先達・濱田耕作はここでも埴輪を採集したとか・・・。
後円部の墳丘上に享保13年(1733)に建てられたという「鶯陵」の顕彰碑がある。


清少納言が「枕草子」の第17段に、
陵(みささぎ)は うぐひすの陵(みささぎ)。柏原の陵。あめの陵。
と書いている「うぐひすのみささぎ」がここだとも・・・。
16代仁徳天皇の皇后、磐之媛命の墓は、現在、奈良市の北郊にある佐紀盾列古墳群のヒシアゲ古墳(平城坂上陵)が比定されている。
現在の位置に比定されたのは明治になってからで、それまでは「平城天皇陵」とされていたそうである。

ところで、この磐之媛命、葛城襲津彦の娘だが、なぜ仁徳天皇と離ればなれに葬られているのかというと・・・、「書紀」(巻第十一 大鷦鷯天皇 仁德天皇)によれば、皇后である磐之媛命が紀の国へ出かけている留守に、天皇は八田皇女を難波宮に呼び寄せて寵愛したので、怒った皇后はそれ以後、筒城宮(現・京都府綴喜郡)に入って天皇の求めにも応じず、その後その地で亡くなる。
「書紀」には、
卅五年夏六月、皇后磐之媛命、薨於筒城宮。
卅七年冬十一月甲戌朔乙酉、葬皇后於乃羅山。
即ち、
仁徳天皇35年夏6月、皇后磐之媛命は筒城宮でなくなられた。
37年冬11月12日、皇后をナラ山に葬った。
と、ごく簡単に記載している。
なお、磐之媛は、履中・反噬正・允恭の各天皇の母。
駐車場まで戻って春日奥山道路を進むと、直ぐに十八丁休憩所。
この休憩所の傍らにある石仏。
白粉を塗って、唇に紅が・・・悪戯?。
なんとも異様な顔になっていた。

花山・地蔵の背を過ぎ、春日奥山の最大の山桜の下を通り、さらに進むと谷から水音が聞こえてきた。


案内の石碑に導かれ、遊歩道から分れて下降すると落差10mほどの鶯の瀧。
滝の名は、この辺りで美しく囀る金色の小鳥を、神功皇后が「うぐいす」と名付け愛玩したことに、あるいは滝から落ちる水音がうぐいすの鳴声のように聞こえることに由来するともいわれているそうな・・・。

元の遊歩道に戻ると直ぐに大原橋休憩所。
ここに「春日山原始林」の石標が建っている。
その横からも鶯の瀧に至るルートがある。
変化のない樹林帯を進むと、間もなく芳山交番所。
ここでクルマの通る春日奥山道路と別れ、未舗装の「柳生街道(滝坂道)」を下るとやがて江戸時代に奈良奉行によって敷かれたという石畳道に・・・。

ここは、柳生の道場を目指す剣豪たちが往来した道。
そこの三叉路に高さ2mほどの首切地蔵が立っている。
柳生十兵衛の弟子・荒木又右衛門がためし切りしたと伝わるとおり、首のところは、真一文字にセメントで繋がれている様子。


原始林の中、能登川沿いに石畳道を下っていくと間もなく、磨崖仏・朝日観音。
真ん中に弥勒菩薩像、その両側に地蔵菩薩が刻まれている。
東面しており、朝日に映えるのでこの名が付いたとか・・・。

続いて、壁面に夕日観音。

そのすぐ先の道端に、崖から転がり落ちてきたのか、横向きの大日如来像・寝仏。

右手に古墳状の連なるマウンドを見ながら下ると白乳神社、飛鳥中学校、志賀直哉旧居を経て砥石町のBSに辿り着いた。


春日山原始林・・・寒地性植物群と亜熱帯性植物群など多様な植物相が評価された特別天然記念物。
また、春日大社や東大寺などの建造物群と合わせて世界文化遺産にも登録されている。


千年以上、手つかずの樹林の中を歩いていると自然の力・強風のためか、所々で幹の途中から折れた大木や根元から倒れた木々が目に付いた。
その中で育っているのがナギやナンキンハゼ。
これらの木々の出現によって春日山原始林の多様性が劣化し、春日山の照葉樹林も徐々に崩壊しつつあるのだろうか・・・。

この日の総歩行数:26,676歩
下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
にほんブログ村
滋賀県内の遺跡・史跡などの探訪録は、
コチラ ⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2
2014年07月20日
大和の国を訪ねる(2)・・・多神社・多遺跡、新沢千塚古墳群、室大墓へ
筒井城から多神社(多坐弥志理都比古神社)へ。

ここは、
太安万侶らをはじめとする
古代氏族多氏の本貫地?
この冬、
纏向遺跡など田原本町内を散策した折に、
夕刻タイムアウトになったため訪れることができなかった処。
書紀 巻第三 神日本磐余彥天皇 神武天皇に
辛酉年春正月庚辰朔、天皇卽帝位於橿原宮、是歲爲天皇元年。尊正妃爲皇后、生皇子神八井命・神渟名川耳尊。
とあり、
神武天皇が即位されたこと、皇子の神八井命と神淳名川耳尊(第三子、綏靖天皇)が生まれたことなどが記載されている。
さらに、巻第四 神渟名川耳天皇 綏靖天皇に
・・・神日本磐余彥天皇崩。・・・其庶兄手硏耳命、行年已長、久歷朝機。故、亦委事而親之。然其王、立操厝懷、本乖仁義、遂以諒闇之際、威福自由、苞藏禍心、圖害二弟。・・・。
冬十一月、神渟名川耳尊、與兄神八井耳命、陰知其志而善防之。至於山陵事畢、乃使弓部稚彥造弓、倭鍛部天津眞浦造眞麛鏃、矢部作箭。及弓矢既成、神渟名川耳尊、欲以射殺手硏耳命。會有手硏耳命於片丘大窨中獨臥于大牀、時渟名川耳尊、謂神八井耳命曰「今適其時也。夫言貴密、事宜愼、故我之陰謀、本無預者。今日之事、唯吾與爾自行之耳。吾當先開窨戸、爾其射之。」
因相隨進入、神渟名川耳尊、突開其戸。神八井耳命、則手脚戰慄、不能放矢。時神渟名川耳尊、掣取其兄所持弓矢而射手硏耳命、一發中胸、再發中背、遂殺之。於是、神八井耳命、懣然自服、讓於神渟名川耳尊曰「吾是乃兄、而懦弱不能致果。今汝特挺神武、自誅元惡。宜哉乎、汝之光臨天位、以承皇祖之業。吾當爲汝輔之、奉典神祇者。」是卽多臣之始祖也。
・・・四年夏四月、神八井耳命薨。卽葬于畝傍山北。
とあり、
神武天皇の崩御後、兄(第一子)の手硏耳命が権力を欲しいままにし、二人の弟(神八井耳命と神渟名川耳尊)を殺そうと企てたが、そのことを知った二人は・・・。ふるえおののいて矢を射ることができなかった神八井耳命の弓矢を神渟名川耳尊が取って胸と背中を射抜いて殺した。これを恥じて神八井耳命は皇位を神渟名川耳尊に譲った。・・・ことなどが記載されている。
多神社(多坐弥志理都比古神社)、「みしりつひこ(=神八井耳命)」。
神武天皇の子でありながら弟に皇位を譲ったので、「身を退いた」という意味?
もっとも、末子相続制の習俗を反映かな??っていう見方も・・・。
鳥居をくぐると、整然と並んだ石灯籠。

境内の左に築地塀で囲まれた神職の館。

正面、拝殿の後ろに春日造社殿1間社の本殿が東西に4殿並んでいる。
東の第一殿が神武天皇、第二殿が神八井耳命(神武天皇の長子。多氏の祖)、第三殿が神淳名川耳命(綏靖天皇)、第四殿が姫御神(玉依姫)を祀る。
本殿の後方に古代の祭祀場もしくは古墳と考えられている「神武塚」と呼ばれる小丘があるそうなのだが・・・鬱蒼と茂った林の中、塚の確認はできなかった。


鳥居まで戻ると、
その南東に 真新しい
「古事記」と刻んだ石柱と
小杜神社境内地図。
南に進むと古事記献上の碑。
平成24年(2012)に、『古事記』が編纂1300年を記念して建てられた。

杜の中に鎮座する小杜神社の祭神は、太安万侶。
30数年前に奈良市此瀬町の茶畑で火葬された骨や真珠が納められた木櫃と墓誌が出土したことから、この神社東方にある太安万侶の墓と伝える小円墳は見なかった。

小杜神社の南に、皇子神命神社。
林の中、忘れ去られたような古びた小さな祠が建っていた。

多神社周辺は、弥生時代から中世に至る時期の大規模な複合遺跡。
特に、弥生時代、長軸350m、短軸300mの規模をもつ拠点的な環濠集落であったと推定されている。
多神社の東約200m、集落の西のはずれに姫皇子命神社。
本殿(春日造)が東面(多神社及び他の摂社はすべて南面)しており、三輪山に昇る朝日が直射する位置、三輪山と向かいあうように建てられていた。
このあと、橿原市の新沢千塚古墳群と御所市の室大墓などを廻って帰宅。
前者の新沢千塚古墳群は、4世紀末から7世紀にかけて造営された600余基からなる大古墳群。
シルクロードの最東端にある古墳群からは、これまでペルシャ地方や中国東北部、朝鮮半島などからもたらされたとみられるガラス容器や金銀製の装身具などの副葬品が出土している。 20数年前、初めて訪ねたときは、正倉院御物の類似品が古墳から出土したことに驚いたことを思いだす。
以前あった資料館は、今春、博物館としてリニューアルオープンしていた。

後者の室大墓古墳(室宮山古墳)は、古墳時代中期前半、全長238m・後円部径105m・高さ25m・前方部幅110m・高さ22m、三段築成の巨大な前方後円墳。

孝安天皇室秋津島宮趾碑と八幡神社本殿の間の鳥居をくぐって斜面を登ると後円部の墳頂に出る。
竪穴式石室の天井石の一部がなく、そこから長持形石棺・縄掛突起が見えている。
これと並行して北側にも天井石が露出した竪穴式石室がある。

この日の探訪は、ここまで~。 走行キロ:202km、歩数:12,945歩。
下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
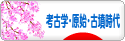
にほんブログ村
滋賀県内の遺跡・史跡などの探訪録は、
コチラ ⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2

ここは、
太安万侶らをはじめとする
古代氏族多氏の本貫地?
この冬、
纏向遺跡など田原本町内を散策した折に、
夕刻タイムアウトになったため訪れることができなかった処。
書紀 巻第三 神日本磐余彥天皇 神武天皇に
辛酉年春正月庚辰朔、天皇卽帝位於橿原宮、是歲爲天皇元年。尊正妃爲皇后、生皇子神八井命・神渟名川耳尊。
とあり、
神武天皇が即位されたこと、皇子の神八井命と神淳名川耳尊(第三子、綏靖天皇)が生まれたことなどが記載されている。
さらに、巻第四 神渟名川耳天皇 綏靖天皇に
・・・神日本磐余彥天皇崩。・・・其庶兄手硏耳命、行年已長、久歷朝機。故、亦委事而親之。然其王、立操厝懷、本乖仁義、遂以諒闇之際、威福自由、苞藏禍心、圖害二弟。・・・。
冬十一月、神渟名川耳尊、與兄神八井耳命、陰知其志而善防之。至於山陵事畢、乃使弓部稚彥造弓、倭鍛部天津眞浦造眞麛鏃、矢部作箭。及弓矢既成、神渟名川耳尊、欲以射殺手硏耳命。會有手硏耳命於片丘大窨中獨臥于大牀、時渟名川耳尊、謂神八井耳命曰「今適其時也。夫言貴密、事宜愼、故我之陰謀、本無預者。今日之事、唯吾與爾自行之耳。吾當先開窨戸、爾其射之。」
因相隨進入、神渟名川耳尊、突開其戸。神八井耳命、則手脚戰慄、不能放矢。時神渟名川耳尊、掣取其兄所持弓矢而射手硏耳命、一發中胸、再發中背、遂殺之。於是、神八井耳命、懣然自服、讓於神渟名川耳尊曰「吾是乃兄、而懦弱不能致果。今汝特挺神武、自誅元惡。宜哉乎、汝之光臨天位、以承皇祖之業。吾當爲汝輔之、奉典神祇者。」是卽多臣之始祖也。
・・・四年夏四月、神八井耳命薨。卽葬于畝傍山北。
とあり、
神武天皇の崩御後、兄(第一子)の手硏耳命が権力を欲しいままにし、二人の弟(神八井耳命と神渟名川耳尊)を殺そうと企てたが、そのことを知った二人は・・・。ふるえおののいて矢を射ることができなかった神八井耳命の弓矢を神渟名川耳尊が取って胸と背中を射抜いて殺した。これを恥じて神八井耳命は皇位を神渟名川耳尊に譲った。・・・ことなどが記載されている。
多神社(多坐弥志理都比古神社)、「みしりつひこ(=神八井耳命)」。
神武天皇の子でありながら弟に皇位を譲ったので、「身を退いた」という意味?
もっとも、末子相続制の習俗を反映かな??っていう見方も・・・。
鳥居をくぐると、整然と並んだ石灯籠。

境内の左に築地塀で囲まれた神職の館。

正面、拝殿の後ろに春日造社殿1間社の本殿が東西に4殿並んでいる。
東の第一殿が神武天皇、第二殿が神八井耳命(神武天皇の長子。多氏の祖)、第三殿が神淳名川耳命(綏靖天皇)、第四殿が姫御神(玉依姫)を祀る。
本殿の後方に古代の祭祀場もしくは古墳と考えられている「神武塚」と呼ばれる小丘があるそうなのだが・・・鬱蒼と茂った林の中、塚の確認はできなかった。


鳥居まで戻ると、
その南東に 真新しい
「古事記」と刻んだ石柱と
小杜神社境内地図。
南に進むと古事記献上の碑。
平成24年(2012)に、『古事記』が編纂1300年を記念して建てられた。

杜の中に鎮座する小杜神社の祭神は、太安万侶。
30数年前に奈良市此瀬町の茶畑で火葬された骨や真珠が納められた木櫃と墓誌が出土したことから、この神社東方にある太安万侶の墓と伝える小円墳は見なかった。

小杜神社の南に、皇子神命神社。
林の中、忘れ去られたような古びた小さな祠が建っていた。

多神社周辺は、弥生時代から中世に至る時期の大規模な複合遺跡。
特に、弥生時代、長軸350m、短軸300mの規模をもつ拠点的な環濠集落であったと推定されている。
多神社の東約200m、集落の西のはずれに姫皇子命神社。
本殿(春日造)が東面(多神社及び他の摂社はすべて南面)しており、三輪山に昇る朝日が直射する位置、三輪山と向かいあうように建てられていた。
このあと、橿原市の新沢千塚古墳群と御所市の室大墓などを廻って帰宅。
前者の新沢千塚古墳群は、4世紀末から7世紀にかけて造営された600余基からなる大古墳群。
シルクロードの最東端にある古墳群からは、これまでペルシャ地方や中国東北部、朝鮮半島などからもたらされたとみられるガラス容器や金銀製の装身具などの副葬品が出土している。 20数年前、初めて訪ねたときは、正倉院御物の類似品が古墳から出土したことに驚いたことを思いだす。
以前あった資料館は、今春、博物館としてリニューアルオープンしていた。

後者の室大墓古墳(室宮山古墳)は、古墳時代中期前半、全長238m・後円部径105m・高さ25m・前方部幅110m・高さ22m、三段築成の巨大な前方後円墳。

孝安天皇室秋津島宮趾碑と八幡神社本殿の間の鳥居をくぐって斜面を登ると後円部の墳頂に出る。
竪穴式石室の天井石の一部がなく、そこから長持形石棺・縄掛突起が見えている。
これと並行して北側にも天井石が露出した竪穴式石室がある。

この日の探訪は、ここまで~。 走行キロ:202km、歩数:12,945歩。
下のバナー「考古学・原始・古墳時代」をクリックしてね
・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)
にほんブログ村
滋賀県内の遺跡・史跡などの探訪録は、
コチラ ⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/takedream2



