2014年01月16日
河内の国・丹比野を歩く
前日(1月10日)、夜明け前まで降り15cmほど積った雪も好天気により昼前まですっかり融けてしまった。
今回は、近時、何かと話題(徳洲会病院)の多い松原市界隈を歩いた。

近鉄・河内松原駅前バスターミナル③番から近鉄バス・余部行に乗って15分ほどで下黒山BS下車(運賃240円)。
ちなみに車両はISUZUの中型ERGAmio。乗客は私だけの貸切。DRさんに尋ねると午前中、駅発の乗客はほとんどいないとのこと・・・。

丹比神社(堺市美原区)
下黒山BSから東南東、古い家が並ぶ細い道を歩くと直ぐに新興住宅の並ぶその南に林が見えた。
反正天皇の名代である丹比部の管理者であった丹比連の祖神を祀る。のち宣化天皇の末裔・丹比公(のちに真人)の支配地に替わったため多治比真人一族の祖神を加えた?
主祭神は火明命と瑞歯別命とのことなのだが、この火明命(天照国照彦火明命)、がよく分からない。
書紀では天忍穂耳命の子で、邇邇芸命の兄とも父とも・・・。
古事記では天火明命と表記。
先代旧事本紀には物部連の祖である天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊。
播磨国風土記では大己貴神の子とも・・・。 さてさて、如何~。

境内に入ると直ぐに目に付いたのが「多遅比瑞歯別の命 産湯の井戸」。 以下、その碑文。
仁徳天皇と磐の媛の間にお産れになった皇子で若松宮と称し、この井戸の水で産湯を使わしめられたと云う事が今の世まで語り傳えられている この人は後の十八代反正天皇のことである。
「多治井(丹比)氏」には、左大臣となった嶋をはじめ、かぐや姫の求婚者のひとり平城京の造営長官であった池守や催鋳銭司(和同開珎の鋳造総責任者)であった三宅麻呂(※)がいる。
※『続日本紀 巻第四 元明天皇』和銅元年(708)2月11日。
なお、碑文には命の名の「遅」は「羊」ではなく「寺」をあてていた。
また、古事記(下巻)に反正天皇の出生記事があるがその場所の記載はなく、書紀(巻大十二)は誕生地を淡路島としている。
記紀ともに反正天皇の記事は異常に少ないが、何故?

拝殿から見る参道は長い。
両側の新興住宅地を過ぎると道も狭く古い家並みが続き、往時の勢いを感じる。


丹比廃寺跡(徳泉寺跡。堺市美原区)
美原体育館とグランドの間の道を東進すると道路の右(南側)にコンクリートで固められ一段高くなったところに石碑と礎石が現われた。道路の北側の段上にも小さな祠、ということは遺構が道路により分断されている?
以下、説明板の表記、
塔の心礎と出土する古瓦から奈良時代前期に創建された丹比氏の氏寺と考えられる大寺の跡です。
いい伝えによると、弘法大師によって開創された徳泉寺は、天正年間織田信長に反旗をひるがえした松永久秀によって伽藍が破壊されるなど、破壊と再興を繰り返しましたが、昭和14年火災にあい、以後再建されることなく現在に至っています。
とのこと。
一方、「美原町史」には、
松永久秀が徳泉寺の伽藍を破却して徳泉寺城を構えたが、久秀の敗退により破棄されたという。
「河内志」に「在多治井村 松永久秀所拠」とみえる。字名の「徳泉寺」周辺に「城北」・「城北上」・「城北下」・「城山」・「城山南」などがある。
多治井地区の東は、南から北へ台地を浸食して流れる東除川に面する急崖になっており、東からの敵に備えるにはうってつけの場所である。推定地は、古代の丹比廃寺と重複するものと思われる。
とあることから、説明板記載の『破壊』は松永久秀による城への転用(再構築)のことか?

みはら歴史博物館(堺市美原区)

丹比神社まで戻って阪和自動車道の北にある歴史博物館ニ立ち寄る。
以前来た時(15年ほど前?)にはなかった施設。
メインの展示は、河内鋳物師(常設展示室1)と黒姫山古墳(常設展示室2)の2つ。
前者は、平安時代から室町時代にかけて美原地域で活躍した鋳造技術者集団。
展示室のガラス床の下に真福寺(黒山)遺跡の「梵鐘鋳造土坑」を展示。
後者から出土した短甲、冑などを展示。
なお、今回訪れたときは、これらに加えて午年にちなんで「馬の郷土玩具」約100点の展示されていた。

黒姫山古墳(堺市美原区。古墳時代中期(5世紀中頃)、全長114m、二段築成の前方後円墳。後円部の埋葬施設は盗掘により破壊・消滅。)
前方部中央の竪穴式石室から鋲留短甲24領・衝角付冑11領・眉庇付冑13領のほか大量の鉄製武具・武器が出土。第17代履中天皇の皇后黒姫の墓とも伝えられているが丹比氏の古墳とも? 中世に砦として使用。
歴史博物館のすぐ西にあるが、一旦、南に下がって阪和自動車道沿いを西進しなければいけない。道路の新設整備中なので、これができれば迂回しなくても行けるようになる?

ガイダンス施設に立寄る。
古墳のリーフレットあり。
5回/日、決った時間に映像を流すだけ・・・管理人さん?がいたのだけれど、無愛想~で、話しかけるも応答なし。
施設の南に石室を復元展示。
天井石が2枚
残りはどこ?

周濠に沿って東北から南側を西北まで移動。
以前は陸橋があり墳丘に上がったような記憶があるのだが・・・水濠とフェンスで立ち入り不可。
前方部西面のテラスに復元・円筒埴輪が並べられていた。
 黒姫山古墳の西、府道309号を北進。
黒姫山古墳の西、府道309号を北進。
鍋宮大明神碑(堺市美原区。日本御鋳物師発祥地)・太井遺跡(大保の南側)
道の西沿いに「日本御鋳物師発祥地碑」。 その奥に「鍋宮大明神碑」と「大保千軒之碑」。
この辺りは、百済系の鋳物師の集落跡。奈良時代には和同開珎や東大寺大仏、平安~室町時代には梵鐘(「河内国丹南郡○○」の銘)・鰐口・風呂釜の鋳造に従事したものの、南北朝の動乱の頃に新たな庇護者と需要を求めて全国に分散したとのこと。
「日本御鋳物師発祥地碑」には、
鍋宮大明神は別名烏丸大明神とも称し千余年以前この地域一円に居住していた御鋳物師達が、その祖神石凝姥命を主神として祭祀した御社であり、明治初年廃社となって広国神社に合祀されている。この地は鍋宮大明神神域の一部であって史蹟地として昭和四十四年十月、地元有志によって碑石を建立し永久に記念したものである。当時の御鋳物師達は中世紀以降全国各地に移住し、今では河内鋳物の往時をしのぶ面影もないが、この地域は鋳物発祥の地であり、日本文化発展に寄与貢献した御鋳物師達とその末裔の功績を永遠に讃え顕彰するものである。
また、「大保千軒之碑」には
国々の鋳物師、いづれにありても皆石凝姥命の苗末裔にて藤原朝臣河内国丹比の大保の系図にたがふことなし 皆大保村の鍋宮大明神の産土神なり
さらに、
平安時代末から室町時代にかけて、大保を中心に美原町(河内国丹南郡)周辺は、河内鋳物師と呼ばれた鋳造技術集団の本拠地であった。
河内鋳物師は高度な技術を駆使して、東大寺大仏の補修、鎌倉大仏の造営、社寺の梵鐘、仏具、農具、河内鍋、お釜等の生活用具まで、多種多様な鋳物製品を全国に供給しており、その繁栄ぶりを大保千軒と呼称された。
大保は、鋳物師の長に朝廷より賜った官位でそのまま地名になっている。
 府道309号を挟んで鍋宮大明神碑の東北に
府道309号を挟んで鍋宮大明神碑の東北に
広国神社(堺市美原区。主祭神:第二十六代安閑天皇=廣國押武金日命)
本殿の横に鍋宮大明神(烏丸大明神)の小さな祠。



境内に黒姫山古墳石室の天井石一枚(水路の橋として利用されていた)と鋳物製の大鍋(「河内鍋」。径140cm)を展示。
鳥居横に説明板が有るのだけれど文字が消えて判読できない。ここまでの堺市市内の説明板は似たような状態、なんとかならないものか・・・。

畦道や昔ながらの路地を抜けて北進。


来迎寺(松原市。融通念仏宗)・丹南藩陣屋址
府道2号(竹内街道?)を背にして来迎寺があった。山門は南西側。
天平3年(731)、狭山池の水利工事で亡くなった方を供養するために行基が毘沙門天を祀ったのが始まりとか・・・。
門前に「丹南藩主高木主水正陣屋址」の石碑。
丹南藩? ・・・ 徳川氏の旗本。大阪夏の陣において「平野の戦い」で真田軍を敗退させた功績により当地で1万石の藩主になったそうな。
来迎寺から中高野街道を北上し、途中、右折(東進)して丹比柴籬神社へ。


途中、岡で竹内街道とクロス。 ポケットパークには「中高野街道」の石碑。
高野街道?・・・京・大坂から高野山への参詣道。京を起点とする東高野街道、大坂・杭全神社近くを起点とする中高野街道、大坂・四天王寺を起点とする下高野街道、堺を起点とする西高野街道の4ルートがあり、合流して河内長野市で一本になる。高野山近くの「町石道」は咋秋に訪ねた。
竹内街道?・・・難波と大和飛鳥を結ぶ幹線道路であった丹比道を整備・拡張して造設されたとも、日本最古の官道。書紀巻第二十二推古天皇二十一年(613)の条に「難波より京に至る大道を置く」とある。




丹比柴籬神社(松原市。5C後半の創建。河内丹比の柴籬宮)
第18代反正天皇(仁徳天皇第三皇子。「倭の五王」のひとり「珍」?)の都跡との伝承。
書紀に「冬十月、河内の丹比に都を造った。これを柴籬宮という。」とある。
この日、「開運松原六社めぐり(※)」の開催中のためか、多くの参拝者が見られた。
※ 年の始まりに阿保神社・阿麻美許曽神社・我堂八幡宮・柴籬神社・布忍神社・屯倉神社の六社を「めぐり・はじめる」参拝により、神々のご加護のもと、より良い年となるように開運を祈するものとのこと。
松原市郷土資料館(松原市)
丹比柴籬神社の北隣、松原市民ふるさとピアザ1階。無人・無料。
旧石器時代などの出土品の展示をはじめ、難波大道や大和川の付け替えの解説など。
丹比大溝(松原市)
 近鉄河内松原駅前にある「ゆめニティまつばら」に付設された立体駐車場の南から南西方向に幅10mほどの未利用地がのびている。あるはずの説明板が見当たらない。
近鉄河内松原駅前にある「ゆめニティまつばら」に付設された立体駐車場の南から南西方向に幅10mほどの未利用地がのびている。あるはずの説明板が見当たらない。
この大溝は、狭山池から大和川に流入している東除川と西除川を結んだ水路。延長4km、幅10m、深さ3m。羽曳野丘陵から派生する段丘上をほぼ標高23mの等高線に沿って開削されている。灌漑用だけではなく運河としての役割も担っていたか?
約3時間半の散策。
今回、予定していて行けなかった「大塚山古墳」と「大津神社」は、今後の楽しみ・・・。
今回は、近時、何かと話題(徳洲会病院)の多い松原市界隈を歩いた。
近鉄・河内松原駅前バスターミナル③番から近鉄バス・余部行に乗って15分ほどで下黒山BS下車(運賃240円)。
ちなみに車両はISUZUの中型ERGAmio。乗客は私だけの貸切。DRさんに尋ねると午前中、駅発の乗客はほとんどいないとのこと・・・。
丹比神社(堺市美原区)
下黒山BSから東南東、古い家が並ぶ細い道を歩くと直ぐに新興住宅の並ぶその南に林が見えた。
反正天皇の名代である丹比部の管理者であった丹比連の祖神を祀る。のち宣化天皇の末裔・丹比公(のちに真人)の支配地に替わったため多治比真人一族の祖神を加えた?
主祭神は火明命と瑞歯別命とのことなのだが、この火明命(天照国照彦火明命)、がよく分からない。
書紀では天忍穂耳命の子で、邇邇芸命の兄とも父とも・・・。
古事記では天火明命と表記。
先代旧事本紀には物部連の祖である天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊。
播磨国風土記では大己貴神の子とも・・・。 さてさて、如何~。
境内に入ると直ぐに目に付いたのが「多遅比瑞歯別の命 産湯の井戸」。 以下、その碑文。
仁徳天皇と磐の媛の間にお産れになった皇子で若松宮と称し、この井戸の水で産湯を使わしめられたと云う事が今の世まで語り傳えられている この人は後の十八代反正天皇のことである。
「多治井(丹比)氏」には、左大臣となった嶋をはじめ、かぐや姫の求婚者のひとり平城京の造営長官であった池守や催鋳銭司(和同開珎の鋳造総責任者)であった三宅麻呂(※)がいる。
※『続日本紀 巻第四 元明天皇』和銅元年(708)2月11日。
なお、碑文には命の名の「遅」は「羊」ではなく「寺」をあてていた。
また、古事記(下巻)に反正天皇の出生記事があるがその場所の記載はなく、書紀(巻大十二)は誕生地を淡路島としている。
記紀ともに反正天皇の記事は異常に少ないが、何故?
拝殿から見る参道は長い。
両側の新興住宅地を過ぎると道も狭く古い家並みが続き、往時の勢いを感じる。
丹比廃寺跡(徳泉寺跡。堺市美原区)
美原体育館とグランドの間の道を東進すると道路の右(南側)にコンクリートで固められ一段高くなったところに石碑と礎石が現われた。道路の北側の段上にも小さな祠、ということは遺構が道路により分断されている?
以下、説明板の表記、
塔の心礎と出土する古瓦から奈良時代前期に創建された丹比氏の氏寺と考えられる大寺の跡です。
いい伝えによると、弘法大師によって開創された徳泉寺は、天正年間織田信長に反旗をひるがえした松永久秀によって伽藍が破壊されるなど、破壊と再興を繰り返しましたが、昭和14年火災にあい、以後再建されることなく現在に至っています。
とのこと。
一方、「美原町史」には、
松永久秀が徳泉寺の伽藍を破却して徳泉寺城を構えたが、久秀の敗退により破棄されたという。
「河内志」に「在多治井村 松永久秀所拠」とみえる。字名の「徳泉寺」周辺に「城北」・「城北上」・「城北下」・「城山」・「城山南」などがある。
多治井地区の東は、南から北へ台地を浸食して流れる東除川に面する急崖になっており、東からの敵に備えるにはうってつけの場所である。推定地は、古代の丹比廃寺と重複するものと思われる。
とあることから、説明板記載の『破壊』は松永久秀による城への転用(再構築)のことか?
みはら歴史博物館(堺市美原区)
丹比神社まで戻って阪和自動車道の北にある歴史博物館ニ立ち寄る。
以前来た時(15年ほど前?)にはなかった施設。
メインの展示は、河内鋳物師(常設展示室1)と黒姫山古墳(常設展示室2)の2つ。
前者は、平安時代から室町時代にかけて美原地域で活躍した鋳造技術者集団。
展示室のガラス床の下に真福寺(黒山)遺跡の「梵鐘鋳造土坑」を展示。
後者から出土した短甲、冑などを展示。
なお、今回訪れたときは、これらに加えて午年にちなんで「馬の郷土玩具」約100点の展示されていた。
黒姫山古墳(堺市美原区。古墳時代中期(5世紀中頃)、全長114m、二段築成の前方後円墳。後円部の埋葬施設は盗掘により破壊・消滅。)
前方部中央の竪穴式石室から鋲留短甲24領・衝角付冑11領・眉庇付冑13領のほか大量の鉄製武具・武器が出土。第17代履中天皇の皇后黒姫の墓とも伝えられているが丹比氏の古墳とも? 中世に砦として使用。
歴史博物館のすぐ西にあるが、一旦、南に下がって阪和自動車道沿いを西進しなければいけない。道路の新設整備中なので、これができれば迂回しなくても行けるようになる?
ガイダンス施設に立寄る。
古墳のリーフレットあり。
5回/日、決った時間に映像を流すだけ・・・管理人さん?がいたのだけれど、無愛想~で、話しかけるも応答なし。
施設の南に石室を復元展示。
天井石が2枚
残りはどこ?
周濠に沿って東北から南側を西北まで移動。
以前は陸橋があり墳丘に上がったような記憶があるのだが・・・水濠とフェンスで立ち入り不可。
前方部西面のテラスに復元・円筒埴輪が並べられていた。
鍋宮大明神碑(堺市美原区。日本御鋳物師発祥地)・太井遺跡(大保の南側)
道の西沿いに「日本御鋳物師発祥地碑」。 その奥に「鍋宮大明神碑」と「大保千軒之碑」。
この辺りは、百済系の鋳物師の集落跡。奈良時代には和同開珎や東大寺大仏、平安~室町時代には梵鐘(「河内国丹南郡○○」の銘)・鰐口・風呂釜の鋳造に従事したものの、南北朝の動乱の頃に新たな庇護者と需要を求めて全国に分散したとのこと。
「日本御鋳物師発祥地碑」には、
鍋宮大明神は別名烏丸大明神とも称し千余年以前この地域一円に居住していた御鋳物師達が、その祖神石凝姥命を主神として祭祀した御社であり、明治初年廃社となって広国神社に合祀されている。この地は鍋宮大明神神域の一部であって史蹟地として昭和四十四年十月、地元有志によって碑石を建立し永久に記念したものである。当時の御鋳物師達は中世紀以降全国各地に移住し、今では河内鋳物の往時をしのぶ面影もないが、この地域は鋳物発祥の地であり、日本文化発展に寄与貢献した御鋳物師達とその末裔の功績を永遠に讃え顕彰するものである。
また、「大保千軒之碑」には
国々の鋳物師、いづれにありても皆石凝姥命の苗末裔にて藤原朝臣河内国丹比の大保の系図にたがふことなし 皆大保村の鍋宮大明神の産土神なり
さらに、
平安時代末から室町時代にかけて、大保を中心に美原町(河内国丹南郡)周辺は、河内鋳物師と呼ばれた鋳造技術集団の本拠地であった。
河内鋳物師は高度な技術を駆使して、東大寺大仏の補修、鎌倉大仏の造営、社寺の梵鐘、仏具、農具、河内鍋、お釜等の生活用具まで、多種多様な鋳物製品を全国に供給しており、その繁栄ぶりを大保千軒と呼称された。
大保は、鋳物師の長に朝廷より賜った官位でそのまま地名になっている。
広国神社(堺市美原区。主祭神:第二十六代安閑天皇=廣國押武金日命)
本殿の横に鍋宮大明神(烏丸大明神)の小さな祠。
境内に黒姫山古墳石室の天井石一枚(水路の橋として利用されていた)と鋳物製の大鍋(「河内鍋」。径140cm)を展示。
鳥居横に説明板が有るのだけれど文字が消えて判読できない。ここまでの堺市市内の説明板は似たような状態、なんとかならないものか・・・。
畦道や昔ながらの路地を抜けて北進。
来迎寺(松原市。融通念仏宗)・丹南藩陣屋址
府道2号(竹内街道?)を背にして来迎寺があった。山門は南西側。
天平3年(731)、狭山池の水利工事で亡くなった方を供養するために行基が毘沙門天を祀ったのが始まりとか・・・。
門前に「丹南藩主高木主水正陣屋址」の石碑。
丹南藩? ・・・ 徳川氏の旗本。大阪夏の陣において「平野の戦い」で真田軍を敗退させた功績により当地で1万石の藩主になったそうな。
来迎寺から中高野街道を北上し、途中、右折(東進)して丹比柴籬神社へ。
途中、岡で竹内街道とクロス。 ポケットパークには「中高野街道」の石碑。
高野街道?・・・京・大坂から高野山への参詣道。京を起点とする東高野街道、大坂・杭全神社近くを起点とする中高野街道、大坂・四天王寺を起点とする下高野街道、堺を起点とする西高野街道の4ルートがあり、合流して河内長野市で一本になる。高野山近くの「町石道」は咋秋に訪ねた。
竹内街道?・・・難波と大和飛鳥を結ぶ幹線道路であった丹比道を整備・拡張して造設されたとも、日本最古の官道。書紀巻第二十二推古天皇二十一年(613)の条に「難波より京に至る大道を置く」とある。
丹比柴籬神社(松原市。5C後半の創建。河内丹比の柴籬宮)
第18代反正天皇(仁徳天皇第三皇子。「倭の五王」のひとり「珍」?)の都跡との伝承。
書紀に「冬十月、河内の丹比に都を造った。これを柴籬宮という。」とある。
この日、「開運松原六社めぐり(※)」の開催中のためか、多くの参拝者が見られた。
※ 年の始まりに阿保神社・阿麻美許曽神社・我堂八幡宮・柴籬神社・布忍神社・屯倉神社の六社を「めぐり・はじめる」参拝により、神々のご加護のもと、より良い年となるように開運を祈するものとのこと。
松原市郷土資料館(松原市)
丹比柴籬神社の北隣、松原市民ふるさとピアザ1階。無人・無料。
旧石器時代などの出土品の展示をはじめ、難波大道や大和川の付け替えの解説など。
丹比大溝(松原市)
この大溝は、狭山池から大和川に流入している東除川と西除川を結んだ水路。延長4km、幅10m、深さ3m。羽曳野丘陵から派生する段丘上をほぼ標高23mの等高線に沿って開削されている。灌漑用だけではなく運河としての役割も担っていたか?
約3時間半の散策。
今回、予定していて行けなかった「大塚山古墳」と「大津神社」は、今後の楽しみ・・・。
下のバナー「歴史ブログ」をクリックしてね ・・・ 「歴史」のブログがいっ~ぱい見れるよ (^J^)



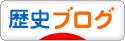
にほんブログ村



にほんブログ村
大和の国を歩く ~ 本薬師寺
飛鳥へ ~ 都塚古墳を訪ねる
奈良・春日山原始林を歩く
大和の国を訪ねる(2)・・・多神社・多遺跡、新沢千塚古墳群、室大墓へ
大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その3)
大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その2)
飛鳥へ ~ 都塚古墳を訪ねる
奈良・春日山原始林を歩く
大和の国を訪ねる(2)・・・多神社・多遺跡、新沢千塚古墳群、室大墓へ
大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その3)
大和国・平群の谷を歩く~古代の祭祀遺構を訪ねて(その2)










